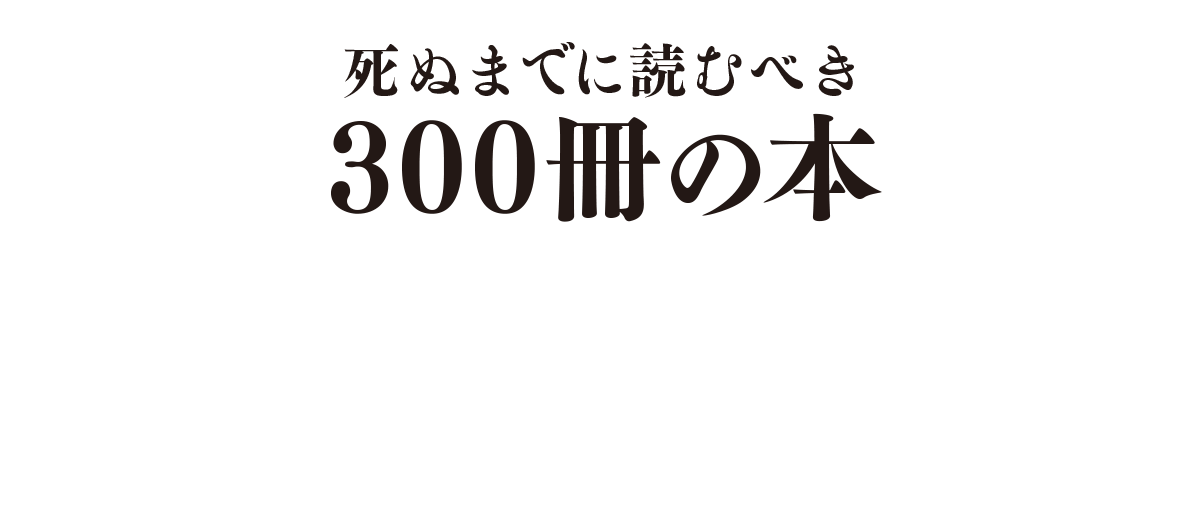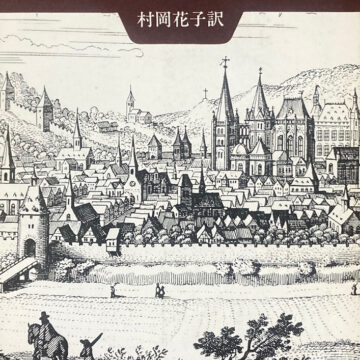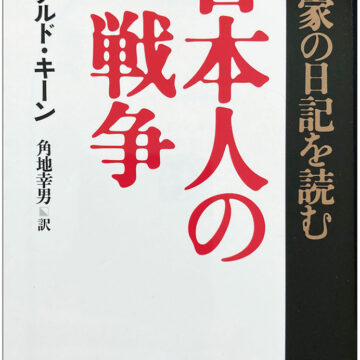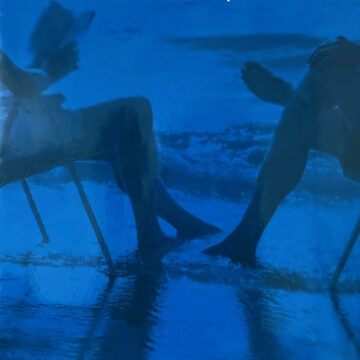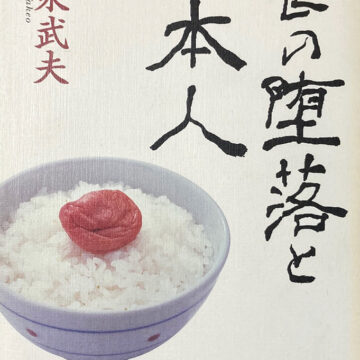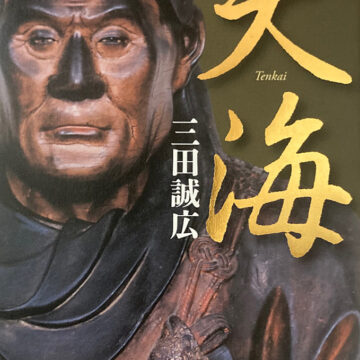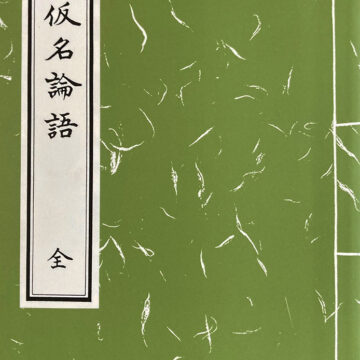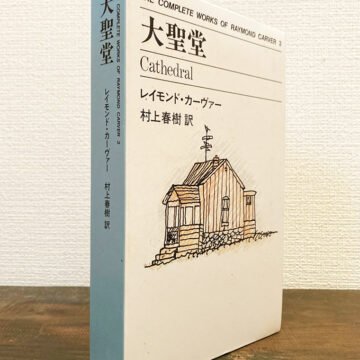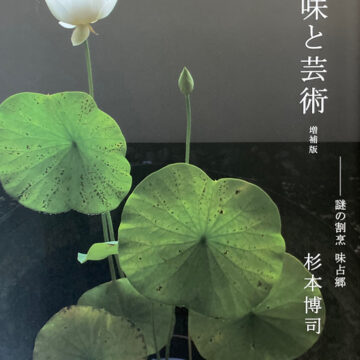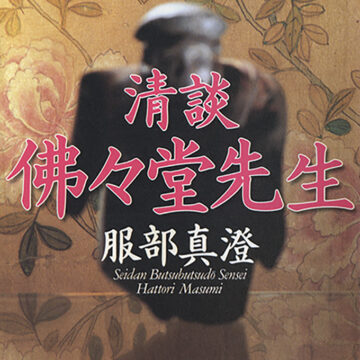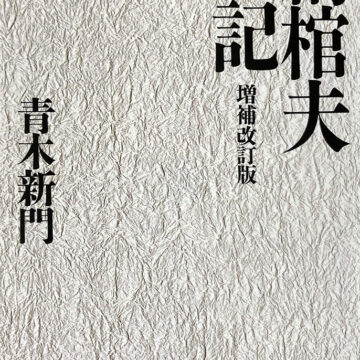どんなに時代が変わろうとも、本が人類の知的財産であることに変わりはありません。
少年の時分より、本を師と仰ぐ髙久 多樂がさまざまなジャンルから独断と偏見で選んだ300冊の本。
本選びの際の参考書として、活用してください。【テキスト/髙久 多樂】
Topics
file.192『クリスマス・カロル』チャールズ・ディケンズ 村岡花子訳 新潮文庫
本書の主人公・スクルージほどではないにせよ、私はクリスマスに心を動かされたことがほとんどない。キリスト教徒でもないのになんで祝ったり贈り物を交換したりケーキを食べたりするわけ?とい…
file.191『日本人の戦争』ドナルド・キーン 角地幸男訳 文春文庫
近代になるまで、日本には外国人が容易に同化できない3つの〝鉄壁〟が備わっていた。周りを海で囲まれた島国であったこと、すぐに習得ができない複雑な日本語があったこと、そして2000年以…
file.190『ロゴスの市』乙川優三郎 徳間文庫
時代小説の名手・乙川優三郎は、2013年に発表した『脊梁山脈』以降、現代文学を書き続けている。乙川の現代文学には特徴がある。主人公が小説家・編集者・翻訳家・同時通訳者・装丁家・コピ…
file.189『食の堕落と日本人』小泉武夫 東洋経済新聞社
本書には小泉さんの怒りが渦巻いている。「日本人というのは、昔から主に魚を食し、雑穀根茎、陸稲水稲を食うという食生活を何千年にもわたってつくりあげてきて、その食文化の範囲の中で生きて…
file.188『天海』三田誠広 作品社
日本の歴史には名僧・怪僧が百出する。そのなかでもひときわ特異な存在感を示すのが天海だ。徳川家康から家光まで、徳川幕府の黎明期を支えた大人物として天海の名は永遠に刻まれるだろう。しか…
file.187『仮名論語』論語普及会
こういう時勢だから、あらためて『論語』を読んでみたいと思う人も少なくないだろう。問題はなにを読むか。なにしろ『論語』に関する本は数え切れないほどある。私のイチオシは上掲の『仮名論語…
file.186『大聖堂』レイモンド・カーヴァー 村上春樹訳 中央公論社
レイモンド・カーヴァーと言えば、ミニマリズムの代表的な作家である。ミニマリズムを的確に訳す言葉を知らないが、あえて表現すれば「半径五十メートルの作家」とでも言えばいいだろうか。つま…
file.185『趣味と芸術 ―謎の割烹 味占郷』杉本博司 講談社
前回はユニークな数奇者が主人公の小説だったが、今回は現代の数奇者が夢想する割烹を舞台にした会食の数々を覗いてみたい。タイトルはNHKのテキストのようだが、これは作者特有の煙幕であろ…
file.184『清談 佛々堂先生』服部真澄 講談社
タイトルにもある佛々堂先生とはいかなる人物か?本書には4つの短編が収められているが、そのいずれにも佛々堂先生の描写がある。それらを総合すれば、以下のようになるだろう。・古美術、骨董…
file.183『納棺夫日記』青木新門 文春文庫
人は自分の死について、四六時中深く考えることはしない。日常に忙殺されてそれどころではないという事情もあるだろうし、考えてもわからないことをあえて考えないということもあるだろう。しか…