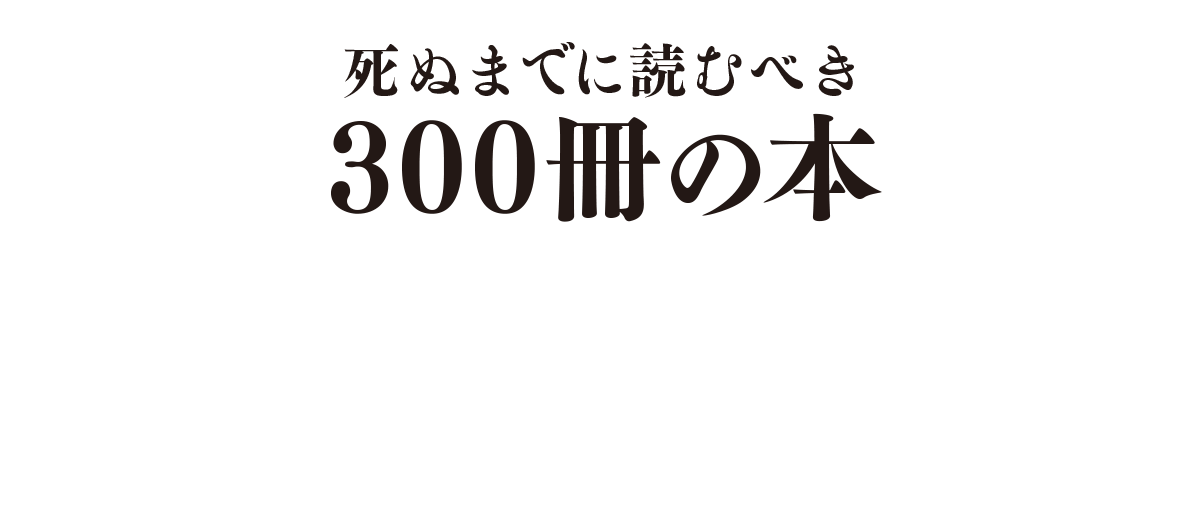言葉の力を信じる男と女の真摯な交歓

時代小説の名手・乙川優三郎は、2013年に発表した『脊梁山脈』以降、現代文学を書き続けている。
乙川の現代文学には特徴がある。主人公が小説家・編集者・翻訳家・同時通訳者・装丁家・コピーライターなど言葉に関わる仕事をしている人が多いこと。そして御宿(おんじゅく)や鴨川などの房総が頻繁に出てくることである。
若き日のジョン・アーヴィンは、レスリングとウィーンを定番のように書いていたが、定番のモチーフはマンネリ化を生む危険性があると同時に作家の強固な軸にもなりえる。2015年に発表された本作『ロゴスの市』の主人公は翻訳家と同時通訳者であり、重要な舞台として御宿が出てくる。今のところ乙川優三郎の現代小説の頂点にあると思う。ちなみにロゴスとは言葉や真理という意味をいう。
主人公は、成川弘之と戒能(かいの)悠子。のんびりした性格の弘之は翻訳家を、せっかちでそつのない行動をする悠子は同時通訳者を目指している。20歳で出会った二人は、つかず離れずの関係で30年余りの歳月をおくり、やがて意外な結末へと進んでいく。
二人がそれぞれのフィールドで言葉と格闘し、スキルを磨き上げていく過程に感嘆する。いずれも英語を日本語に移し替える仕事だが、それぞれの言語が持つ特徴をできるだけ損なうことなく移し替えをするには非常な困難が伴う。職人が皮膚感覚で繊細な技術と感性を養うに等しいが、その微細な進歩が読者にもわかるよう微に入り細を穿つ描写が続く。
この作品では「言葉」という、人類に与えられた至高の超能力について、さまざまな角度からその本質を探っている。そもそも言葉ってなんだろう? と問いかけないではいられない。
言葉に対する二人の真摯なアプローチは、スコット・フィツジェラルドの『華麗なるギャツビー』で、ニック・キャラウェイが発した言葉、「結局、人生はひとつの窓から眺めた方がよく見える」そのものである。いみじくも乙川優三郎は初の現代小説『脊梁山脈』でこの言葉が引用している。
だれにも「ひとつの窓」があるはず。音楽家は音楽を通して、接客業の人は人をもてなすことにおいて、社会や人間模様をつぶさに観察し、それで自身の人生を豊かに彩ることができる。問題は、自分に合った「ひとつの窓」をいかにして見つけ出し、磨き上げるかだが、その過程こそがこの世に生まれてきた意義なのではないだろうか。
この小説には、登場人物の言葉を借りて、著者の思いが発露されている。いくつか引用しよう。
「読者には小説の中の偶然を作り事として嫌う人がいますが、現実の偶然すら知らない凡庸な生活を送る人たちだと思います」
これは悠子の言葉だが、同感である。本を読まない人が増えているが、本を読む習慣がある人でも小説は読まないという人が珍しくない。つねづね、なんともったいない生き方をしているのかと思っていた。
「少し古いというだけで優れた小説が絶版になり、かわりに量産される粗削りな作品が書店の棚をにぎわす時代であった」
日本最大級の書店でさえ、良書は少ない。例えば乙川優三郎の著作33作のうち、何冊常備しているかを調べたら、ほんの数冊しかなかった。平積みになっている本の大半はハウツーものや時事的なもの、有名人が書いたものばかり。手にとって見てみたいと思えるのは100冊に1冊くらいしかない。もちろん、それは書店だけに原因があるわけではないが。
……それはそれとして、『ロゴスの市』の海にたゆたっているときの蕩けるような感覚といったら! 思い出すだけでうっとりしてくる。
髙久多樂の新刊『紺碧の将』発売中
https://www.compass-point.jp/book/konpeki.html
本サイトの髙久の連載記事