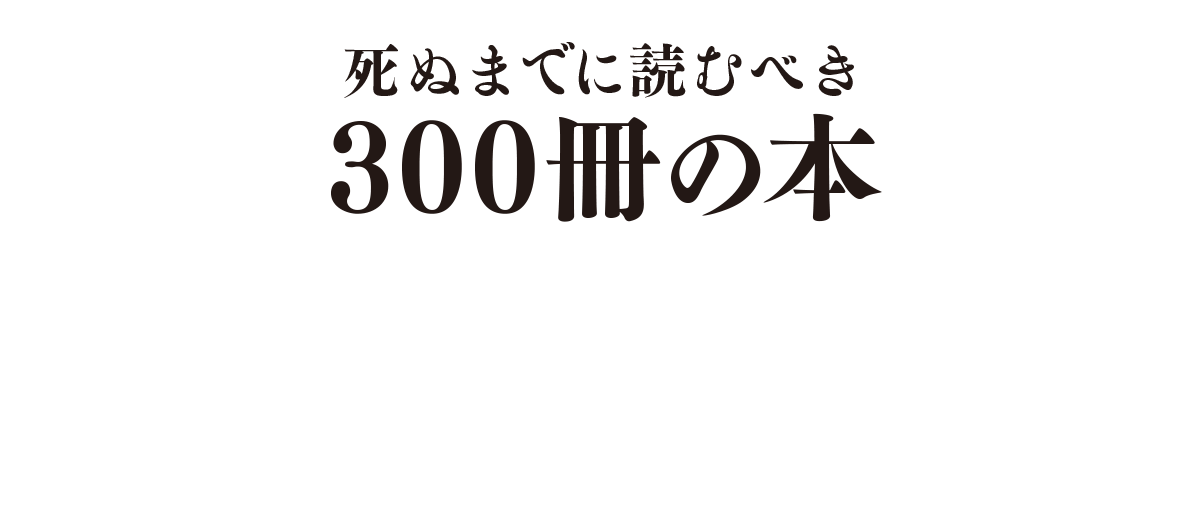複眼的に明治維新を見る
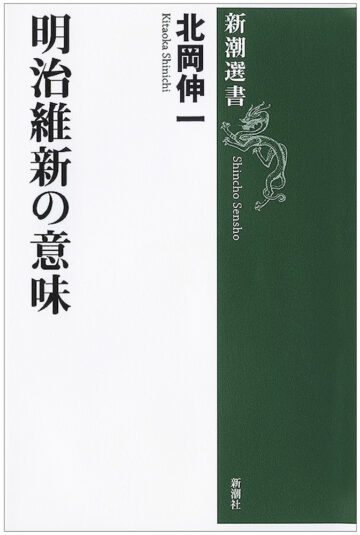
明治維新関連の本は、事実を詳細に記したものから小説の類まで含めれば、どれほどの数になるだろう。
私にとって、明治維新の決定版が2020年、刊行された。それが本書。
著者の北岡伸一氏の歴史観には新聞の論説などでたびたび触れていたが、近代の政治史に関して私がもっとも信頼する一人である。過去に起きたこと(歴史)への眼差しが透明で怜悧。情に流されず、リアリズムを理解している。かといって、左翼史観者のように偏っていない。もちろん、右にも偏っていない。ひとことでいえば、気持ちがいいくらいにバランスがいいのだ。
もうひとつ、これはきわめて個人的な理由でもあるのだが、明治維新から近代国家創生にかけて、もっとも重要な人物として大久保利通にフォーカス意していること。本来、それは当然だと思うが、そういう歴史観をもつ人は少ない。
まず、明治維新をどうとらえるかで書き手のスタンスが大きく異る。その点について、北岡氏はこのように自らの立ち位置を明らかにしている。
――岡義武は、明治維新はマルクス主義のカテゴリーにあてはまらない民族革命であるという主張を行った。すなわち、明治維新は、西洋の脅威に直面した日本が、近代化を遂げなければ独立を維持できないと考えて行った革命であった。筆者もこの立場をとる。
マルクス史観の人は、どうしても革命は民衆の力によってなされたと思いたがるが、明治維新の経緯をつぶさに概観すればわかるように、けっしてそんなことはない。ごくごく少数の下級志士が決起し、その都度潰されながら少しずつ大きな波紋となって広がった。民衆は、大きな流れについていっただけだ。
北岡氏はこうも書いている。
――国家は国際関係の中に存在する。よくその国の舵取りを行う有能な権力者と、そうでない権力者がいる。またその国家をよりよく発展させる権力と、そうでない権力とがある。こうした権力の質を論じることが、実は政治史研究の中心課題である。それは、権力は下部構造によって基本的に規定されるとするマルクス主義と対極にある考え方である。
明治維新は黒船による外圧があって初めて胎動が生じた。ということは、それ以降の事の是非は、対外関係を俯瞰しながら判断しなければならないということ。
なるほど、平和が続くということは、こういう一面もあるのだなと目からウロコが落ちたくだりがある。それは、徳川の幕藩体制が続いた260余年の間、戦乱がないのと引き換えに科学技術が衰退したということ。幕末の長州征伐に従った譜代大名の家臣は、大阪夏の陣とほとんど同じ武器を携えていたという。幕府は、最強の封建領主だったが、その優位は、幕末に西洋列強から新しい軍事技術が導入されると、たちまち失われてしまった。
戦国末期、日本にあった鉄砲の数は世界のどの国よりも多く、いわば世界一の軍事大国であった。しかし、そのころの火縄銃から、日本はほとんど進歩していなかった。
鉄砲の発展の停滞とともに、航海技術も衰退した。かつて南蛮貿易に従事して東南アジアとの間を往復することができたのに、江戸時代は、日本の沿岸航路だけになってしまった。黒船が来航したとき、西洋人が天候にかかわらず外洋に乗り出していることに日本人は衝撃を受けたというのだ。
つまり、盤石の体制ができたために、それ以上に政府(幕府)の力を強化する必要がなくなってしまったのである。西洋では、引き続く戦争がより強大な軍備を必要とし、それを支える収入を得るためブルジョアジーの政治参加を認め、議会が成立した、と北岡氏は指摘しているが、平和が続いた日本ではそういうことが起こらなかった。
北岡氏の真骨頂は「江戸時代は平和が長く続いた。よかったよかった」だけではなく、その負の面にも着目していること。平和という、だれもが希求する状況がずっと続いても、その代償はあるのだと教えてくれる。
前述したように、大久保利通に対する見方も公正だ。大久保は権力を一手に集め、有司専制と批判され、やりたい放題やったかのような言われ方をするが、じつは公議輿論という言葉をたびたび用い、「天下の大問題に自分の意見を持ち、機会があればそれを実行に移す覚悟を持ち、批判するときは対案を持って批判し、相手の批判にも耳を傾けて堂々と議論する。そういう覚悟を持つ有志の声を、ここでは問題にしている。そういう声は、身分にかかわらず尊重しなければならない」という信念をもっていた。けっして独裁的な人ではなかった。
また、急激な変化を良しとせず、漸進主義をとった。欧米視察の際、殖産興業の重要性を痛感したが、その後、主に行ったことは灌漑など農業に関する事業が中心であった。生活に困窮する士族のための事業の提供(士族授産)と関係づけて考えていたからだ。
征韓論に反対した大久保が、台湾や朝鮮半島沖に兵を出したことへの批判にも、理路整然とその理を説いている。
著者が大久保を信頼する理由は、困難に直面した場合の心構えを論じた、次の文章なのだろう。
――例えば或目的地に向かって路をゆくに当り、忽ち行詰りとなったならば、万難を排して踏破するなり、または迂回するなり、臨機に適当な手段を用いなければならぬ。そこで静定の工夫を回らしたならば、必ず何処にか活路が見出されるものである。そして行着かんとする処に到達するものである。……行詰ってただ困ったと思うばかりでは、いつ目的地に達し得るやわからぬ。人間は行詰っても、行詰らぬように心がけていなければ大事業は成し遂げられるものではない。
維新三傑と数えられるように、明治維新という革命のキーパーソンのひとりであったことは事実だが、大久保がもっともその力を発揮したのは、明治6年から暗殺される11年までであろう。西郷は革命家であったが、大久保の本領は政治家であった。
北岡氏は大久保と西郷について、以下のように書いている。
――西郷は実は明治国家の将来についてほとんどヴィジョンを提示していない。他方で、自死願望があった。さらに健康もすぐれなかった。西郷がもっとも苦しんでいたのは、彼と共に戦ってきた兵士たちの処遇であった。革命や戦争において、もっとも難しいものは、非軍事化である。中国では裁兵と言うが、命をかけて戦ってきた人間にとって、平常に復帰することは難しい。西郷は、常に最前線で危機に立ち向かい、兵士と共にあることで、兵士の信頼を得てきた。第一次長州征伐の際の和平交渉など、その例であった。兵士たちの絶対的な信頼を得てきた西郷にとって、彼らを裏切ることはできなかった。自分を慕う仲間を裏切ることなく、しかし同志である大久保の国家建設を妨害することもなく、戦士の同胞の思い出の中に死んでいくことが、西郷の希望であったと私は考える。これは、政治的人間である大久保と、非政治的・宗教的人間である西郷の、決定的に違うところであった。
本書を読めば、明治維新という革命が、世界に類を見ないほど驚くべきスピードでなされたことがわかる。それらを担った人物たちを顕彰することは、後世に生きるわれわれの責務でもある。
●知的好奇心の高い人のためのサイト「Chinoma」10コンテンツ配信中
本サイトの髙久の連載記事
髙久の代表的著作