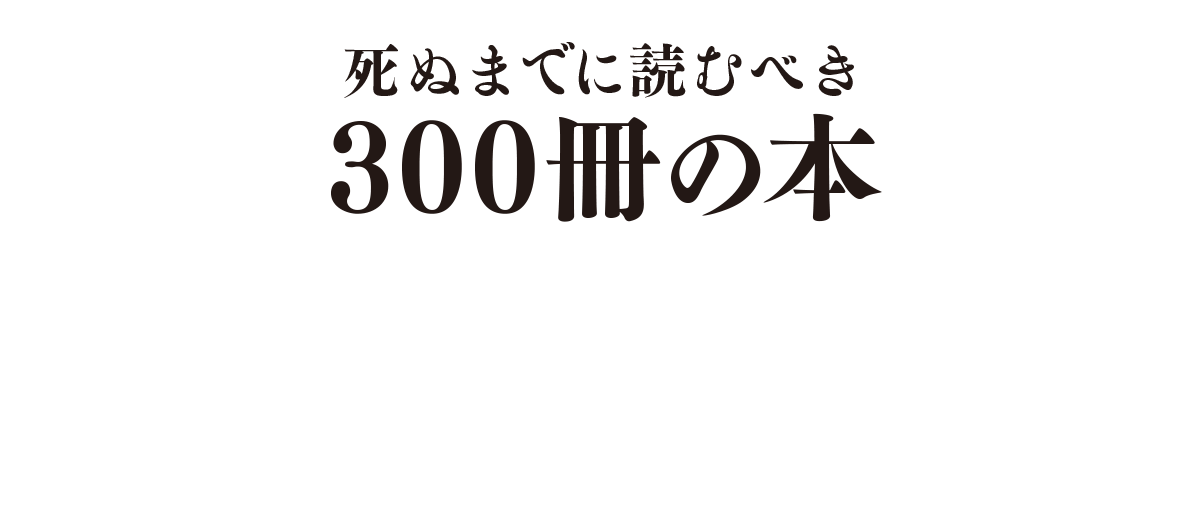家族の間にうごめく、不吉な風
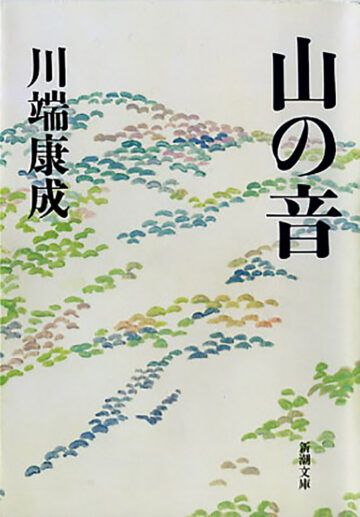
ノルウェイ・ブック・クラブは、世界54カ国の著名な作家100人の投票によって選ばれた「世界文学100選」を発表している。現在、文学ファンの間では最も権威があるという。そのなかに日本の作品が2つ選ばれている。ひとつは『源氏物語』、もうひとつが川端康成の『山の音』である。
おそらく選考にはエドワード・サイデンステッカーが加わっていたと思われる。川端の『雪国』を英訳し、川端の名を世界に知らしめた人として知られている。ノーベル文学賞受賞にも一枚噛んでいたにちがいない。
では、世界の作家が評価する日本文学の精華たるこの作品はいかなるものか。そのような好奇心で読み始めたが、ほどなくして肩透かしを食った。なぜなら、この作品は、ある家庭の人間関係に焦点を当てた、半径数十メートルが舞台の小説だからだ。淡々と家庭内の人間関係のズレがミルフィーユのように細かく積み重ねられ、大きな変化もないままに幕を閉じる。
ただ、さすがは川端と思ったこともたしか。物語の起伏はほとんどないにもかかわらず、読後、とても視界がくっきりしてきたのだ。文章によって、じっくりと読者の心象を彫琢した結果だろう。
タイトルの「山の音」は、主人公の尾形信吾が深夜、裏山で得体のしれない音を聞いたというエピソードからきている。それを聞いてから、信吾は死の影に怯えるようになる。老境に入る直前の男の微妙な心の揺れ動きが表れている。
主な登場人物は尾形信吾のほか、妻の保子、二人の子を連れて出戻りした長女の房子、長男修一と嫁の菊子。住まいは鎌倉。
時代設定は昭和30年の少し前あたりだろうか。戦争の爪痕がそこかしこに潜んでいる。修一は復員兵であり、彼の浮気相手・絹子は、戦争未亡人だ。やがて絹子は修一の子を宿すが、そのことを妻や父親に知られても積極的に解決しようとしない。戦争によって心に傷を受けたのか、すべてに虚無的だ。そういう意味では、「ロスト・ジェネレーション(失われた世代)」と揶揄されたフィツジェラルドやフォークナー、ヘミングウェイが描く世界とも通底する。
基調となるのは、信吾と菊子の淡い恋心にも似た信頼関係だ。信吾にとって菊子は息子の嫁、菊子にとって信吾は舅。男女の組み合わせとしては〝ありえない〟関係である。まして、修一と房江という〝ほんとうの子〟との間はギクシャクしている。なおさら二人の交情は厚くなる。ほかの家族も二人の心が通じ合っていることは承知している。その微妙な心の揺れ動きが日本独特の〝もののあはれ〟と言えなくもない。
あるいは信吾は、ひたひたと眼前に迫る老いの醜さ、そして死という圧倒的な生の断崖絶壁を直視したくないがため、身近なところで最も相性のいい菊子に思いを寄せているのかもしれない。菊子は尾形家のなかでは唯一のよそ者だが、血に縛られていない分、よぶんな軋轢もない。
あるいは信吾は、初恋の相手が忘れられず、それが思わぬ方向へ流れ出しているのかもしれない。ある日、彼はネクタイの結び方がわからなくなり、妻にネクタイを結んでもらっている時、ふと昔、大学を卒業し初めて背広を着た日に、妻の姉がネクタイを結んでくれたことを思い出す。彼女は妹に似ず、器量が良かった。その人に対する思いがいつまでも忘れられない。
家族とは、不思議な形態だ。人間社会のなかで最も小さな組織と言い換えてもいい。血縁がベースにあるからこそ堅固とも思われるが、その実、脆弱でもある。ちょっとした心の掛け違いで、思わぬ綻びが生じる。距離が近すぎるためだ。この作品は、家族の間にうごめく、不吉な風を描いているという点で世界クラスの評価を得たのではないか。
●知的好奇心の高い人のためのサイト「Chinoma」10コンテンツ配信中
本サイトの髙久の連載記事
髙久の代表的著作