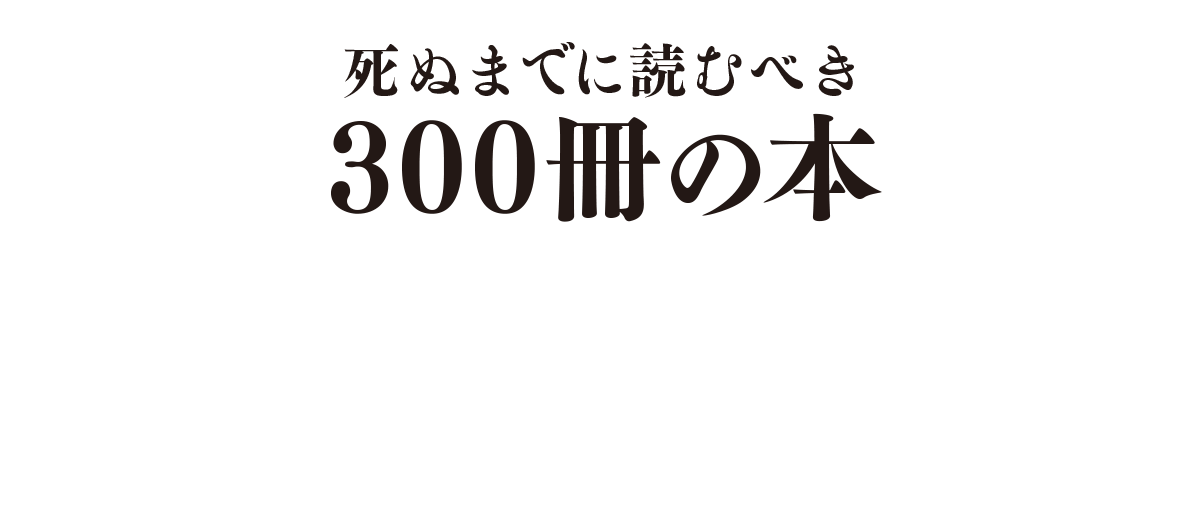信長と秀吉の橋渡しをした光秀
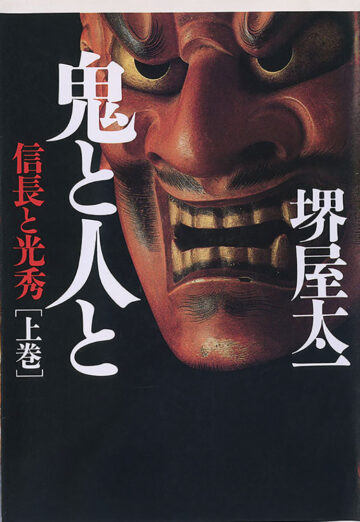
織田信長をテーマにした本や、なぜ明智光秀が信長を討ったかをテーマにした本をたくさん読んできたが、意外や意外、堺屋太一著の本書はそのジャンルの白眉といえる。なぜ「意外や意外」かといえば、堺屋は歴史の専門家ではないし、小説専門の人ではない。歴史的考察が甘かったり、あるいは表現が平板になる可能性もじゅうぶんあったはずだ。
そもそも彼は元通商産業省(現経済産業省)の官僚であり、大阪万博を成功させたキーマンである。社会を見通す眼力も広範で、「団塊の世代」というネーミングも彼による。一度、取材したことがあるが、彼の唱える道州制論は説得力があった。弁舌も上手い。つまり、堺屋太一はマルチタレントだったのだ。そして、それゆえバランス感覚がすぐれていた。そういう人が独自のアプローチで信長と光秀の人物像に迫ったのだから、「意外」ではなかったのかもしれない。
最大の成功要因は、信長と光秀の独白形式にしたことだろう。同じものを見ても、感じ方はひとそれぞれ。富士山を見て神々しいと思う人もいれば、ただの山じゃないかと思う人もいる。ものの見方は、人の違いを露わにする。
武田勝頼の首を見る信長の独白から始まる。「案外と大きいのお」とつぶやいたあと、勝頼の父信玄に対する印象が脳裏に去来する。「お前(信玄)のような仕来りと常識を墨守するやり様では、いずれは時代の変化に立ち後れてしまう」と毒づく。そして勝頼の首を「使い物にならぬな、こんなのは」と言って櫃を足蹴にする。
いっぽう光秀は「戦い敗れたとはいえ勝頼公は清和源氏の血を引く武田家の当主、甲信駿三国の太守であられたお方だ」と畏敬の念すら覚える。その首が入っている櫃を信長は足蹴にしたのだから、驚くのも無理はない。
武田征討が終わった後、兵粮米の半分を足軽など下級兵士や荷駄者にも分けてやれという信長に対し、その後の戦の兵站を心配する光秀は唖然とする。また、光秀がうっかり「拙者も年来、骨を折った甲斐がござった」と漏らせば、それを聞いた信長はみるみる激昂し、「不埒者は成敗してくれるわ、このキンカ頭」とののしりながら光秀を殴る。信長の内心には、「兵と銭を与えられて戦をするぐらいは骨折りではない。本当の骨折りとは、新しい方法を考え、新しい仕組みを作り、他人に憎まれ蔑まれながらも銭を集め兵を増やすことだ」という思いがある。
信玄は、生涯自分の城を持たなかったことで知られている。「人は石垣、人は城」、すぐれた家臣団がいるから城を築く必要はないと躑躅ヶ崎の館に住んでいた。その屋形跡を見た信長は、「やっぱりつまらんもんじゃのお」と歯牙にもかけない。華麗な安土城を築いた信長の価値観と信玄のそれは正反対ともいえる。
いっぽう光秀は、「信玄公は一代で実入りを十倍にしたと聞くが、お暮らしは変わらなかった。奇をてらわず贅を誇らぬ信玄公の躑躅ヶ崎の館は偉大な志の結晶だ」と見る。
ことごとく信長と光秀は考え方を異にする。
では、なぜ光秀が信長を討つことになったのか。いくつかの伏線が暗示される。四国攻めからはずされたこと、安土城で家康を饗応する役目を途中で解かれたこと、西近江から山陰の2カ国に領地替えさせられたこと(しかもそのときはまだ毛利領だった)など、いくつもの〝ヒント〟が提示される。長年仕えてきた佐久間親子が追放されたことも要因のひとつだろう。
光秀の才能を評価していた信長だが、「光秀はただの人じゃ、所詮、ただの人じゃ」とつぶやく。いっぽうの光秀は、「信長様は、過去の功績も人事の情もお感じにならないらしい。人を金銭道具と同様に、ただその日その時の役立ちだけで見られるお方なのだ」と憂える。
堺屋太一らしさは本能寺の変後、あっという間に光秀が追い詰められていく描写にある。光秀は、自分が信長を討てば、同じように信長を憎んでいる大名が味方になってくれると思っていたが、蓋を開けるとすぐに孤立した。世に言う〝三日天下〟に終わる。
「大将とは苦労の多いものよ」
光秀のつぶやきが印象的だ。
彼は信長配下だからこそ、その能力を十全に活かすことができた。大企業で仕事ができた人が、名刺がなくなったらただの人になってしまうのと同じだった。サラリーマン時代、仕事ができた人が、独立して起業するや、鳴かず飛ばずで終わってしまうケースが少なくないが、それと同じような悲哀を光秀も味わう。つまり、堺屋太一は、人にはそれぞれ能力や個性に応じた分限があると言いたかったのではないか。
いっぽうの天才的革命児、信長はなぜ信頼している部下から謀反を起こされたのか。時代を見る目はきわめてすぐれていたのに、人の心を読む目がなかったということに尽きる。硬直した古い秩序を憎み、新しい世を切り拓こうとした信長と、権威や礼節を重んじつつ出世競争に腐心する光秀では、しょせん相容れることはなかったのだろう。
著者はあとがきにこう書いている。
――織田右大将信長の死は、「新しい世」を作る流れを押し留めるものではなかった。それは、信長が拾い上げ育て上げた羽柴秀吉に引き継がれ、妥協と矮小化の道を辿りつつも前進する。惟任光秀は日本史上に例のない主観と独創の「鬼」信長から、器用で闊達で物真似上手な日本的天才秀吉に、この国を譲り渡す役割を担った「人」だったのかも知れない。
●知的好奇心の高い人のためのサイト「Chinoma」10コンテンツ配信中
本サイトの髙久の連載記事
髙久の代表的著作