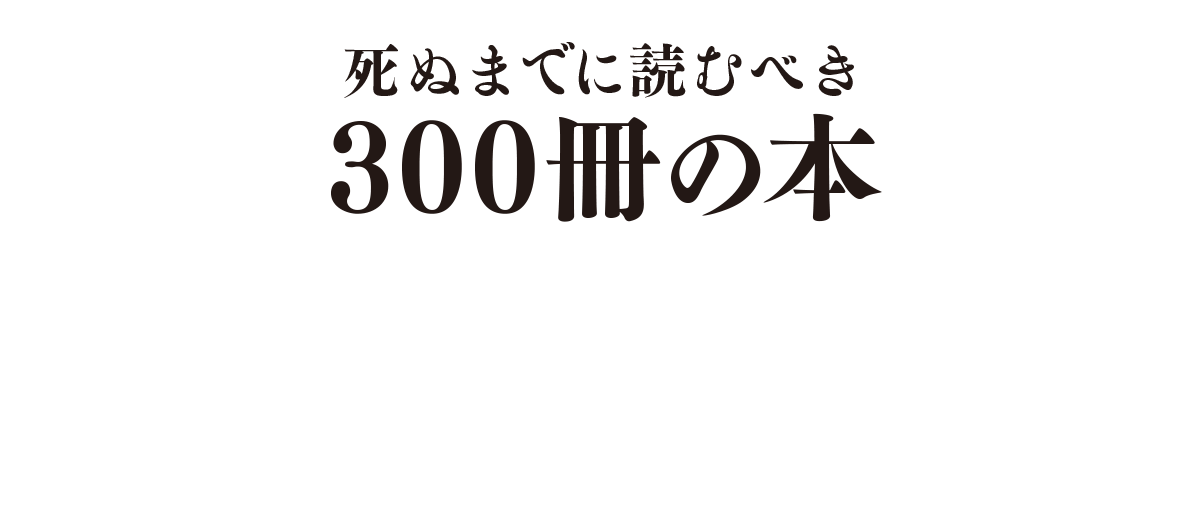若者の直感が知覚する怒り

シリトーを初めて読んだときの印象は忘れられない。「スカッとした」ひとことで言えばそういう感慨だった。
あれは高校1年のとき。集英社が刊行を始めた現代の世界文学全集の初回配本がシリトーだった。
それまで、私は世界の古典文学に首まで浸かっていた。どれを読んでもスケールが大きく、世の中にはとんでもないものがたくさんあるものだと好奇心が刺激されっぱなしだった。
古典文学は長い時間に淘汰されずに現代まで残っているという点で、まぎれもなく一流ではあるが、ある型にはめられている感は拭えない。それはそうだろう。ゆるぎない古典(クラシック)と認められるまでには膨大な時間がかかる。いま、とびぬけて人気のある作家でも、50年後、100年後は言うに及ばず、3年後でさえどういう評価になっているかわからない。それくらい時間の風化作用はおそろしいものだ。
ずっと古典ばかり、つまり評価の定まった世界選抜の文学ばかり読んでいた身にとって、シリトーはじつに鮮烈だった。うだるような暑さのなか、走ったあとに飲む、きりりと冷えたビールのようと言えば大げさだろうか。それほど衝撃的だった。初めてプレスリーやビートルズを耳にした人も、同じような衝撃を受けたのだと思う。
手にした本は化粧箱入りの瀟洒なデザインで、そのなかに収められていたのが『華麗なる門出』と今回紹介する『長距離走者の孤独』である。
アラン・シリトーは1928年、イギリスはノッティンガムの工場労働者の子として生まれた。物心ついた頃は世界恐慌の煽りを受けて極度の不景気に喘いでいた時期だった。14歳で工員として就職し、自ら生計をたてた。18歳で空軍に入隊したがマレー半島で肺結核を発症し、除隊。1年半の療養生活を強いられたが、それが幸いした。その間に〝読み・書き〟を習えたからだ。
さまざまな出自の作家がいるが、シリトーほど徹頭徹尾のアウトサイダーはいまい。いわば、ぺんぺん草の類である。
しかし、だからこそ文学部出のエリート作家には逆立ちしても書けない文体が生まれたともいえる。自分を高邁な人間だと見せようという意識などみじんもないから、驚くほど直截で、どこまでも抜ける空のような清々しさがある。小難しい言い回しに自家薬籠される、学者のような作家が惨めに思えるほどに。
本書は、映画された表題作ほか7篇の短編が収められている。とりわけ表題作の鮮やかな筆さばきは印象深い。発表されたのが1959年、私が生まれた年というのもなにかの縁を感じる。
主人公のスミスは、貧しい家庭に育った札つきのワル。強盗の罪で捕まり、感化院に送られる。
感化院には権力と偽善を象徴するような太鼓腹の院長がいるが、彼はスミスにある才能を見出す。長距離走だ。院長はスミスに厳しい練習を課し、特別に院外での練習を許す。彼がメキメキと力をつけると、院の代表としてクロスカントリー競技会に出場させる。スミスを思いやってのことではない。スミスが優れた成績をあげれば、自分の手柄となるからだ。
大会の当日、スミスは軽快に走る。タッ、タッ、タッ、ハッ、ハッ、ハッ、ペタッ、ペタッ、ペタッ……シュッ、シュッとランナーの激しい息遣いと地を蹴りつける音が聞こえてくるような描写が続く。余談だが、初めて読んだとき、原文はどうなっているのだろうと興味がわいたが、確かめる術がなかった。
2位以下を大きく引き離してゴールに向かうスミス。ふと、小鳥が自分に囁きかけたような気がした。せめてもうちょっと生き続けろよ、だけど6ヶ月のあいだは、あの草の匂いもかげなきゃ、あの埃っぽい樹皮の味も味わえないし、この美しい小径を踏むこともできないだろうって。彼はそれまでに味わったことのない感興に襲われ、走りながら泣けてしまう。
やがて視界に院長や彼の仲間たちが入ってくる。皆、腕を振り回してやんやの喝采をスミスにおくっている。
しかし、スミスは彼らの前で速力を落とし、ついに立ち止まってしまった。院長たちは大騒ぎする。早く走れ、追いつかれるぞ、と。スミスは〝阿呆みたいに〟動かない。やがて、後続の選手たちにどんどん抜かれてしまう。優勝を果たせば自分の評価が上がることはわかっているが、それ以上に院長の偽善がまかり通ることになるのが気に食わない。
この作品はスミスの一人称で描かれているため、文章はきわめて粗雑で品がなく、書き散らしたような印象を与える。しかし、それでもなおピュアな空気を醸しているのはどういうわけか。
常識という名の、既成の価値観に対する反抗心が虚飾なく描かれているからだろう。悪いことと知りながら賄賂をもらってしまうのとは対極の、いわゆる愚直な〝おバカさん〟のふるまいだ。
わけもなく反抗したい。なんだかよくわからないけど、大人がつくっている社会はうさん臭い。そういう直感が働くからこそ、若者は社会に対して心底から怒ることができる。進化の過程でそういった感情が失われていないのは、それが人間にとって必要だからではないか。
なんともモヤモヤとした、間尺に合わない感懐を思い起こし、いたく共感したことを昨日のことのように思い出す。
本サイトの髙久の連載記事
◆「多樂スパイス」
◆ネコが若い女性に禅を指南 「うーにゃん先生の心のマッサージ」
◆「偉大な日本人列伝」
髙久の近作
●『葉っぱは見えるが根っこは見えない』
●『FINDING VENUS ガラスで表現する命の根源と女性性』
お薦めの記事
●「美し人」最新記事 画家・岩井綾女さん
●「美しい日本のことば」