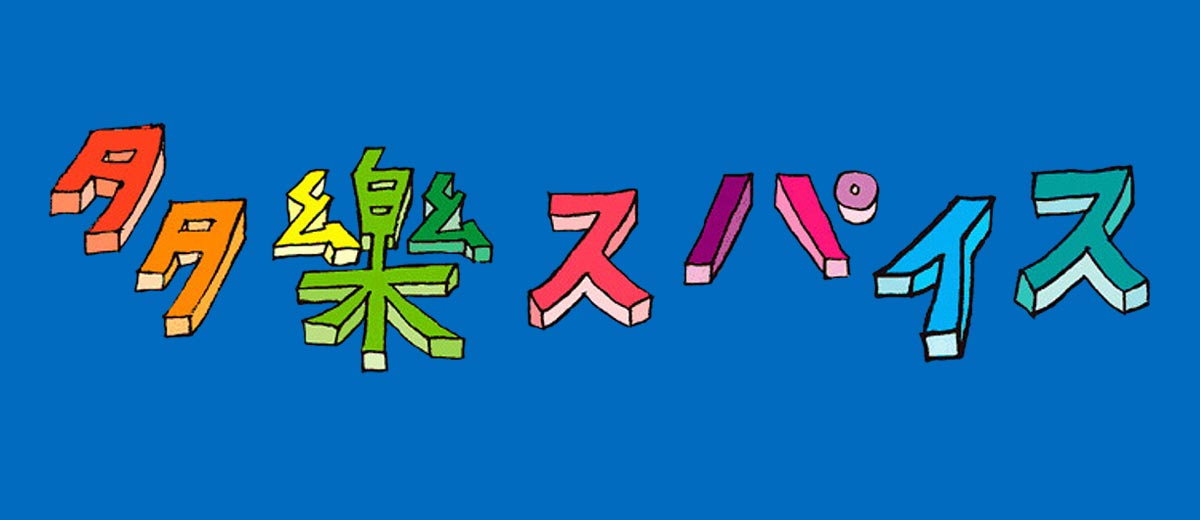古いものは人を呼ぶ
 片道3時間弱かけて、南会津にある〈シェやまのべ〉というフレンチレストランへお昼を食べに行った帰り道、大内宿に寄った。
片道3時間弱かけて、南会津にある〈シェやまのべ〉というフレンチレストランへお昼を食べに行った帰り道、大内宿に寄った。
以前から名前は知っていたが、訪れたのは初めてだ。ご存知の方も多いだろうが、日光今市から会津若松へ抜ける会津西街道沿いにある宿場で、江戸時代の風情が残っているところである。
正直、驚いたなあ。もっとひっそりしているかと思ったら、駐車場には大型バスが何台も並び、大勢の観光客でにぎわっている(バスの正面に掲げられている札を見ると、ミステリーツアーの類が多かった)。大半がお年をめした方ばかりだが、中には若いカップルが指を絡ませ顔を上気させ呼吸を荒げ、じっとり汗ばみながら土産物に見入っていたりしている。
山間にある江戸時代の宿場というだけで、これだけの人が集まってしまうものなのか。しかもその日は平日である。最近、復元がなったと言われる宇都宮城なんかよりずっと多くの人が訪れている。
そこで私ははたと膝を打ったのだった。古いものをきちんと残しておけば、人はそれに価値を見いだすのだ。世の中がどんなにめまぐるしく変わろうとも、どんなに最新技術の携帯電話が発表されようと、変わらないものは変わらない。それをきちんと残すことによって、普遍性のある価値を提供し続けられるのである。
東京ミッドタウンに移設されたサントリー美術館で催されていた『BIONBO/屏風 日本の美』展も多くの人で賑わっていたが、それと同じようなことだろう。平安時代や桃山時代に描かれた屏風を見るために、多くの人たちが訪れ、人混みの肩越しに作品を少しだけ見て満足できるのである。
古いものをきちんと残せるって、素敵な文化だなあ、とあらためて感心した次第である。
(071014 第16回 写真は大内宿)