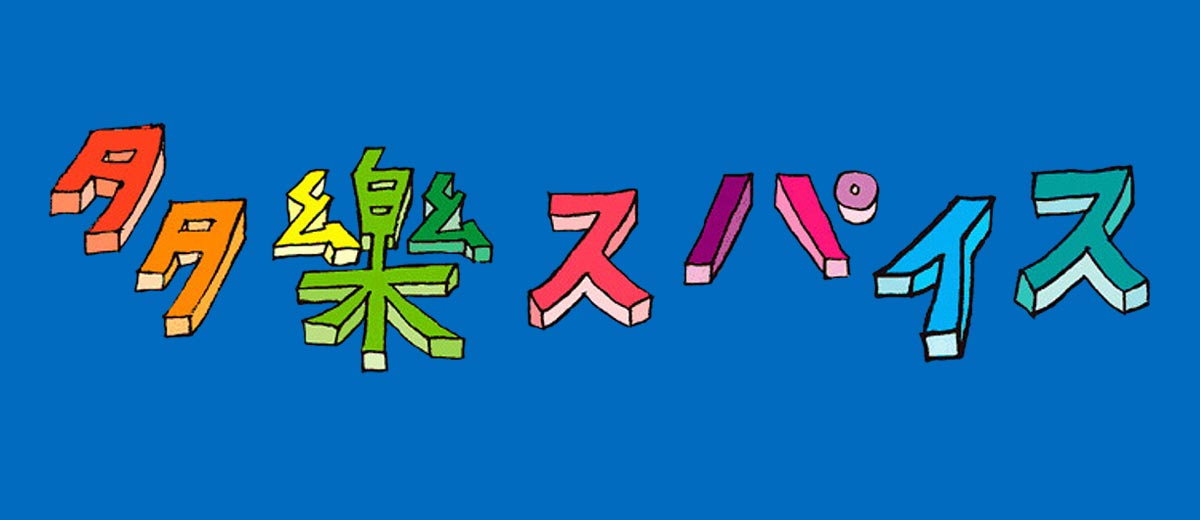女の闘い
 ロワール川といえばフランス最長の川で、全長約1020km。その河岸には数百の城が点在しているが、宮廷がパリに移るまでの160年間はフランス文化と政治の中心地であった。それだけにさまざまな物語が残されている。
ロワール川といえばフランス最長の川で、全長約1020km。その河岸には数百の城が点在しているが、宮廷がパリに移るまでの160年間はフランス文化と政治の中心地であった。それだけにさまざまな物語が残されている。
一度、バスでシュノンソー城に行ったことがある。アンリ2世の正妻カトリーヌ・ド・メディシスと愛人ディアンヌ・ド・ポワティエのどろどろの確執があった城でも有名だ。ガイドが英語でそれについて詳しく語っていたが、詳細は理解できずとも、わかったことは、「女はコワイ」(も、もちろん、コワクナイ女性もいるので、ご、誤解しないでほしいのだが…)。なにしろ、嫉妬を原動力にした女同士の闘いは、男のイマジネーションをはるかに超えて残忍だ。
おー、こわ!
日本の城の主人公は豊臣家滅亡前の大坂城など、ごくごく例外を除き、大半が男だったが、フランスはやはりお国柄といおうか、女性が主役になっていることが多い。このシュノンソー城も代々女性が城主だったことから「6人の奥方の城」とも呼ばれている。
壕も石垣もないので、ほんとうにこれが戦うための城だったのかと思えてしまう。あるいは、最初から女の闘いを想定して造っているのだろうか。
女性の城主ということもあって、その外見も内装も優美だが、だからといってため息が出るほど美しいとは思わなかった。姫路城と比べたら、全体のプロポーションや細部の造りなど、比べものにならない。しかも、橋下治の『ひらがな日本美術史』によれば、姫路城は戦うことを主眼として造られており、実用性の方が装飾性よりも勝っているという。その見方はちょっと意外だった。関ヶ原以降、池田輝政によって建てられたこの城は、戦闘を想定していない、造形美を求めた城造りだったと思い込んでいたのだが、さにあらず。例えば、外壁の白は類焼を防ぐための塗料がその色だったので、やむなくその色になったという。たしかに当時の城の基本色は黒だった。当時、白を使うのはかなり野暮ったいと見られていたようだ。それなのに、現代人が見ると、ため息が50回くらい出てしまうほど美しい。
日本人の感性は、深くて優美だ。
(111207 第301回 写真はバラ園から見たシュノンソー城)