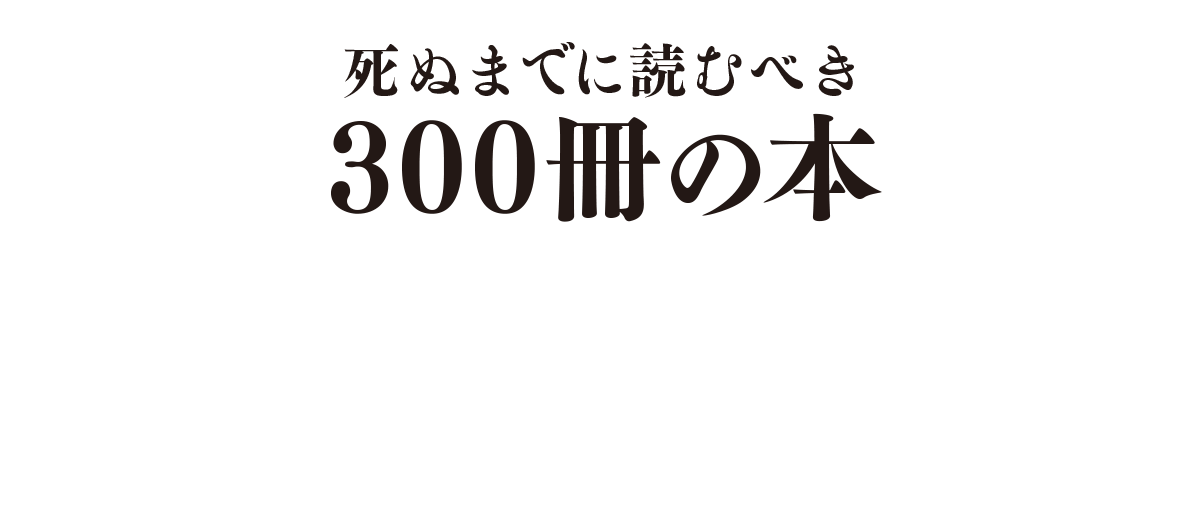でっかい歌人、西行の生涯を映す万華鏡

鳥羽院の北面の武士だった佐藤義清(のりきよ)が歌の道に生きると決意して出家し、西行と名を改め、2300首もの歌を作りながら濃密な73年の生涯を閉じるまでを、弟子の藤原秋実が聞き語りの形式でまとめるという構成がいい。
秋実は実在の人物かどうかわからないが、評伝の書き手というポジションを与えられている。西行ゆかりの人たちから話を聞いたり、あるいは西行からじかに聞いたことなどを織り交ぜながら、多面的で重層的な西行像に迫っていく。辻邦生はこの作品の構想に10年の歳月を要したというが、秋実が師の人物像を明らかにしていく過程を読者が共有するという仕掛けはみごとと言う以外ない。
本書の付録に、辻邦生は「西行の内面の成熟と、摂関政治から武家支配に変わってゆく時代の崩壊過程とを、焦点の深いレンズで一挙に撮影するのに似た手法で書きたいと思い、一章ごとに語り手を変え、内側と外側を合わせ鏡のように書いた」と明かしている。
なんといっても最大の魅力は、主人公・西行がじつにスケールの大きな人物として描かれていることだ。世の中が嫌で隠遁し、社会に背を向けて生きたのではなく、むしろ人間の愚かな行為も含め、山川草木、森羅万象がいとおしく、世の中に積極的に関わっていくという意思をもっていたがゆえの出家だった。
歌の師匠である藤原為忠から、こう言われたことが西行に重くのしかかる。
「義清、言葉で作る歌は綺麗かもしれない。だが、綺麗な歌を作る人が、そうした現実を生きていないのでは意味がない。大事なのは、その綺麗さを生きることだ。それを生きて、その結果、綺麗さが溢れて滴り落ち、それが歌になったのなら、その綺麗さは真に生命を持ったものと言える」
そして西行は北面の武士という恵まれた仕事を辞め、出家する。真の意味の出家とは、我という家を出、我執という家居を脱却し、物の好さのなかに住むことだ、と。
西行はそういう境地を目指して出家するが、それは同時にニュートラルな立ち位置を得るということでもある。そして、北面の武士に引き立ててくれた鳥羽院とその女院(待賢門院璋子)、皇子・新院(崇徳院)ら天皇家の面々、歌を通じて強い絆を築いた藤原俊成、北面の武士時代の同僚・平清盛や藤原秀衡、源頼朝ら武家……。当時のオールスターとも言える人物たちと深く交わり、森羅万象を愛で、その果実として数々の歌を生み出した。
時代が下り、松尾芭蕉は西行に憧れて歌枕を詠んだが、平和な時代ということもあり、芭蕉のまわりの人物はいかにも小粒、人間関係の多彩さにおいて西行とは比べるべくもない(そのかわり、市井の人々の感懐を汲むうえではプラスに作用したとは思うが)。
西行が一気に内面の充実を見せるのは、1回目の陸奥への旅を終えてからだ。西行の目に映ることごとくが愛おしく思えるようになったのだ。彼は弟子の秋実にこう語る。
「この世の好さはすぐ過ぎてゆく。花も散る。月も欠ける。そのときの花の好さ、月の良さも、もちろん消えてゆく。それは花や月のうえに懸った虹のようなものなのだ。これを歌のなかに移せば、歌は花の好さ、月の好さとなって、そこに現前する。この世の花、この世の月は消えても、歌のなかに花の好さ、月の好さは留まる」
この世のすべては無常。しかし、それを歌に封じ込めれば、その好さは永遠に消えることはない。その歌が後の世の人たちに親しまれている限り。
現世の煩悩を捨てたはずの西行だが、命がけで作った歌の数々の行く末に執着を残しているところは人間味を感じさせる。西行は勅撰集に自作が選ばれることを強く願っていた。『詞歌集』では詠み人知らずという表記で1首だけ選ばれたにすぎないが、『千載集』では18首も選ばれ、子供のように喜ぶシーンがある(本書には描かれていないが、その後、『新古今和歌集』では入撰数トップの94首が選ばれている)。
また、仏師が仏像を彫ると寺院に献じ、本堂に安置してもらうのと同じように、歌人は歌を作り、それを寺社に献し、神々の法楽に資してよいのではないかと考え、歌合をつくることを着想する。そして、36番の歌合を2組選び、それぞれに藤原俊成とその子・藤原定家に判者となってもらう。定家からの判詞がなかなか届かず、やきもきするところは、愚直な人間味を感じさせる。
皇位継承問題によって、保元の乱に巻き込まれていく崇徳院の悲運は、圧巻。人の噂に触発されて大きくなっていく疑心暗鬼。崇徳院の行く末を案じる西行は、崇徳院と後白河帝の間をとりもとうと奔走するが、大きな波を変えることはできなかった。あたかも、このままでは米英と戦端を開くことになるとわかっていながらだれも止められなかった先の大戦と符合する。
待賢門院璋子との切ない恋、やがて慈円と名乗ることになる歌詠みとの問答など、読みどころは満載。もちろん、西行が全身全霊をかけて詠んだ歌の数々も、その背景とともに味わうことができる。
残りの命がわずかだと悟った西行は、秋実にこう語る。
「人の仕事とは、一生かかって円を描いているようなものではないか。円が完結しないあいだは、せっせと仕事をする。だが、誰にも、仕事が終わり、円が閉じたと思うときがくる。そのとき人は息をつき、重荷を運びきったような思いを味わう」
明らかに言えることは、本書を読んだことで、世の中の見方が変わったということ。これまで漠然と思っていたことが、「その通り!」と輪郭を露わにしてきた。そういう本との出会いは奇跡といえるかもしれない。
●知的好奇心の高い人のためのサイト「Chinoma」10コンテンツ配信中
本サイトの髙久の連載記事
髙久の代表的著作