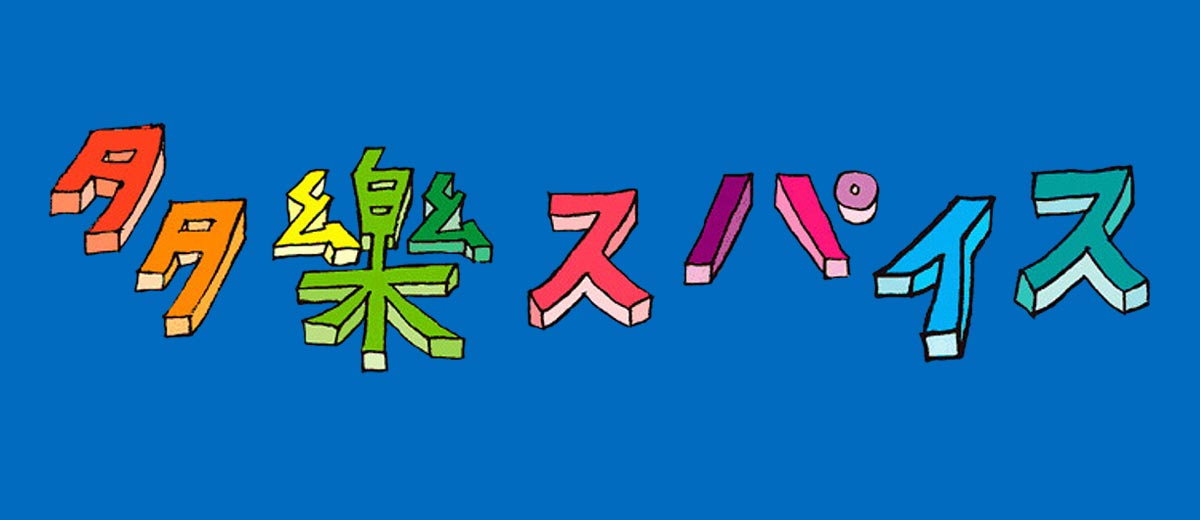血流が逆噴射してドーパミンドバドバ
 数ヶ月前、ある用事で一人の高齢男性がわが家を訪れた。その人はリビングに入るなりレコードプレーヤーに目を留め、「レコードを聴かれるのですね」と言った。私が「ええ。音楽はお好きですか」と返すと、クラシックが好きと答えた。そして、「でも最近はCDを聴こうと思ってセットしても、プレイボタンを押さないことが多いですね。隅々まで知っていますから、聴いても仕方ないかと思ってしまって」と続けた。
数ヶ月前、ある用事で一人の高齢男性がわが家を訪れた。その人はリビングに入るなりレコードプレーヤーに目を留め、「レコードを聴かれるのですね」と言った。私が「ええ。音楽はお好きですか」と返すと、クラシックが好きと答えた。そして、「でも最近はCDを聴こうと思ってセットしても、プレイボタンを押さないことが多いですね。隅々まで知っていますから、聴いても仕方ないかと思ってしまって」と続けた。
私は失礼を承知で、「それは老化現象のひとつですね。新しい音楽も聴かれるといいですよ。すると別の角度から慣れ親しんだ音楽を聴くことができ、新たな発見がありますから」と言った。
この半年間、私はグレイシー・エイブラムという26歳の新しい才能を聴き続けているが、たしかにそれが余波となって、ずっと親しんできた音楽の別の面を教えてくれることがある。
以上のこととは関係ないが、久しぶりに血が逆流するような感動と興奮を覚える映画を観た。
『レッド・ツェッペリン・ビカミング』というドキュメンタリー映画(becomingとは起源の意)。クイーンの『ボヘミアン・ラプソディー』以来、往年のロック・アーティストを題材にした映画が創られている。エリック・クラプトン、デヴィッド・ボウイー、ボブ・ディラン、トーキング・ヘッズ……。彼らにはいまだ熱狂的なファンがいるから、一定の観客を見込むことができる。
『レッド・ツェッペリン・ビカミング』は、構成そのものに新味はない。現在のジミー・ページ、ロバート・プラント、ジョン・ポール・ジョーンズのインタビューと初期のライブ映像などを組み合わせたもの。ときどき亡きジョン・ボーナムの音声も混じる。
なんといっても素晴らしかったのは、圧倒的なサウンドである。リアルタイムで聴いていた頃から、レッド・ツェッペリンは他のバンドと一線を画していると思っていたが、その理由は単純明快だった。音楽のスタイルが唯一無二なのだ。それを可能にしたのが、ギター・ドラム・ベースの卓越した演奏力・表現力とロバート・プラントの歌唱力。加えて、ジミー・ペイジによる緻密なプロデュース力によるものだということがわかった。
彼らは川が自然に合流するように集まり、バンドを結成した。当時も今も、無名のバンドが世の脚光を浴びるようになるまでの常道はある。しかし、彼らはその道を行かなかった。自分たちで質の高いデモテープをつくり、直接、レコード会社に掛け合った。それがアトランティック・レーベルである。もともとR&Bが好きで、そのレーベルからデビューしたいと思っていたそうだが、そのときレコード会社に突きつけた条件がイカしている。
「シングル盤を出さないこと」
これは常識外れだ。ふつう、名前を〝売る〟ためには、ヒットチャートの上位にランクされるのが常道である。しかもこの当時、彼らは貧しかった。映画のなかでプラントが「あの頃はお金がなくて、移動中ガス欠になってしまい、よその車からガソリンを盗んで御用になった」と語っているように、本来であればなるべく早く名前を売って金を得たいはず。しかし、彼らはシングルを発売することを拒絶した。レッド・ツェッペリンの曲は、ほとんどが親しみやすいとは言えないが、少しでもヒットしそうな曲はレコード会社に勝手にシングル・カットされないよう、途中に実験的な音を入れるなど、徹底してシングル化を忌避した。しかも、アルバムジャケットに自分たちの写真を載せることもしなかった。ビジュアル面で魅力的であったにもかかわらず。そういう、目先の損得を超えたフィロソフィーを持っている人に、私は弱い。
彼らの偉大なキャリアのなかで、ヒット曲はない。すべてアルバム単位で勝負し、大成功を収めた。(参考記事「ロックが到達した頂点のひとつ」)
ところで、彼らの音楽が唯一無二になったのは、どのような理由からか。
リズムのノリや縦揺れのグルーヴ感では黒人に敵わないと考えたことだろう。彼らは他のバンドとまったく異なるアプローチをした。それは、音の塊で構築するということ。あたかも巨大な建造物を創るかのように音のブロックを組み立てた。ブロックとブロックの隙間はおのずと間(ブレーク)となり、そこにギターやドラムやベースがタイミングをずらして流入し、炸裂する。そのサウンドの凄まじさは異様でさえある。
とりわけジョン・ボーナムのドラミングが凄い! 1980年に彼が亡くなったとき、後釜としてコージー・パウエルやサイモン・カークらの名前があがったが、私はボンゾ(ジョン・ボーナム)の代わりを務められるドラマーは、世界中を探してもいないと確信していた。そして実際、レッド・ツェッペリンは解散する。
私はいまでも世界最高のドラマーはジョン・ボーナムだと思っている。数字では割り切れない独特のリズムを自在に操り、圧倒的なパワーでツェッペリンの屋台骨を支えていた。
映画を観て興奮冷めやらぬ私は、CDショップへ足を運び、まだ持っていない何枚かのCDを購入し(レコードではすべて持っているが)、大音量で聴きまくっている。
この映画を観たことによって、彼らのフィロソフィーと独特のサウンドの魅力を知ることができた。血湧き肉躍る映画体験であった。
(251005 第1291回)
髙久多樂の新刊『紺碧の将』発売中
https://www.compass-point.jp/book/konpeki.html
本サイトの髙久の連載記事