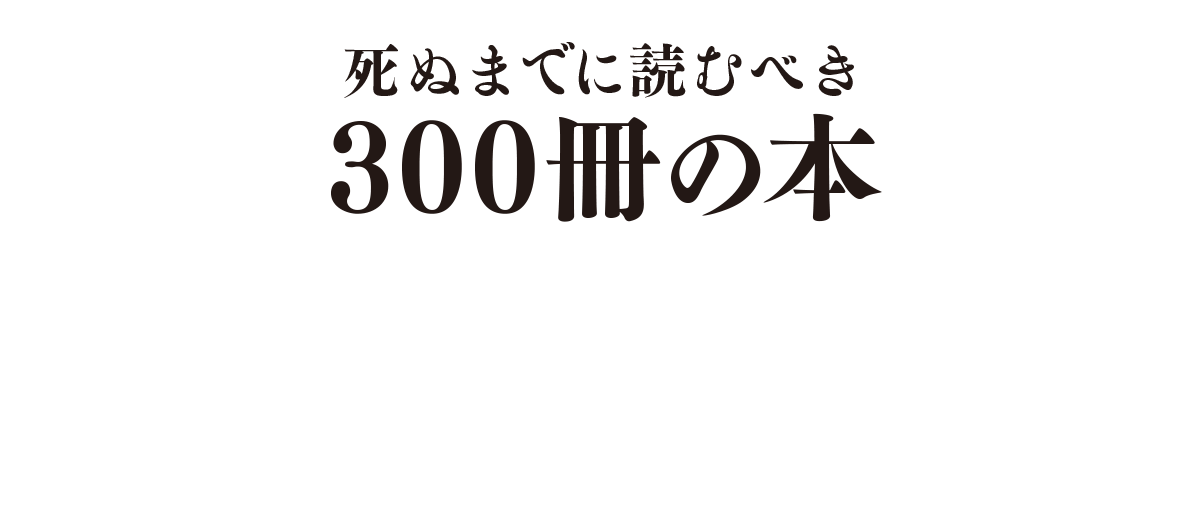組紐のように綾なす人間模様

私は現代日本文学の最高峰は乙川優三郎と位置づけている。その乙川氏が作家になろうと決意したとき、文章の手本としたのが芝木好子であった。そのことは読売新聞のコラム「私をつくった書物たち」に書かれていたし、彼の小説『ロゴスの市』でも『隅田川暮色』がいかに素晴らしい作品かについて詳しく描かれている。いわば芝木好子は乙川優三郎の原型である。本作を一読すれば、それが料簡できるはず。
作者の芝木好子は浅草で呉服商を営む家の出であり、戦前の浅草や隅田川付近の風景、終戦間際の東京大空襲、組紐という伝統技芸の難しさと奥の深さ、そしてそこに生きる人々を細やかに活写した。
本書の主人公の冴子もまた浅草の呉服問屋の娘である。最後まで自分を気にかけてくれていた父・千明を空襲で失ったことから、故郷の浅草にはなかなか足を向けられず、妻子持ちの大学助教授・悠とひっそり暮らしている。悠は妻に離婚を申し出ているが、承諾してもらえない。
冴子は、湯島にある悠の実家「香月」で組紐の作業を手伝っている。中途半端な立場の彼女は、自分の居場所に苦慮するが、幸い、組紐に魅了され、没頭することでめきめきと腕をあげていく。
そんなおり、「香月」の主人・真造のもとに、『平家納経』に使われていた厳島組紐の復元の依頼がくる。先人が遺した組紐は、やすやすと再現できるほど簡単なものではない。冴子の感性を評価していた真造は、その難解なプロジェクトのメンバーに冴子も加える。
乙川文学もそうだが、日本の伝統技芸の奥深さが、見事に表現されている。紅、朱、濃紫、薄藤、瑠璃色、萌黄など、はるか昔から伝わる日本独特の色に染められた絹糸が何本も組み合わされ、一本の組紐に仕上っていくさまは息を呑むほど。その過程は、あたかも個性の異なる人間が、複雑な人間模様を編んでいるかのようでもある。
登場人物も造形が深い。冴子の幼なじみの藍染め職人の息子・俊男、嫌味の塊のような悠の祖母・加津(悪態がことごとく魅力的でもあるのだが)、冴子を慕う響一など、芝木好子によってつくり出された人物は誰一人、存在感の薄い人はいない。
清澄で彫りが深く、流れるようなストーリー展開も魅力。
こんな作品があまり知られていないなんて……。日本人の教養と感性の衰退を見る思いである。
髙久多樂の新刊『紺碧の将』発売中
https://www.compass-point.jp/book/konpeki.html
本サイトの髙久の連載記事