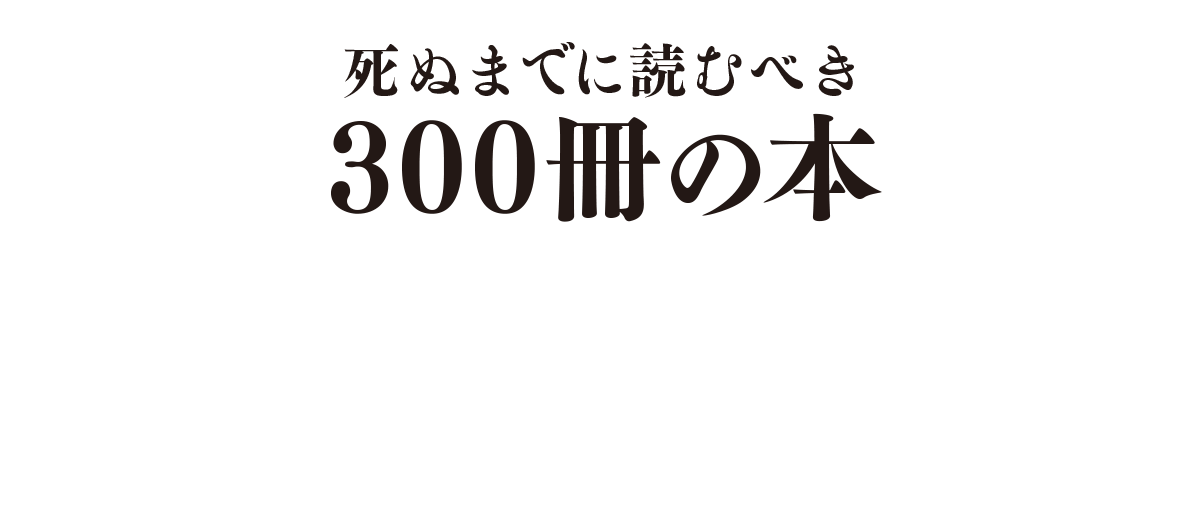「戦争が苦手な日本人」の証明
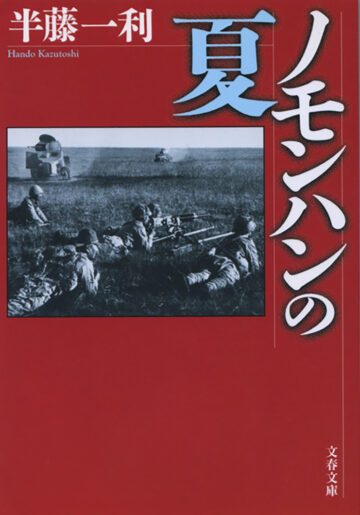
読み進めるのがつらくなる本だ。『失敗の本質』(中公文庫)もそうだが、先の大戦の敗因を分析した書物は、いかに日本人の軍部が無能かをこれでもかと思い知らされるようで、気が滅入る。日本人ほど組織的な競争、なかんずく戦争に不向きな人種はいないのではないかと思えてくる。日清・日露の両戦争でなぜ勝てたのか、不思議でならない。
日本の近代史、とくに昭和史に関して半藤一利の解釈と解説は信頼できる。歴史を語るうえで、なんらかのフィルターがかかるのはやむをえないが(人間は機械ではなく主観をもつ生き物だから)、度を過ぎれば、事実を歪曲することになる。しかし、半藤史観は右にも左にも偏らず、きわめて冷静だ。
本書のあとがきで、半藤が初めて辻政信(元陸軍大佐)に会ったときの感想をこう述べている。
――現実の世には存在することはないとずっと考えていた「絶対悪」が、背広姿でふわふわしたソファに坐っているのを眼前に見た。
半藤一利をしてそこまで言わしめる辻政信とはいったいなにものだったのか。どうして、そのような人物が作戦参謀として権力をもっていたのか。
辻は、手前勝手かつ無謀な作戦で多くの部下を死なせ、それらに対して慙愧の念を抱くどころか、戦争が終わると戦犯容疑から逃れるために逃亡生活を続け、時効になったあと、忽然と社会復帰して『潜行三千里』などという本を書いて耳目を集め、あろうことか国会議員に立候補して当選し、ふんぞり返っていた人物である。恥知らずも、ここまでいけば達人の領域だ。半藤一利ならずとも「絶対悪」と言いたくなるだろう。
本書は、そんな輩の〝生態〟に絞って読み進めても興味深い。なぜなら、それこそ〝失敗を活かす〟ことにつながるからだ。
歴史に学ばない限り、同じ誤りをおかすのは自明の理。能力がないがゆえに無責任で、ひきょうなだけの人物をリーダーに据えると、組織全体が壊滅的な打撃を受けるという教訓である。半藤も書いている。「手前本位でいい調子になっている組織がいかに壊滅していくかの、よき教本だ」と。
本書のタイトルにもなっているノモンハン事件について簡単に記す。「事件」となっているものの、まぎれもなく戦争のひとつであり、この名称ひとつとっても、完敗したことを矮小化しようという作為を感じる。
ノモンハン事件は、1939年の5月から8月にかけて満蒙国境で行われ、関東軍がソ連軍に完膚なきまでに叩かされた負け戦をいう。
8月20日から数日間にわたった最後の戦闘において、日本は一方的な敗北を喫した。この戦闘での日本側の損失は、出動人員5万8925人、戦死7720人、戦傷8664人、戦病2363人、生死不明1021人、計1万9768人となっている。第23師団に限っていえば、ノモンハン事件の全期間を通しての出動人員1万5975人に対して、戦死及び傷病者は1万2230人、損耗率はなんと76パーセントにも達した。悪名高きガダルカナの戦いでも損耗率は34%。なんと2倍以上もの尊い命が露と消えたのだ。このときの敗因を公正に分析していれば、2年後の対米英開戦はなかったのではないかと思われる。
では、なぜ精鋭と思われていたはずの関東軍が、ボロ雑巾のように踏みにじられたのか。答えは、明白だろう。いみじくも、戦後、昭和天皇が日光に疎開していた皇太子(現平成上皇)に宛て、日本の敗因は科学的裏付けもなく、やみくもに精神主義に走ったからだと喝破しているように、精神力だけを頼りに無計画で無謀な戦いを挑んだからだ。そして、この敗戦をきっかけに戦い方を変えたのであればまだしも、日本はついぞ終戦まで変えることができなかった。
当時の戦力を比較すれば、日本が勝てる可能性はなかったということが明らかだ。
例えば、
●圧倒的に物量の差があった(関東軍の11師団に対し、ソ連軍は30師団。戦車は関東軍の200両に対し、ソ連軍は2200両。航空機は関東軍の560機に対し、ソ連軍2500機)
●平坦の重要性を無視するのは、一貫して日本軍の特徴だった。関東軍は輸送手段に乏しく、歩兵は歩いて戦場まで行く始末だった。武器・弾薬も圧倒的に不足しているうえ、食料については〝現地調達〟だった
●兵器の数だけではなく、質も差があった。ソ連軍の短機関銃に対し、日本の38式歩兵銃が中心兵器だった。戦車の質も格段にちがっていた
詳細に見れば、さらに大きな戦力差があったはずだ。しかも、関東軍は、慣れない極寒の地での戦闘を強いられた。どう見ても勝てるはずはない。しかし、関東軍の作戦参謀は、精神力で勝てると思っていた。その張本人が辻政信である。陸軍参謀本部の不拡大方針を無視し、自分は安全圏にいて、都合のいい机上の空論をふりまわし、多くの日本兵を無駄死にさせた。本来であれば、八つ裂きにしても足りない。そういう人物が、戦後、大物政治家になるというブラックジョークのようなことが実際に起った。それが日本という国の実態でもある。
戦いのあと、ソ連軍の司令官のジューコフは、スターリンにこう報告したという。
「日本軍の下士官兵は頑強で勇敢であり、青年将校は狂信的な頑強さで戦うが、高級将校は無能だ」
わずか数ヶ月の戦いで、日本軍の高級将校は無能であることを見破られてしまったのだ。そして、その無能ぶりは、終戦まで続くことになる。
どうしてそこまで無能だったのか。
明治以降の点数主義偏重が大きな原因だと私は思っている。
辻は陸軍士官学校を主席で卒業している。現代でいえば、東京大学を主席で卒業するようなものだから、たしかに優秀だったのだろう。ただし、ある面においては。
それはそれで敬意に値する。しかし、それは「あらかじめ決まった答えがある設問に対し、ある一定の時間内に最も多く答えられた人」というだけの話である。戦争に、「あらかじめ決まった答え」などあるはずもない。その都度、無数の選択肢のなかからどれがいいか適宜判断しなければならない。そういうことに不慣れな学術エリートが、戦争で使い物にならないのは当然のことだ。
問題は、それを考慮せず、学校で高い点数をとった者に指揮権を与えてしまう仕組みが悪い。
明治に行われた日清・日露の両戦争と比較すれば、指揮官・上級将校の「人間力」の差そのものだったということがわかる。東郷平八郎も秋山真之も大山巌も児玉源太郎も山本権兵衛も桂太郎も学術エリートではなかった。そのかわり、どんな状況下でも最適の答えを得ようと考えられる思考力をもち、それを部下に納得させることができた。人間として信頼があったからだ。「あの人が言うのだから」という、一見根拠のないものが、大きな力を生むことがある。そういう信用を得るためには、日々の仕事において、そういうことができる人間だと納得させなければならない。そのような資質に欠けていた辻政信のような人物を抜擢した時点で、すでに日本軍の敗戦は決まったようなものだ。
さて、現代はどうなのだろうか。戦後の日本は、それらを反省材料に統治システムを変えているのであろうか。
半藤一利は、「人は過去からなにも学ばない」と語っているが、ほんとうにそうだとしたら、やりきれない。
だから思う。日本人は戦争が苦手なのだから、戦争にならないよう、最善を尽くすべきだと。もちろん、憲法9条があるから戦争にならないと考えるのは、戦前の精神主義と同根である。
●知的好奇心の高い人のためのサイト「Chinoma」10コンテンツ配信中
本サイトの髙久の連載記事
髙久の代表的著作