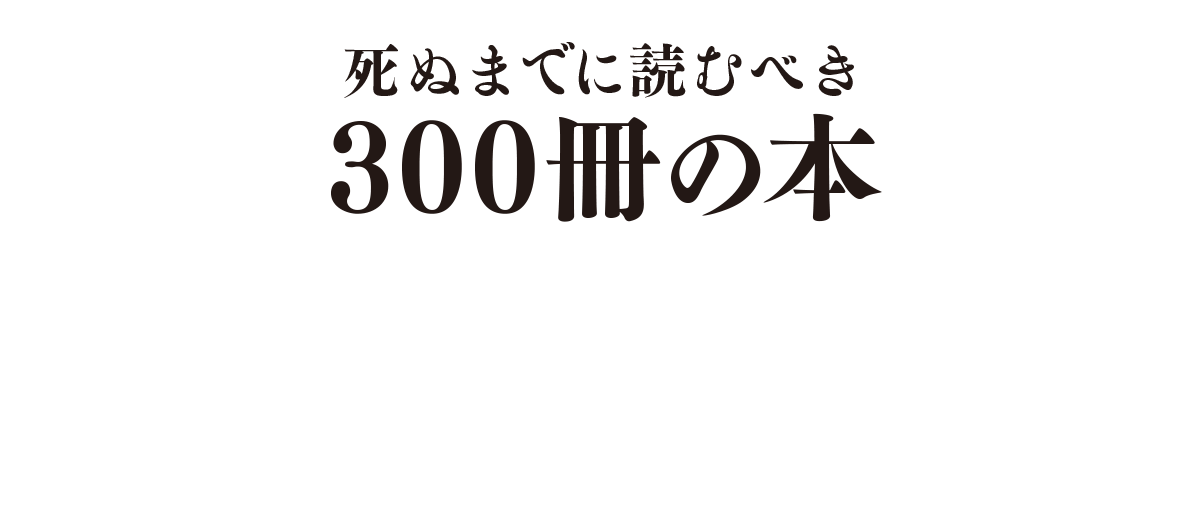右肩上がりの時代を象徴する国民的文学

「坂の上の雲」とはなんとも言い得て妙のタイトルだ。坂の上に浮かぶ雲を目指して一丸となって進んで行った時代の青春群像を描いた巨編に、これ以上ふさわしいタイトルはない。
本書は戦後の高度成長期(昭和43年から48年)にサンケイ新聞に連載されたもので、時代背景は明治の後期だが、右肩上がりという点では昭和40年代と似ている。
人口減少が加速し、すべてにおいて衰退を余儀なくされる時代において本書を読む意義とはなにかと考えざるをえない。これでもかと悲観的な情報があふれるなか、底抜けに肯定的な本書はどこかほかの惑星の話のようでもある。
しかし、うつむき加減の時代だからこそ読む価値があるともいえる。目線が上がれば、おのずと心が晴れ晴れとする。
この本に描かれるほとんどは辛酸ばかりである。10年以上にもわたって国家予算の半分以上を軍事費に割いていたのだから、国民の生活が苦しくないわけがない。戦場での肉弾戦は凄惨きわまりない。
それでも国民は不満を言わなかった。外国に侵略されることの意味を知っていたからだ。
江戸の太平の世から目覚めた新生日本だが、周りを見渡せば西洋列強の歯牙が目前にあった。一対一で向き合えば劣勢は必定だったが、幸い列強のなかにもそれぞれの利害があり、思惑がある。それらを正確に読み取り、反対にパワーバランスを利することによって相手の力を削ぐことができると当時の政治家は知っていたようだ。
当時、ロシアと結ぶかイギリスと結ぶか、政治家や外交官らは厳しい選択を強いられた。伊藤博文や井上馨はロシアと結ぶことを、桂太郎や小村寿太郎はイギリスと結ぶことを主張した。
激しい議論ののち、日本はイギリスと手を結ぶことを決断する。ロシアは国際条約を破ることをなんとも思っていない。イギリスも狡猾さではひけをとらないが、一度決まった国際条約は遵守する国柄がある。日本の首脳部は後者に賭けた。当時のイギリスは世界に冠たる海洋王国。まだ国力の弱い日本と対等の軍事同盟を結ぶことなどないと思われていたが、日本と手を結ぶことの利を説いて、日英同盟が締結された。
そして、開戦。よく知られているように、日本は陸戦で勝ち続け、ロシアが回航させてきたバルチック艦隊を対馬沖で壊滅させた。その後、ポーツマス講話条約を締結させた(ポーツマス条約締結に関する小村寿太郎の活躍は、小欄第37回『ポーツマスの旗』に詳しい)。
過酷な総力戦を描いた物語なのに、なぜこの本の読後感は爽やかなのか。
素材がいいからだろう。ここに描かれている人物の多くは高潔にしてわずかの私心もなかった。曇りのない志が言動や風貌に表れていた。古今東西、これほど傑出した人物が同時期にそろった事例はほかにないかもしれない。ギリシャの英雄たちが生きた時代でさえ、これほどではなかっただろう。それほど当時の日本には傑出した人材がそろっていた。
冒頭、愛媛県松山市ののびやかな描写から始まる。それに続いて、秋山好古、真之兄弟そして正岡子規が登場する。戦記ものの主人公のひとりに、俳人を列するというのは司馬遼太郎の豊かな情感ゆえだ。
やがて視点は山本権兵衛、小村寿太郎、児玉源太郎、東郷平八郎ら主役級の人物へと移り、さらには諜報部員・明石元二郎や講和条約の仲介役としてルーズベルトを説得する金子堅太郎らの脇役まで、さまざまな人物にスポットを当てながら日本が総力戦を貫いた様子を描く。司馬遼太郎は軍人としての乃木希典を酷評したが、水師営の会見では世界に範たる紳士的態度であったことを見事に活写した。
横須賀港に当時の日本艦隊旗艦「三笠」記念艦がある。艦内には日本海海戦の資料が陳列されており、極限状態のなかで勝利を手にした様子が手に取るようにわかる。
武器商人や狂人以外、戦争を好きな人などいまい。それでも、やむをえず戦わなければならなかったとき、どう戦うか。その成否によってそれぞれの国の現在の立ち位置が定まっているともいえる。そう思えばこそ、先人たちの努力に頭が下がる。そういう思いを呼び起こしてくれる『坂の上の雲』は、やはり一級の国民文学である。