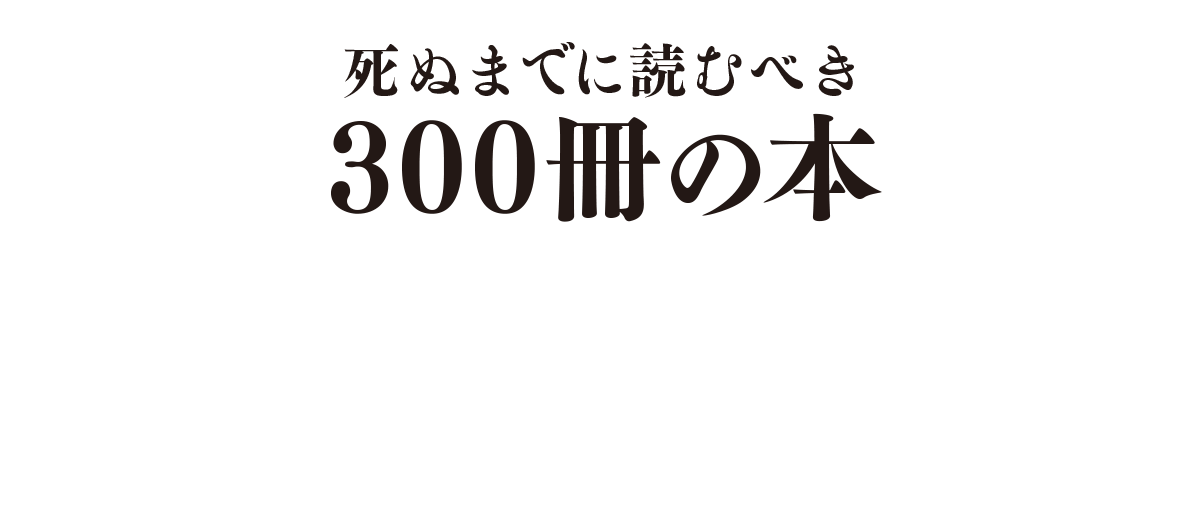人間がもつ、感化の力

山本周五郎といえば、直木賞を辞退したことで知られる。理由がふるっている。「もっと新しい作家や作品に賞が与えられるべきだ」。新人作家のために道を譲ったのだ。また「作品を完璧な形で仕上げたい」とも言った。完璧な小説など、よもやこの世にあるはずもないが、山本周五郎はそれを目指していたのだろう。実直な人である。
本書が刊行されたのは、1959年(昭和34年)で筆者の生年と同じ。なんらかの縁を覚える。
とはいえ、本書を読んだのは、黒澤明監督による『赤ひげ』を何度も観た後のこと。いきおい、映画のストーリーと原作はどう違うか、という見方にもなる。極度の貧困ゆえ服毒自殺を図った一家の少年の顛末など、いくつかの重要なエピソードは改変されているが、作品の根底に流れるエッセンスは、黒澤監督によって巧みに引き出されていた。
それは貧困であり、その遠因にあるのが無知だということ。これはそのまま現代にも当てはまる。学力格差は社会人になってからの収入格差へとつながり、この悪循環から脱するのは容易ではない。私学の無償化などが進み、今後、日本もさらなる教育格差が広がるにちがいない。アメリカの後追いをするかのように。つまり、意識の高い家庭の子供は私学へ進学し、そうでない子供は公立へ行く。そして公立校は劣化のイットをたどる。
話を本題に戻そう。『赤ひげ診療譚』は、江戸時代、小石川養生所を舞台に、正義感溢れ、頑固一徹な医師・新出去定を中心に、いくつかのエピソードが綴られる。新出去定のモデルとなったのは実在した町医者・小川笙船である。
本作を読むと、つくづく人間の本質は変わらないと痛感する。科学技術は著しく発達しているが、人間そのものは進歩していない。それどころか、ある面では退化していると言わざるを得ない。
解決策はおおむねわかっている。すべての子供に教育を施し、それぞれの人の個性が活かせるよう、緻密な社会制度設計をすること。政治の要諦はその一点にあると言って過言ではない。
境遇に不満をもち、反抗的な態度をとる若い医師・保本登がやがて改心し、〝本物〟の医者になろうと決意するラストはかなり戯画的だが、重要なヒントを含んでいる。つまり、感化である。感化とは、誰かに感じて自分が化けていくということ。それを教育と言い換えてもいい。
赤ひげ先生は、自分の言動を通して若い医者の卵を感化させたのである。
髙久多樂の新刊『紺碧の将』発売中
https://www.compass-point.jp/book/konpeki.html
本サイトの髙久の連載記事