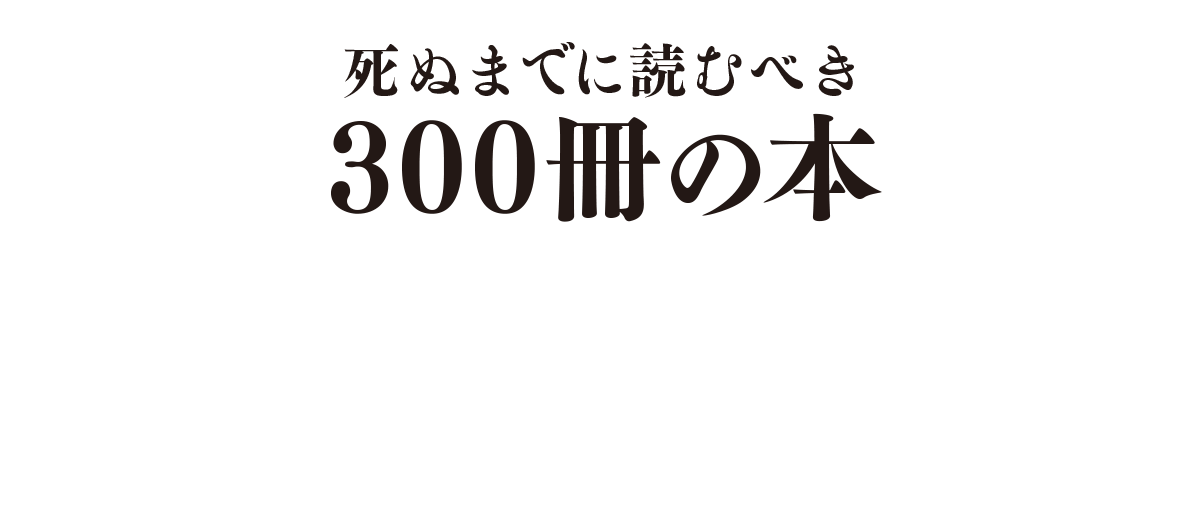人間の心はわからないことだらけ

フランスのノーベル文学賞受賞者アンドレ・ジッドは1869年に生まれ、1951年まで生きた人だから、「古典作家」の範疇には入らない。しかし、ジッドに付随するイメージは、長い時間にも摩耗しなかった大作家そのもの。とても20世紀なかばまで生きた人とは思えない。なぜ、彼は文学者の巨匠と見られているのか。
文学者として王道を歩んだからではないか。なにしろ、彼が扱うテーマは、古今東西あらゆる人間が無縁ではいられなかった「愛」である。それにキリスト教の信仰心が絡んでいる。私のように、キリスト教にまったく馴染みのない人間はともかく、特にヨーロッパ人にとってきわめて重要な、愛と信仰心という2大テーマを真正面から扱い、それなりの成果をおさめた作家はそう多くはない。
加えて、ジッドの作品は超一流の技術に支えられている。かつて、石川淳が『狭き門』を「ここには鑿(のみ)の冴えがある」と評したが、彼の作品には腕っこきの大工が丹念に形を整えていくような風格がある。
私がジッドを読んだのは中学時代。学校の図書室にあったダイジェスト版だった。その後、20代になって文庫で完全版を読み、30年の歳月が流れたのち再読した。
物語の筋はほとんど忘れていたが、〝感触〟だけは覚えていた。登場人物の心理も言動も理解できなかった。バルザックの登場人物はあるていど理解できたのに……。つまり、私は潔癖すぎる善人の心がわからなかったのだ。今でもわからない。
そういう傾向は、フランス映画にも通ずるものがある。なぜこの人はこういう行動をとるのか、なぜ死ななければいけないのか、と。同じ人間であるはずなのに、人によって(生まれた時代や民族性、社会的環境などの違いがあるにせよ)行動規範はこうまで異なるということを学んだ。
そう、この小説によって得たことは「学び」である。けっして楽しみながら読んだとは思えないが、人間の不条理を眼前に突きつけられた思いがした。多感な頃、そして長い年月を隔ててそういう物語に接することができたことは、人間を見る目を養ううえで良かったと思う。
物語の語り手であり主人公でもあるジェロームは、2歳年上の従姉であるアリサに恋心を抱く。アリサもまたジェロームを愛しているが、彼女の妹のジュリエットもまたジェロームに好意を抱いていた。しかし、神の国に憧れを持つアリサは、妹への遠慮もあり結婚をためらい続ける。姉の思いを知ったジュリエットが身を引いてもなお、彼女の態度は変わらない。
煩悶の末、アリサはジェロームとの結婚をあきらめ、ついに命を落とす。残されたジェロームは、アリサが遺した日記に綴られた自分への熱い思いを胸に、「すべてを忘れてしまうまで」一人生きていくことを決めるというのが話の大筋だ。
それにしても「わからない」。この作品において、信仰心の厚いアリサの自己犠牲の精神は美しいとされる。しかし、「死んでしまってはおしまいよ」。なぜに、ここで死ぬ必要があるのだ。相思相愛で、結婚の障壁がないのであれば、なにも逡巡する必要はない。それが〝ふつうの〟考え方だ。結婚することが信仰心と両立しないという設定も理解できない。キリスト教とはそれほど非寛容な宗教なのか。現実には、キリスト教徒の大半はふつうに結婚しているではないか。
読み手(=自分)がキリスト教に不案内だからだろうか。
しかし、では小説としてつまらないかといえば、まったくそうではなく、(ここにも紹介しているくらいだから)むしろ優れた文学の香りを十全に楽しんだ。
人間の心にはわからないことがある、いや、わからないことだらけだ。なんでもかんでもすぐに答えを得られる現代にこそ読まれるべき作品である。
最新の書籍(電子書籍)
●『焚き火と夕焼け エアロコンセプト 菅野敬一、かく語りき』
本サイトの髙久の連載記事