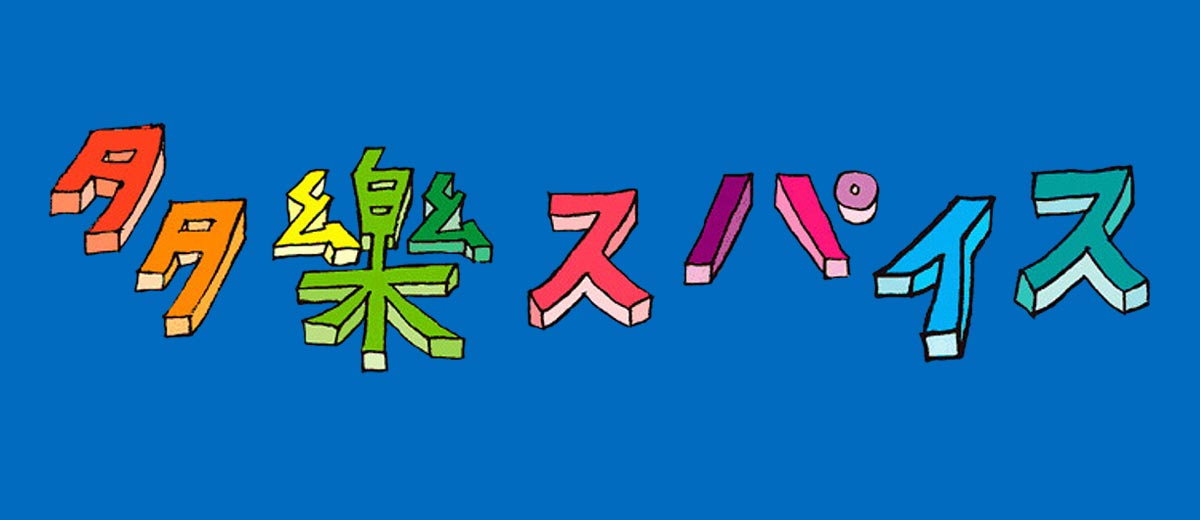植物に学ぶか否か
2011.11.16
 秋は夕暮れ、と清少納言は書いた。「つるべおとし」のように早変わりする景色の変化を、清少納言はじつに的確に、そして、あでやかに表現した。たしかに、みるみる日が沈んでいくときに見せてくれる自然のショーは、人間がつくった映像では太刀打ちできないほど劇的だ。山や木、あるいは建物のシルエットが近づいたり遠のいたり、朧になったり明瞭になったり……。
秋は夕暮れ、と清少納言は書いた。「つるべおとし」のように早変わりする景色の変化を、清少納言はじつに的確に、そして、あでやかに表現した。たしかに、みるみる日が沈んでいくときに見せてくれる自然のショーは、人間がつくった映像では太刀打ちできないほど劇的だ。山や木、あるいは建物のシルエットが近づいたり遠のいたり、朧になったり明瞭になったり……。
また、日に日に色が変わっていく葉は、色彩の魔術師といってもいいだろう。秋になって葉が紅葉するのは、寒さに備えて木が自らを守るため、枝と葉の接着点を遮断することによって光合成を抑えるためにおこるという。その結果、葉緑体がなくなり、葉から緑色が抜けていく。黄色になったりオレンジ色になったり紫色になったりと、色が多彩なのは、もともとその葉がもっている色素によって異なってくるからだという。
そのことだけをとっても、植物の知恵には驚かされる。物言わず、あらゆる活動が超スローなのでわれわれ人間は見落としがちだが、植物の生きる知恵に学ばない手はない。
いま、あらゆる局面で格差が拡大している。その原因は無数にあるが、「植物に学んでいるか、いないか」によっても格差が生じていると思う。どういう格差かといえば、心のあり方における格差である。
(111116 第296回 写真は鹿沼市にある古嶺園の紅葉)