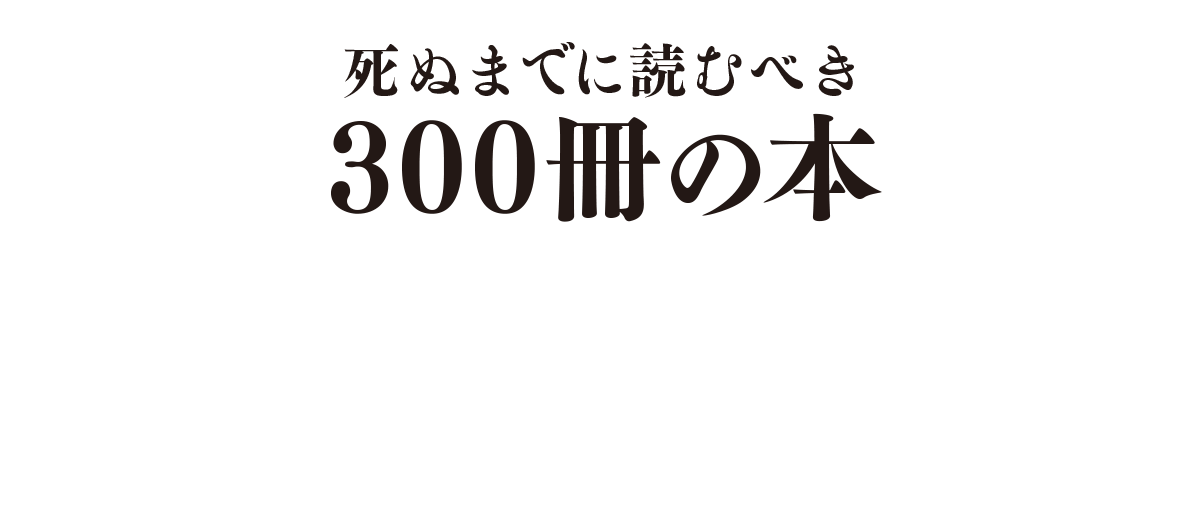超マルチ才能による文化財盗掘の物語
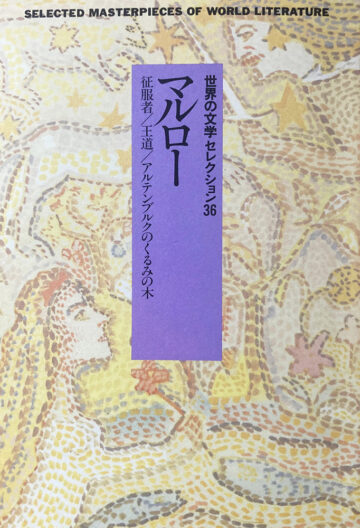
アンドレ・マルローの多才ぶりには驚かされるばかり。本題に入る前に、彼の経歴を簡単に紹介しよう。
1901年、パリ生まれ。若くしてパリ東洋語学校で東洋の言語を学ぶ。在学中にドイツ系の女性と結婚し、妻の財産を株式投資につぎ込むものの株価暴落によって破産。23年、クメール遺跡やアフガニスタンなどでの学術調査を始めるが、カンボジアの寺院から女神像を盗掘し、持ち帰ろうとしてプノンペンで捕らえられ、禁固3年の判決を受ける(執行猶予)。
その後、インドシナ解放運動・中国革命・反ナチ運動などに参加し、36年、スペイン市民戦争に参戦(同じように義勇兵として参戦していたヘミングウェイと出会う)、フランス正規軍の戦車兵、アルザス・ロレーヌ旅団の指揮官を務めるなど過酷な戦場に身を置いた。44年、ゲシュタポに逮捕され、危うく処刑されるところを救出される。それにも懲りず、自由フランス軍のアルザス=ロレーヌ旅団司令官となり、ストラスブール防衛戦やシュトゥットガルト攻略戦に参戦。この功績でレジスタンス記念章や戦争十字勲章を授与される。
作家としても特異な才能を発揮する。26年以降、『西欧の誘惑』『征服者』『王道』などの小説を立て続けに発表し、『人間の条件』でゴンクール賞を受賞。映画作家としてルイ・デリュック賞を受賞。文化防衛のための国際作家同盟を設立するなど文化活動にも尽力する。
活動のフィールドは政治にも及ぶ。45年、ド・ゴール政府の情報大臣、57年にはド・ゴール内閣で文化大臣を歴任する。また、ガリマール書店出版委員としてモーリアックやヴァレリーなどの著作を世に出すなど、ビジネスの世界においても成果をあげる。
……と、八面六臂の活躍といえば聞こえはいいが、その実ハチャメチャだった。こんな人物は世界を見渡しても100年に一人いるかどうかだろう。
そんなマルローの代表的な小説のひとつが本書だが、なんと自身がクメール遺跡の文化財を盗んだ一件を題材にするという厚かましさ。自責の念は露ほどもないらしい。そういう人が長く文化相を務めたというのだから、フランスという国の懐の深さ(?)ははかりしれない。
タイトルの「王道」とは、かつてクメール王国(現在のカンボジア)に存在した道路を指す。二人のフランス人がその道を通ってジャングルに分け入り、古寺院にある石像や壁画を盗掘に行く冒険譚である。一人はクロードという語り手、もう一人はベルケンという冒険家で、クメールの未開地では名の知られた男。古代の文化財は驚くほど高値で取引されていて、実際、若き日のマルローも一攫千金を企んで足を踏み入れたにちがいない。
ジャングルのなかにはさまざまな危険が潜んでいる。マラリアなどの伝染病や野生の生き物や現地に住む部族の襲撃など、まさに命がけの冒険が続く。
物語の最後、老練なベルケンは逆茂木(地面に埋められた尖った竹)の上に転んで膝を負傷する。その傷が化膿し、致命傷となる。彼は強烈な痛みとともに生と死について独白する。この小説は一貫して難解な表現が続き、物語の醍醐味を味わうには程遠いが、ベルケンが間近に迫る死と対峙する様子は鬼気迫るものがある。
余談だが、マルローは日本に深い関心を抱いていた。1960年に来日して「フランスをして大和魂の受託者たらしめよ」と発言したことはつとに知られている。74年に来日したときは那智滝や伊勢神宮を参拝し、自著『反回想録』で伊勢神宮について次のように記している。
「忘れられた建築家が、この社を創案したのだ。日本人が絶えることなくそれを燃しては立て直す。それゆえにこそ永遠なれと。(略)西洋の建築家は、その聖堂が久遠の石のごとくであれと夢み、伊勢の大工たちは、その柱がこの上なく壮麗な宴のごとくであれと念じた。しかしこのたまゆらは、大聖堂よりピラミッドより力強く、永遠を語る」
けだし名考察である。
髙久多樂の新刊『紺碧の将』発売中
https://www.compass-point.jp/book/konpeki.html
本サイトの髙久の連載記事