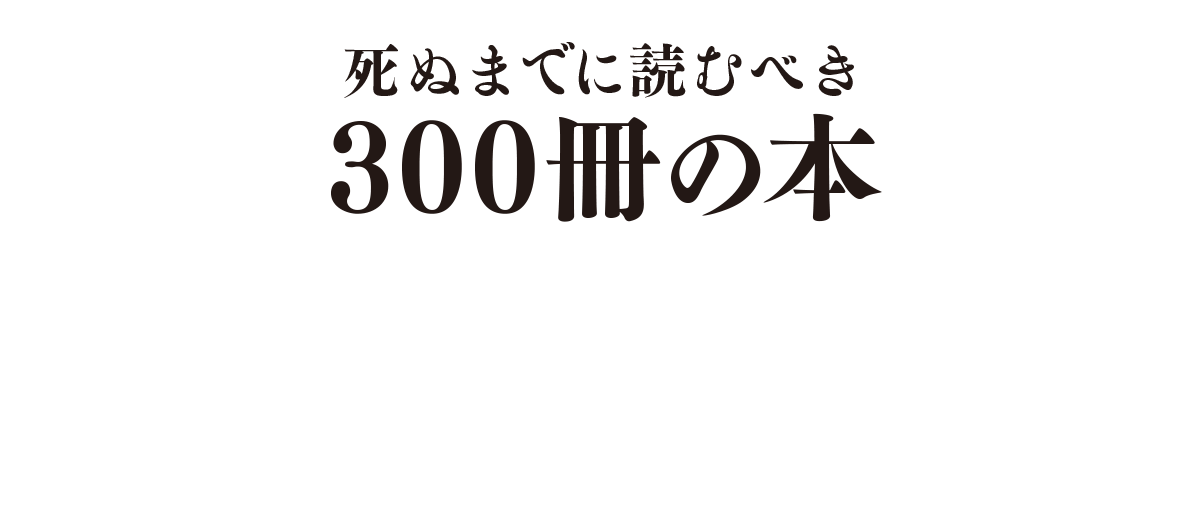日本人が日本語を失うとき
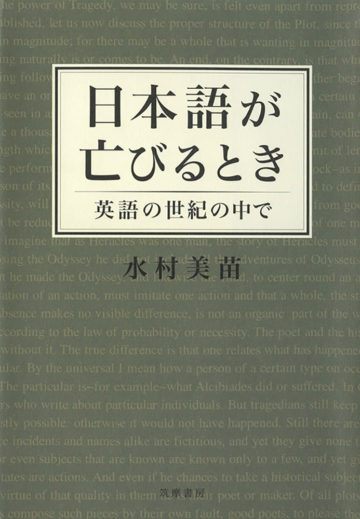
才能に溢れた人である。
12歳のとき、父親の仕事の関係でアメリカへ渡り、以後、日本の近代文学を読み漁るようになる。教養の高い家庭環境だったという理由もあるが、日本を離れていっそう日本語が恋しくなったのだろう。
そんな水村美苗が、未完に終わった夏目漱石の『明暗』の続きを書くのは自然の流れだったかもしれない。大胆にも『續明暗』を書き上げ、それをもってデビューした。漱石ファンには申し訳ないが、私は漱石の『明暗』より水村美苗の『續明暗』の方が断然好きだ。この作品で彼女は芸術選奨新人賞を受賞する。
その後、英文が混在する横組の『私小説 from left to right』で野間文芸新人賞を、エミリー・ブロンテの『嵐が丘』を換骨奪胎して日本を舞台に書き換えた『本格小説』で読売文学賞を、ここで紹介する『日本語が亡びるとき』で小林秀雄賞を、『新聞小説 母の遺産』で大佛次郎賞を受賞する。ほとんどの作品でなんらかの賞を射止めるというプライズ・ゲッターである。
本書は『日本語で書くということ』『日本語で読むということ』とともに、日本語について考察した3部作の中核をなす作品だ。
長くアメリカで生活し、日本語を希求してきた人だからわかることがあるのだろう。日本語という母国語を愛するがゆえに、そうとうな危機感を抱いている。なにしろ世界には6000ぐらいの言語があるといわれているが、そのうちの8割以上が今世紀末までに絶滅するであろうと予測されているのだ。
水村が憧れの日本に帰国し、物書きを始めた頃の様子をこう書いている。
――ふとあたりを見回せば、雄々しく天をつく木がそびえ立つような深い林はなかった。木らしいものがいくつか見えなくもないが、ほとんどは平たい光景が一面に広がっているだけであった。「荒れ果てた」などという詩的な形容はまったくふさわしくない、遊園地のように、すべてが小さくて騒々しい、ひたすら幼稚な光景であった。
あれほど豊穣な文学の森をつくりあげた日本人ではあるが、いったいどうなってしまったのだろうと戸惑うばかりの著者がそこにいる。言葉を操れず、思考は幼稚になるばかり。私も同様な危惧を覚えるひとりであるが、近年、「ので」を使わずに言葉を構築できない人がほとんどである。もはや日本語の体をなしていない。水村ともなれば、さらにその失望感はいや増したにちがいない。
人間の動きをAIが先導するように、世界の言語は加速度的に英語に収斂されている。きわめて特殊な日本語は、そういう潮流にあって、どういうスタンスをとればいいのか。
水村は「日本人をある日本人たらしめるのは、日本の国家でもなく、血でもなく、日本語なのである」と言い、「日本語は、これまで地球上に存在した文字のなかで最も複雑な文字によって表記される」と言う。だからこそ、日本語と英語をどう均衡させるべきか、深い憂慮を抱いているのだ。
戦後、国策の最上位は経済だった。その傾向はますます強まり、それとともに本来、人間がもつはずの情緒や思考能力は急速に衰えている。学校など教育の現場でも、文学の比重は下がる一方。利益を生まない学問など無用だというわけだ。
しかし、水村はこう喝破する。
――科学の進歩などが広い意味での「文学の終わり」をもたらすことはありえない。科学が進歩するに従い、逆に、科学が答えられない領域——文学が本領とする領域がはっきりしてくるだけである。ほかならぬ、意味の領域である。科学は「ヒトがいかに生まれてきたか」を解明しても、「人はいかに生きるべきか」という問いに答えを与えてはくれない。
問題は、政界や教育界にそのことを認識する人がどれだけいるか、であろう。
私は悲観的である。