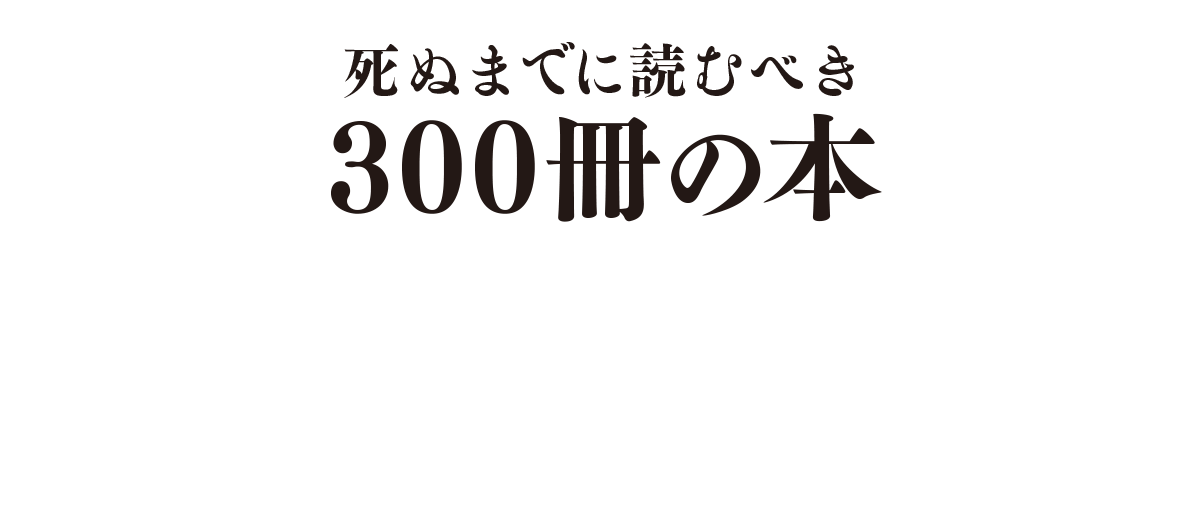プリンスホテルの成り立ちを描いた、現代版・盛者必衰の理
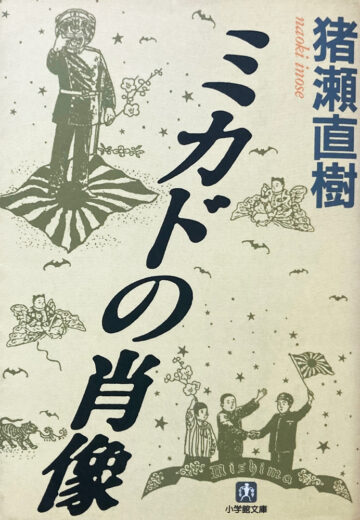
この国で天皇についてネガティブに語ることは、勇気が要る。言論界にも〝犯すべからざる神域〟が存在しているからだ。
私は天皇(あるいは皇室)について、人並みの崇敬を抱いている。本コラムでも『昭和天皇』というタイトルが冠された2つの大著を取り上げた(福田和也版と保阪正康版。
今回取り上げる猪瀬直樹氏の『ミカドの肖像』をどう捉えればいいのだろう。『土地の神話』『欲望のメディア』とともに「ミカド3部作」と呼ばれるシリーズの最初の作品である本書は、およそ900ページに及ぶ大作であり、第18 回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞している。直接的に天皇制を批判しているわけではないが、切り口はいかにも怜悧で、よくぞここまで書いたと思わあるをえない。のちに猪瀬氏は東京都知事にまでなったが、いかにも豪胆な人間の芯のようなものが文章ににじみ出ている。
本書の構成は、
第Ⅰ部 プリンスホテルの謎
第Ⅱ部 歌劇ミカドをめぐる旅
第Ⅲ部 心象風景の中の天皇
とりわけ第Ⅰ部が凄まじい。このパートはバブルの勃興期、時代の寵児として飛ぶ鳥を落とす勢いだった堤家の暗躍を描いたものだが、本書が刊行されたのはその渦中の1986年。その翌年、堤義明氏は世界一の大富豪と認定された。なぜ堤家率いる西武グループが、かくも短期間に莫大な富を得ることができたのか、著者は現場で一部始終を見ていたかのように、そのカラクリが克明に描いている。
伏線は、戦後のGHQによる臣籍降下にあった。それまで14あった宮家が3宮家に減じられたのである。それまで天皇家を含めて皇族はいっさいの税金を免除されていたが、降下した宮家は一般の国民と同じように納税の義務を負うことになった。歳費がなくなったうえ、莫大な税金を払うことになったのだから苦境に陥るのは当然のこと。
そこに目をつけたのが堤康次郎であり、その子・堤清二と異母弟・堤義明だった。彼らにとって、世間知らずの旧皇族は赤子の手をひねるようなものだった。自尊心をくすぐりながら、タダみたいな額で都心の一等地や国立公園のなかにある由緒ある土地をつぎつぎと手に入れていった。それらの土地に、〝皇族〟のイメージを抱かせる「プリンス」の名を冠したホテルを建設していった。
当時の西武は、グループ内で株式を持ち合っていた。その中核にあったのが国土計画(のちコクド)で、グループ企業の3分の2の土地を所有していた。そして国土計画の株式の40%を堤義明が持っていた。康次郎らが旧皇族から買い上げた土地は驚くほど安かったため簿価は異様に低く、そのため持ち株の評価も低かった。つまり、相続をしても堤家の財産は目減りしない仕組みになっていたのである。
文中から、金の亡者たちの姿が垣間見える。関東大震災のあと、人々が混乱の極みにある最中、彼らは電話が何台も並ぶ地下室で、ひたすら土地購入の交渉をしている描写には、さながらサスペンスを読んでいるかのような錯覚を覚えた。
栄枯盛衰は世の定め。世界一の金満家となった堤義明であったが、証券取引法違反で逮捕されたのは2005年。まさに「諸行無常の響きあり、盛者必衰の理をあらわす」を体現することとなった。
第Ⅱ部は、1885年にロンドンで初演され、欧米人に日本のイメージを定着させたといわれるオペレッタ「ミカド」を、第Ⅲ部は明治天皇の御真影を取り上げ、天皇制の本質に切り込んでいる。
髙久多樂の新刊『紺碧の将』発売中
https://www.compass-point.jp/book/konpeki.html
本サイトの髙久の連載記事