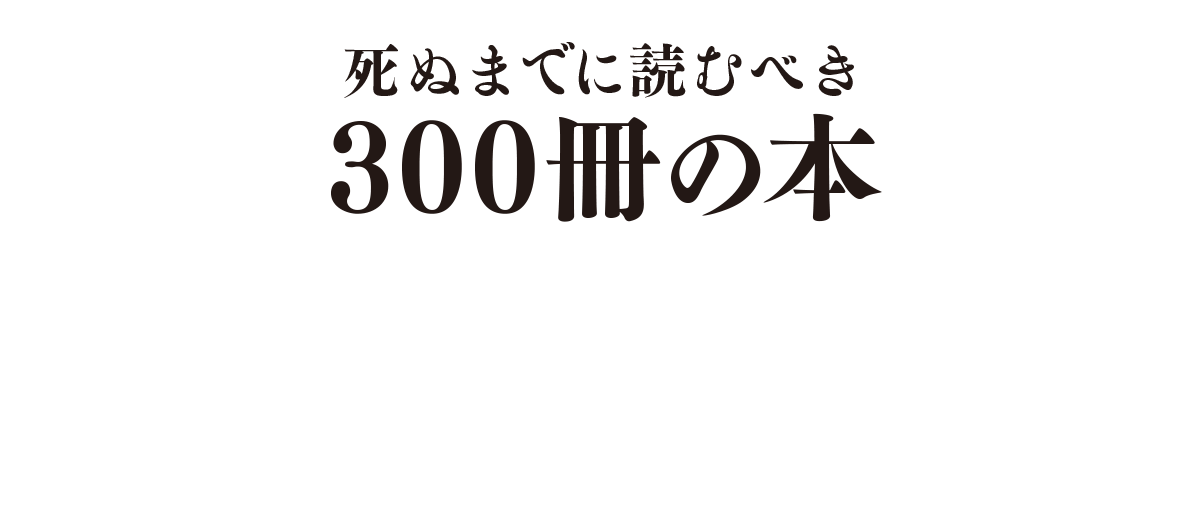命は限りあるからこそ輝く
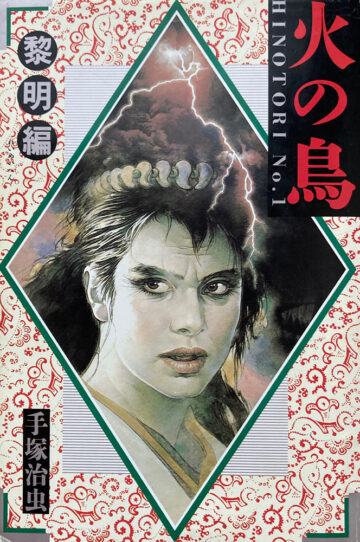
角川書店版では黎明編、未来編、ヤマト編、鳳凰編、復活編、望郷編、乱世編(上)、乱世編(下)、宇宙生命編、太陽編(上)、太陽編(下)の11巻構成だが、共通するのはタイトルにもある火の鳥。その生き血を飲めば永遠の命を得られるというもの。
だれもが死を恐れる。それゆえさまざまな宗教が生まれたともいえる。しかし、どんなに考え方を変えたところで、怖いものは怖い。
本書は、「命とは」という人類にとって最難題に真っ向から挑む巨編である。この作品群の主人公たちはこぞって火の鳥の生き血を望むが、それを飲んで永遠の命を得たとして、ほんとうにそれが幸せなことかと読者に問いかける。命は有限だからこそ輝くのではないか、と。
宇宙観が広大無辺で、読んでいて目眩がしそうだ。マンガというアプローチでこれほど壮大な真理を追求したこと自体、驚き以外のなにものでもない。いったい手塚治虫はいかなる生命観を持っていたのか。
根っこは仏教なのだろう。『ブッダ』という長編も描いているように、手塚治虫は仏教の真髄に通じているようだ。因果応報という言葉がこれほど鋭く心に突き刺さることはない。彼の描く時間は、円環をなしていたり、果てのない未来を描いたりと縦横無尽である。
どの作品もよく練られたストーリーで甲乙つけがたいが、印象に残るのは八百比丘尼と山之辺マサトの物語。
前者は戦国時代のある女性が父を激しく憎み、父の病を治そうとする八百比丘尼を殺害する。しかし、それから時間の円環のなかに閉じ込められる。女性はその円環のなかで火の鳥の羽根を使って人々の病を治すことに専念するのだが、じつは自分が殺害した八百比丘尼こそ自分なのだと気づく。いずれは〝若き日の自分〟が自分を殺しにくるとわかってしまったのだ。やがて自分を殺しに来た自分が現れるが、八百比丘尼は粛々とその運命を受け入れる。そして、すぐまた他の場所で自分が生まれ、長じて自分(八百比丘尼)を殺しに行くという設定だ。何代も何代も、円環のなかで同じ宿命を受け入れて生きなければならないという因果! これほど残酷なことがあろうか。
山之辺マサトの物語も気が遠くなるほど遠大だ。核戦争の後、人類は滅びるが、山之辺マサトだけが永遠の命を得ているため、死ぬことができない。生き物がすべて絶滅し、地球は氷河期を迎え、再びコアセルベートが出現してさまざまな生き物が現れ、やがて人類が登場して繁栄を極め、そしてまた争いの末、絶滅する。その気の遠くなるような長大な時間の繰り返しをたった一人で生き続けなければならないという苦しみ。しかも終わりがない。生き物の誕生から全滅するという長大な歴史を無限に傍観しなければならない。読んでいて背筋が凍りつきそうだ。
他のどの作品にも、共通して描かれるのは「命とは?」というテーマである。あらためて凡常を脱した手塚治虫の偉大さを知った。いま、その余勢を駆って、毎日『ブラック・ジャック』を1編ずつ読んでいる。
髙久多樂の新刊『紺碧の将』発売中
https://www.compass-point.jp/book/konpeki.html
本サイトの髙久の連載記事