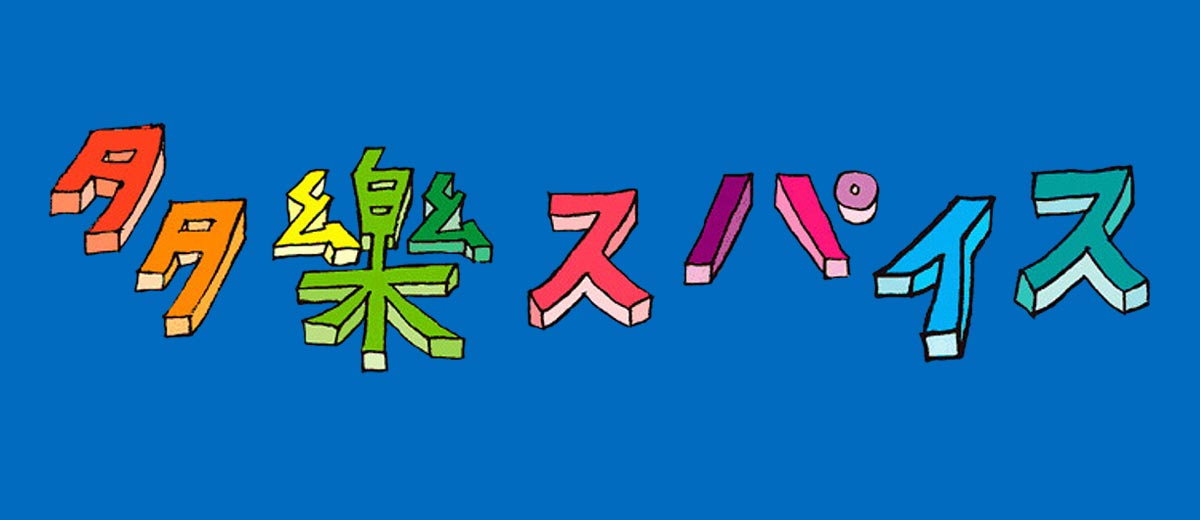沼津御用邸について
 なんと、今夏、那須御用邸にご行幸される天皇・皇后両陛下をお迎えする列に加えさせていただく僥倖に恵まれた。日取りは明かせないが、そう遠い日ではない。
なんと、今夏、那須御用邸にご行幸される天皇・皇后両陛下をお迎えする列に加えさせていただく僥倖に恵まれた。日取りは明かせないが、そう遠い日ではない。
私が日本女性の中で最も尊敬しているのは、なにを隠そう、皇后陛下である。皇后陛下の御歌がフランス語訳され、彼の地で評判になったというのは『祈りの御歌』という本に詳しいが、美智子皇后陛下の感性と表現力は “この世のものとは思えない”ほど傑出している。しかも、歌だけに限らず、多方面に才能を発揮されている。さらに、あの淑やかな立ち居振る舞いである。それをどうしてリスペクトせずにいられようか。
そのような畏れ多い状況下でもあるので、今回は沼津御用邸について書きたい。
沼津御用邸は明治26(1893)年、ご容態がすぐれなかった大正天皇(当時は皇太子)のご静養のために造営された。以後、昭和44年に廃止となるまで明治、大正、昭和と、歴代の天皇皇后両陛下や皇族の方々に利用されている。
沼津御用邸が建てられた当時は、近隣に大山巌(陸軍大臣)、川村純義(海軍大臣)、大木喬任(文部大臣)、西郷従道(陸、海軍大臣)の別荘が建てられていたというが、そうそうたる面々が駿河湾を臨むこの温暖な地に保養所を構えていたのである。
ある年の初夏、沼津御用邸跡の記念公園を訪れたが、敷地は広大で建物は手入れが行き届いていた。やはり日本人のDNAを引き継いでいるので、やんごとない空気に触れると条件的に背筋が伸びる。
右上の写真は、調理室である。最新のキッチンなどと比べると、時代がかっているのは仕方ないと思うが、じつに清潔な佇まいであった。この調理室で働いていた人たちは、極度の緊張と誇りを同時に味わっただろう。
(110721 第267回 写真は旧沼津御用邸の調理室)