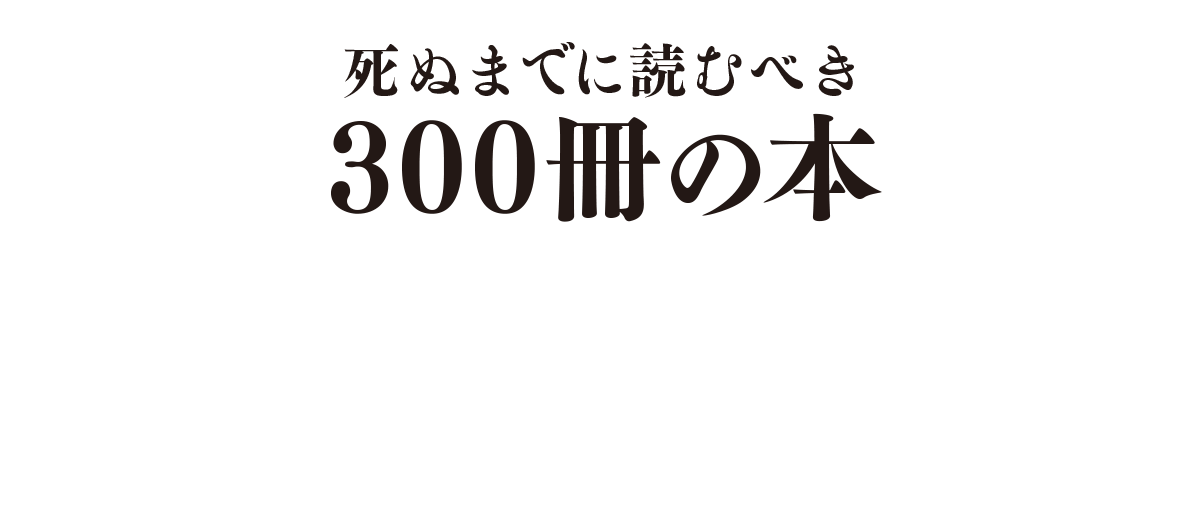悪徳という土壌に咲く、絢爛な華
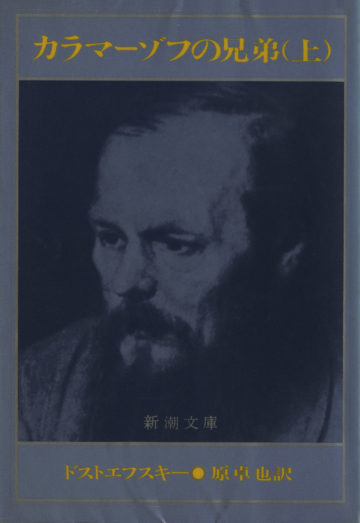
19世紀中期、農奴解放後のロシアの社会混乱を背景に、底なし沼のような人間の多面性を描き、世界文学史の頂点のひとつとして揺るぎない評価を確立している。
この頂に初めて登ったのは22歳の頃だった。読み終わった時、得体の知れない奇妙な感覚に支配された。人間というのはこんなにも不可解な生き物なのか、きちんとその本性を見られるようにならなければとんだ落とし穴にはまってしまうぞと思った。
人間の負の面にこそ真実が隠されている。あらゆる生き物のなかで不自然なほど大脳が発達してしまった人間は科学的な進歩を重ねてきたが、肝心の人間性は向上するどころか、ますます劣化している(と映る。もちろん自分も含めて)。その証拠に、ほかの生き物がけっしてしないような残酷な事件があとを絶たない。人間は素晴らしくなんかないのだ。しかし、だからこそそれを凝視し、自己の内側に存在する悪徳に抗いながら(あるいは認めながら)限られた生をより良くしようとすることに人間の美しさがあるといえるのではないだろうか。
それにしてもロシアで生まれた本作といい、南米コロンビアで生まれた『百年の孤独』といい、不安定な社会にとてつもない傑作が生まれるのは不思議なことだ。小説とは苛烈な環境にはびこる悪徳という土壌を栄養にして咲く悪の華でもあるのだろうか。あるいは、活断層のズレが巨大地震を引き起こすのにも似て、社会の不整合性が偉大な才能から傑作を引き出すのであろうか。
この作品に登場する人物たちが発する、とてつもないパワーに驚愕する。バルザックの作品にも同じことが言えるが、どうしてこうも強烈な自我と個性をもった幾種類もの人間を描けたのか。
本作の主な登場人物は、カラマーゾフ家の家長であるヒョードルと3人の息子(+住み込み料理人のスメルジャコフ)である。ある日、ヒョードルが殺害されるが、下手人はだれかという謎解きが重要なファクターになっていて、推理小説にも似た構造を有している。
しかし、この作品が単なる謎解きに堕していないのは、父親殺しの嫌疑をかけられた長子ドミートリイの裁判を通じ、当時のロシアという国の実体を暴いていくエピソードをはじめ、世界の文学史に残る名場面がいくつもあるからだ。裁判の様子は恐ろしいほどのリアリティに満ちており、また登場人物が醸す物欲、愛欲、金銭欲、知識欲、信仰心などは、あたかも人間性の見本市のようでもある。そして、これこそがきわめて重要なのだが、読み進めるうち、それらは自分を含め、あらゆる人間に内包されているのだと気づかされる。どんなに凶悪な悪人でもひとかけらの善意はあるだろうし、崇高な人間と思われていた人がちょっとしたきっかけで信じられないような悪事をなすこともある。本書を哲学書と括ってもいいと考える所以は、そこにある。
物語を簡単に書こう(簡単に書くのは容易ではないが)。
カラマーゾフ家の主・ヒョードルは粗暴で強欲、好色と悪徳をすべて備えたような人物だ。彼の3人の息子のうち、長兄のドミートリイは軍隊から帰ってきたばかり。猥雑で情熱的、豪放闊達で父親にもっとも似ている。婚約者がいながらグルーシェンカという女をめぐって父と反目しあっている。次兄のイワンは知的で冷静沈着、徹底した背神論者であり、モスクワに住んでいる。末っ子のアレクセイ(愛称アリョーシャ)は地元の修道院の修道僧。敬虔な生活をおくり、長老ゾシマを師と仰いでいる。その4人に加え、ヒョードルの私生児と噂されるスメルジャコフがからみ、物語はめまぐるしく展開し、急転直下の結末を迎える。
ある日、ゾシマの仲介でカラマーゾフ家の面々が一堂に会す。顔を合わせるや、フョードルとドミートリイはグルーシェンカをめぐって大ゲンカを始める。ドミートリイにはカテリーナという婚約者がいることも明かされる。しかもカテリーナの大金をくすねてグルーシェンカとの遊興に使ってしまったという卑劣漢だ。読者の多くは、のちにヒョードルが殺害されることを知って読み始めているだろうが、ドミートリイが父親殺しの動機をふんだんにもっていると明示される。
いっぽう、無神論者のイヴァンにとって、まじめくさった顔で神に仕える弟アレクセイは癪に障る存在だ。ことあるごとに神などいないと弟に説く。「神がなければ、すべてが許される」と。それを聞いたスメルジャコフは喜びに身を震わせる。彼もまた神の存在に疑問を抱いているからだ。
やがてドミートリイは許嫁カテリーナと縁を切るため、彼女に返す金を工面するため父の金を盗もうと忍び込むが、使用人に見つかり逃走する。そしてグルーシェンカが昔の愛人と会っているということを知っていても立ってもいられず、その現場へ急行し、恋敵を追い払う。グルーシェンカはそんな男らしさにほだされ、彼に愛の告白をするが、ドミートリイは父フョードルを殺害したという容疑で警察に逮捕される。数々の証言は、すべてドミートリイに不利なものばかりだった。
ドミートリイが犯人だと思うイヴァンは、スメルジャコフが犯人だと見るアレクセイと絶交する。
しかし、物語は思わぬ方向へ展開する。スメルジャコフが犯行を自白し、イヴァンに殺人を許可されたのだと言うのだ。怒ったイヴァンはスメルジャコフに対し、明日の裁判で真実を言えと言うが、その後、スメルジャコフは自殺してしまう。
裁判は紆余曲折の末、ドミートリイの有罪を断定し、シベリア流刑懲役20年を言い渡すのだが……。
この大作の〝肝〟はいくつかあるが、そのひとつがイヴァンがアレクセイに語って聞かせる「大審問官」という自作の物語詩である。話の舞台は、異端審問が吹き荒れるスペインの街。ひとことで言えば、精神の理想と飢えをしのぐパンと、どちらが重要かというテーマだ。マタイ伝でキリストは「人はパンのみにて生くるにあらず」と言うが、実際はパンがないために飢え苦しむ人が大勢いる。理想だけで空腹を満たすことはできない。だからこそ、パンを得るために犯罪も起こる。
これは永遠のテーマでもあるだろう。事実、理想だけでは食べていけない。しかし、宗教をことごとく否定し、やがてそれが共産主義や社会主義となって結実するものの、新たな差別と弾圧と飢餓を生んだ。われわれ現代人は、20世紀の歴史を通して、その道筋を正確にたどることができる。そういった壮大なテーマに、19世紀の大文学者が挑んだのである。
もうひとつは、ドミートリイを被告とした裁判であろう。次々と暴かれるロシア社会の闇は、そのまま人間の悪徳(ときに美徳)と対になっている。まさに透かし絵のような社会批判だ。
では、真犯人はだれか? ここにきっぱりと書きたいが、ネタバレは困るという読者がいるため、あえて書くのはよそう。
この小説は、多くの事実が背景にあることも特筆すべきだろう。そもそもドストエフスキーのファースト・ネームはヒョードルであるし、彼の父親は実際に殺されている。しかも、ある事件にからみ、ドストエフスキー自身が死刑を宣告され、処刑の直前に恩赦され、財産没収と懲役刑に処されるという辛酸を嘗めている。つまり、ドストエフスキーは死の恐怖をまざまざと体験しているのである。
苛酷な体験をし、それを養分として生涯の最後に書き上げた大作、それが『カラマーゾフの兄弟』だ。
●知的好奇心の高い人のためのサイト「Chinoma」10コンテンツ配信中
本サイトの髙久の連載記事
髙久の代表的著作