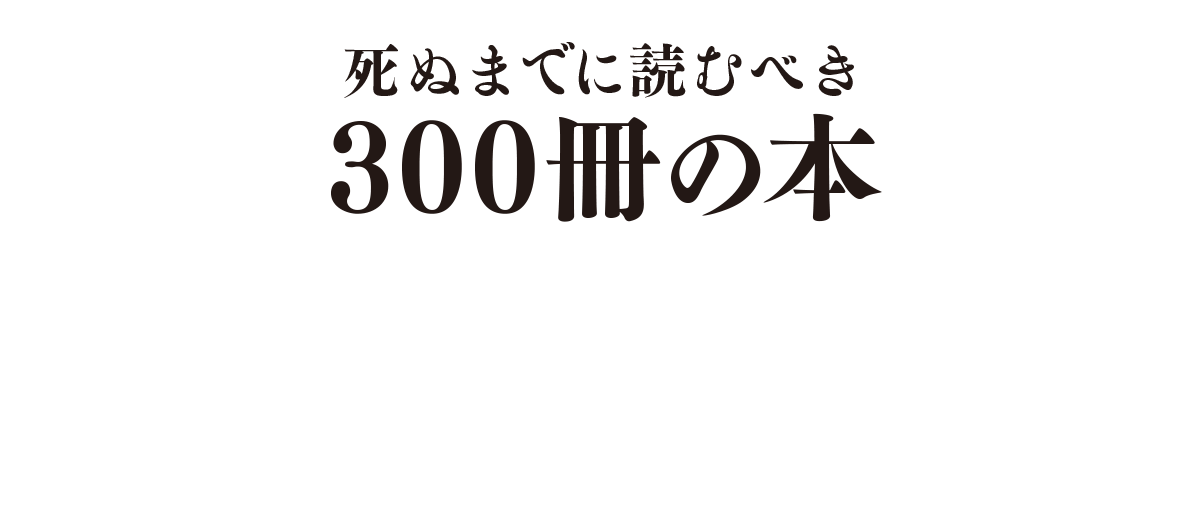現代の日本人への、毒にも薬にもなるギフト
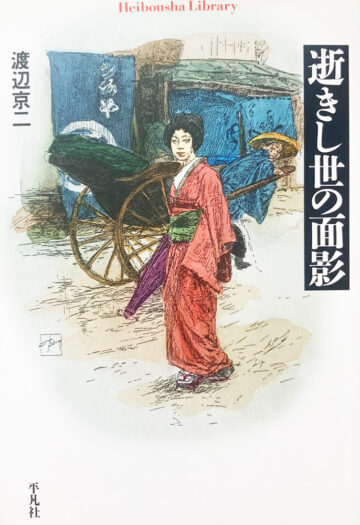
幕末から明治期にかけて来日した外国人が、日本に対する印象を書き記した日記などの引用を目にすることがある。概ね、絶賛に近い。正直に書けば、ほんとうにそうだったのだろうかと疑問に思うこともあった。
そんな思いを抱いている人は本書を読めば、さまざまな疑問が氷解するだろう。
細かい文字組で600ページ弱。著者はほぼ主観を控え、客観的な観察者に徹している(もちろん、どの記述を引用するかですでに恣意的ではあるのだが)。当時の日本を賛美する記述ばかりではなく、辛口の日本批判もある。
ここに描かれているのは〝かつて〟存在した旧き日本の姿。タイトルに「逝きし世」とあるように、すでに滅びてしまった文明の残像である。読みながら、どこか未知の国の描写に思えるものもあるが、「ああ、たしかにこういう面は現代にも残っている」と思えるものもあるから、完全に「逝きし世」とは言い切れない。半分はわれわれ日本人の血のなかに残っていると信じたい。とはいえ、本書に描かれている日本人の姿はほぼ絶滅したと言ってまちがいはないだろう。そういう意味でも、本書はかつてあった文明の発掘資料ともいえる。
内容は14の章に分けられている。
第1章 ある文明の幻影
第2章 陽気な人びと
第3章 簡素とゆたかさ
第4章 親和と礼節
第5章 雑多と充溢
第6章 労働と身体
第7章 自由と身分
第8章 裸体と性
第9章 女の位相
第10章 子どもの楽園
第11章 風景とコスモス
第12章 生類とコスモス
第13章 信仰と祭
第14章 心の垣根
まず驚かされるのは、来日した外国人の記録の量と緻密さである。それだけ当時の日本はワンダーランドだったのだろう。
とりわけ多いのは、日本の風景に対する感嘆である。読んでいてむず痒くなるほど、常軌を逸した賛美が続く。なぜ「むず痒く」なるかといえば、現代日本の風景は、醜悪そのものだから。都市は無個性で無秩序、郊外にも汚い看板があふれ、森の大半は植林された後、放置されたスギ林。はたして現代の外国人の目にどう映るのだろうか。
日本人は子供を可愛がるという記述にも驚いた。それが当たり前だと思い込んでいたが、西洋はそうではないらしい。日本の女性があけすけで、裸体を衆目にさらすことをなんとも思っていないという記述も多い。
いくつか引用してみよう。
「日本人は私がこれまで会った中で、もっとも好感のもてる国民で、貧しさや物乞いのまったくない唯一の国です。私はどんな地位であろうともシナへ行くのはごめんですが、日本なら喜んで出かけます」(オリファント)
「日本人のように遊び好きといってよいような国民の間では、子供特有の娯楽と大人になってからの娯楽の間に、境界線を引くのは容易ではない」(グリフィス)
「住民すべての丁重さと愛想のよさにどんなに驚かされたことか。地球上最も礼儀正しい民族であることは確かだ」(ボーヴォワル)
「アメリカ人にとっては安価と粗悪は同意語なのだが、日本ではもっとも低廉な品物に優美で芸術的なデザインが見出される。日本の職人は本能的に美意識を強く持っているので、金銭的に儲かろうが関係なく、彼らの手から作り出されるものはみな美しい」(アリス・ベーコン)
……このへんでやめておこう。
渡辺京二は現代の日本人に、毒にも薬にもなるギフトを遺してくれた。それを吟味するかどうかは、あなた次第。
髙久多樂の新刊『紺碧の将』発売中
https://www.compass-point.jp/book/konpeki.html
本サイトの髙久の連載記事