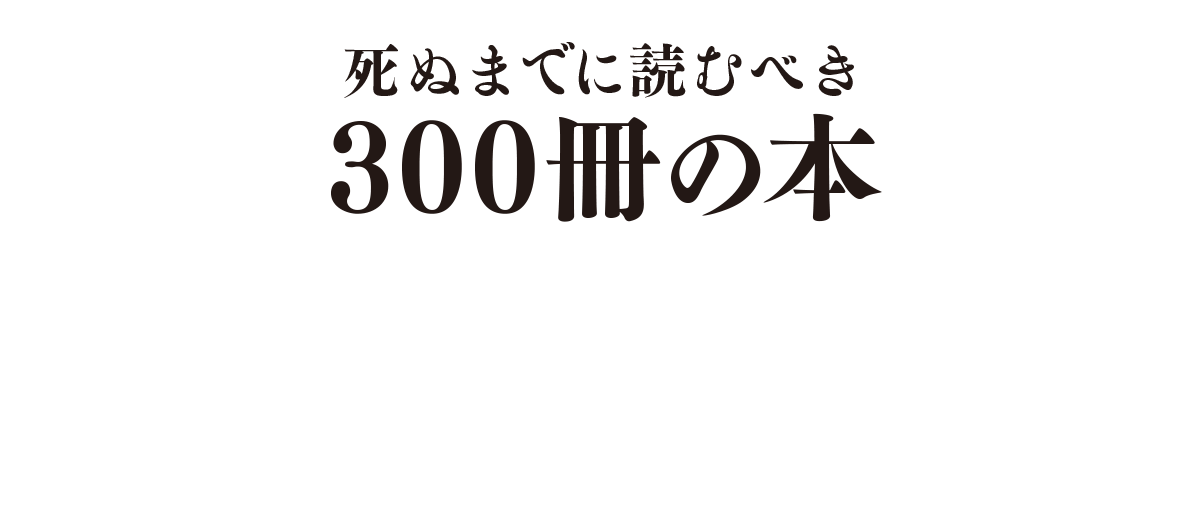貧しき人々への愛惜に満ちた人間讃歌

子供の頃から本好きだった私にとって、小説の王様と言えば、『レ・ミゼラブル』と『モンテ・クリスト伯』でキマリ。両作品は、年少者用に編集された『ああ無情』『巌窟王』から親しんでいる。世界文学全集に収められていたダイジェスト版をはじめ、繰り返し読んだ。
しかし、完全版(新潮文庫)を読んだのは、実は45歳の時だった。
弁解するわけではないが、『レ・ミゼラブル』の完全版を理解するにはある程度の年輪が必要だ。慈愛のかたまりのようなミリエル司教に感化されたジャン・ヴァルジャンは、いきなり善良な人間になってしまうというイメージがあるが、実はそう簡単に黒から白へ変われるものではない。飢えに苦しむ家族のために一本のパンを盗んだことから19年間も牢獄につながれたジャンは、世の中への憎悪をみなぎらせていた。頑なな心がそう簡単にほぐれるはずもなく、改心するまでにはさまざまな相克を経ている。その証拠に、銀の燭台を与えられ放免されたジャンは、その直後にジプシーの少年を脅し、金を奪っている。善意と悪意が心のなかで葛藤し、徐々に改心していく心情の変化は、若い時分にはなかなか理解できないかもしれない。
ジャンを執拗に追うジャヴェール警部の最後の葛藤も読み過ごしてしまうかもしれない。まして、コゼットという、保護すべき存在が目の前に現れてからジャンの心のなかに愛が灯ったことなど、なかなかわかりにくいだろう。それらは、微風を受けた葉のように、じっと目を凝らさなければわからない程度のかすかな徴しだから。
この作品は人生経験を積めば積むほど、味わいが増してくる。だから、何度読んでも飽きることがない。自分の成長と合わせ、作品も変化するのだから。
ヴィクトル・ユゴーは、1845年にこの作品の執筆を開始した。3年後の48年に二月革命が起こり、執筆を一時中断。その12年後の60年に執筆を再開し、62年、完成にこぎつけた。
刊行当時、フランスはナポレオン3世による第二帝政を迎えていた。国会議員を務め、政治家でもあったユゴーは、ナポレオン3世の独裁を批判し、第二帝政が終わるまで帰国しないと公言し、英仏海峡に浮かぶイギリス領の島に亡命していた。
彼は、この作品の売れ行きを心配し、出版社に「?」とだけ記した問い合わせの手紙を出すと、「!」とだけ記された返事を受け取った。この2通は、世界一短い手紙としてギネスに掲載されている。
当時は、産業革命が始まって間もない頃だった。都市には劣悪な環境で酷使される労働者があふれていた。食べ物は、雑穀入りのパンがある程度。ジャン・ヴァルジャンが盗んだパンは、それさえ食べられなかった貧しき人の象徴として描かれている。コゼットは、休暇にきていた兵士の落し胤だが、不義の子は差別の対象となっていた。この作品の底に流れている、貧しき人々への限りない愛惜は、政治家の目をもったユゴーの心情でもある(この作品のタイトルは「憐れな人々」という意)。
それにしても壮大な小説である。
ナポレオンが失脚し、共和制へと移行する19世紀フランスを舞台に、人間の愛憎が乱れた糸玉のようにからまりあう。しかし、どんなにからまっていようとも、糸は一本につながっている。それは前述のように、貧しき人々への愛惜だ。
やがてコゼットと結婚することになるマリユスと卑劣漢テナルディエとコゼットのつながりなど、小説以外にはありえないかもしれない。ほかにも小説的な辻褄合わせが多く、見方によっては〝つくりもの〟の感は否めない。
だが、ユゴーは超然とした筆致でいささかも不自然さを読者に与えない。あらためて言うまでもないことだが、小説はあくまでも作りごと。しかし、その作りごとが実社会に起きたことのひとつだといささかの疑いもなく読者に思いこませることができなければ、その小説は未完成ということになる。
『レ・ミゼラブル』は壮大な世界観と崇高な宗教観にも裏打ちされている美しい作品だが、作者のヴィクトル・ユゴーとはどんな人物だったのか。これについては、本コラムで紹介した『パリの王様たち』に詳しい。フランスの三大文豪であるユゴー、デュマ、バルザックが成功に至るまでの過程、金銭感覚、異性観、社会観などを綴ったものだが、特にユゴーの性欲は蒸気機関車のようにすさまじく、80歳くらいまでひと晩たりとも女性なしでは眠れなかったという。
ところで、この作品を手放しで礼賛できない理由がある。それは、いきなり物語の本筋からはずれ、延々と饒舌な描写が続くこと。ユゴーの『ノートルダム・ド・パリ』やデュマの『モンテ・クリスト伯』もそうだが、そういう記述を読み進めるのは容易ではない。よくもまあ、こんなにモノを知っているものだと驚き、かつ、昔の読者は飽きずに読んだものだと感心する。
本作でも、ワーテルローの戦いや隠語、パリの下水道などについて、延々と御託が続く。忍耐力を試されているのかと思うほどに。
 最後に……。この長大な作品を読み解くうえで、最良のサブ・テキストを紹介しよう。
最後に……。この長大な作品を読み解くうえで、最良のサブ・テキストを紹介しよう。
鹿島茂氏の『レ・ミゼラブル 百六景』(文春文庫)である。106枚の挿絵をもとに、そのシーンの解説をしたものである。当時の読者たちは、それらの挿絵を眺めながら、この滋味あふれる小説世界に耽っていたのであろう。
人類が続く限り、読み継がれる作品であることは間違いない。
髙久の最新の電子書籍
本サイトの髙久の連載記事