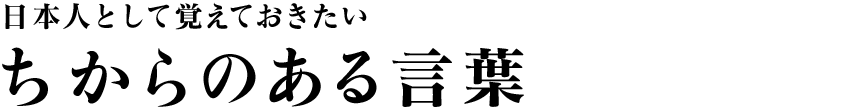いつの時代にも通用する、普遍的な言葉があります。
それぞれの時代を懸命に生き、一事をなした人たちの一言だからこそ、今もなお私たちの心を揺さぶり続ける言葉の数々。“心の栄養”として、活用してください。
Topics
マイケル・ディルダ
「ワシントン・ポスト」紙で長年書評欄を担当し、ピューリッツァー賞を受賞した練達の書評家、マイケル・ディルダの言葉を紹介。著書『本から引き出された本』の中の第3章「仕事と余暇」の中の一文である。 ひらめ…
安田登
能楽師の安田登氏の言葉を紹介。下掛宝生流ワキ方を務める安田氏は、高校教師時代に能に魅了され27歳で入門したという。体を整えるボディーワーカー、ロルファーの資格を有し、能と絡めた活動も行っている。今年5…
外山滋比古
ベストセラー本「思考の整理学」で知られるお茶の水女子大名誉教授、外山滋比古氏の言葉を紹介。某新聞の中面にあった。「遺言は書かない。精一杯のことをして死ぬときは死ぬ」と語る外山氏。人生100年時代という…
世阿弥
引き続き世阿弥の『風姿花伝』から抜粋を。こちらも第七別紙口伝、「因果の花を知ること、窮めなるべし」にあった。わかっちゃいるけど…と思うことをあえて取りあげてみた。誰もが一度は経験したことがあるのではな…
世阿弥
日本最古の教育書ともビジネス書とも言われる世阿弥の『風姿花伝』。その第七「別紙口伝」より抜粋した。能の確立者である観阿弥の長男として生まれ、十代にして時の将軍、足利義満に見出された世阿弥は、室町時代に…
清水克衛
ベストセラー本は置かず、店長自らが読んでいいと思う本しか取り扱わないという独特のスタイルで全国に多くの固定ファンを持つ書店「読書のすすめ」。店長の清水克衛氏が月一回会員向けに書く会報「成幸読書」がこれ…
『星の王子さま』より
サン=テグジュペリの『星の王子さま』の中で、キツネが王子さまに言った言葉だ。「大切なものは目に見えない」と言ったあとに続けてこう言った。当然至極の言葉だが、キツネはさらにこう続けた。「人間たちは、この…
秋吉則州
大徳寺塔頭芳春院住職、秋吉則州和尚の言葉だ。掃除は禅宗の基本の「き」。悩める人ほど掃除せよと喝破する秋吉和尚の著書『日日是掃除』にあった。情報化社会の現代になって、迷える人が多くなった。情報が増えれば…
ラッセル
三大幸福論と言えば、アランの「幸福論」、ヒルティの「幸福論」、そしてラッセルの「幸福論」。中でも精神性より現実性を重視したのがラッセルである。哲学者としてノーベル賞も受賞した彼の幸福論は、客観的に生き…
「大学」より
中国の古典「四書五経」のひとつ、「大学」の中でも比較的有名な言葉。殷の湯王が毎日使う洗面盥に刻んだ句だという。明治維新の「維新」は「維(こ)れ新たに」という意味で、この句が元になっているそうだ。松下幸…