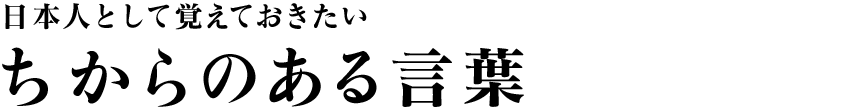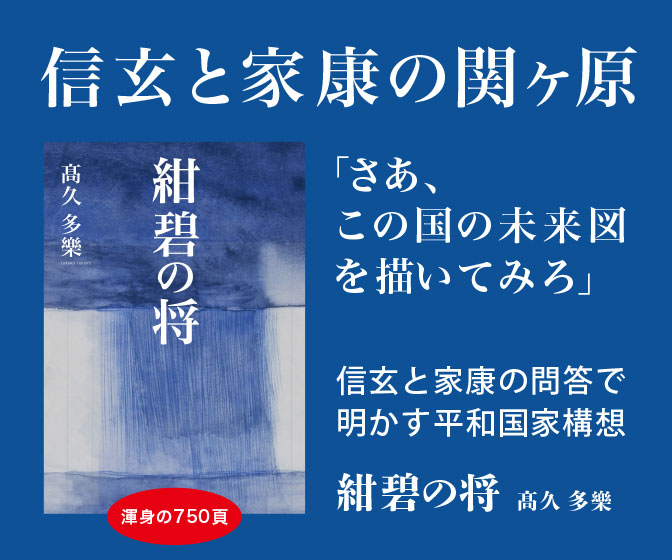ADVERTISING
いつの時代にも通用する、普遍的な言葉があります。
それぞれの時代を懸命に生き、一事をなした人たちの一言だからこそ、今もなお私たちの心を揺さぶり続ける言葉の数々。“心の栄養”として、活用してください。
Topics
村田諒太
元世界ボクシング協会ミドル級王者、村田諒太氏が現役引退の表明をした。某新聞でそのことを見知った。失礼だとは思うが、当欄を閲覧してくださっている読者の方々にも知って欲しくて、言葉の断片を切り張りさせても…
カズオ・イシグロ
2017年、ノーベル文学賞をこの人が手にした時は胸躍った。日本生まれで英国籍の作家、カズオ・イシグロ氏である。『日の名残り』などの作品から漂う、物静かで上品な人柄を思わせるイシグロさん。彼が黒澤映画の…
養老孟司
解剖学者の養老孟司氏の言葉だ。空前の大ヒットとなり、その名を世に知らしめた著書『バカの壁』の第四章のタイトルである。遅ればせながら本書を読んで、己のバカさ加減に辟易している。ガツンと頭をぶん殴られた気…
小川洋子
作家の小川洋子さんのエッセイ集『遠慮深いうたた寝』で、この言葉を見つけた。終盤の「答えのない問い」というエッセイの中の一文だ。『アンネ・フランクの日記』の愛読者でもある小川さんにとって、ホロコースト文…
織田憲嗣
世界的に知られる椅子研究家の織田憲嗣さんの言葉だ。某新聞の特別面で紹介されていた織田さんの暮らしの文面で見つけた。高島屋勤務を経て独立後、グラフィックデザイナーなどの仕事をしていたという織田さん。仕事…
棟方志功
版画家、棟方志功の言葉である。作品・文集『棟方志功ヨロコビノウタ』の中の、1954年に製板された『華狩頌』という作品に添えられている。鳥や獣がいる花咲く森の中で、武器を持たず馬に乗って狩猟をする古代人…
『語りかける花』より
染色家の志村ふくみさんは草木から色を引き出すプロフェショナルだが、色といっしょに草木の言葉も引き出したのだろうか。蓄えた言葉の色のゆたかなこと。随筆『語りかける花』には、草木に耳を傾ける志村さんの姿が…
坂村真民
仏教詩人、坂村真民の詩のタイトルである。一度は目にしたり、耳にしたことがあるのではないか。誰でもわかる直球の言葉だからこそ、胸に残る。詩の内容は知らなくても、タイトルだけでじゅうぶん伝わる。詩そのもの…
ハリエット・ローラー
前回につづき、映画『あなたの旅立ち、綴ります』から。ハリエット・ローラーの言葉をもうひとつ紹介しよう。どちらも甲乙つけ難く、どちらにしようかと迷った片方の言葉だ。生前に訃報記事を書くよう依頼した地元の…
ハリエット・ローラー
映画『あなたの旅立ち、綴ります』の中で、シャーリー・マクレーン演じるハリエット・ローラーが語った言葉だ。自信家で嫌われ者のハリエットは、あることをきっかけに人生の終活をするのだが、映画の後半、余命わず…