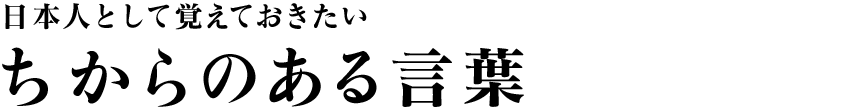いつの時代にも通用する、普遍的な言葉があります。
それぞれの時代を懸命に生き、一事をなした人たちの一言だからこそ、今もなお私たちの心を揺さぶり続ける言葉の数々。“心の栄養”として、活用してください。
Topics
東郷茂徳
開戦当時の外相、東郷茂徳の辞世の句である。山田風太郎の『人間臨終図鑑』より抜粋した。東郷は昭和16年東條内閣において外相の地位にあり、そのときの日米交渉でアメリカからつきつけられたハル・ノートの苛酷さ…
村上春樹
これが格言的なちからのある言葉かと問われると、はっきりYESとは言い難い。言い難いけれど、「たしかにそうだ」と思って取り上げた。村上春樹氏の著書『職業としての小説家』にあった。「効率」とはほど遠い想像…
『梁塵秘抄』より
後白河院が編纂した今様集『梁塵秘抄』から。中でも一番有名なのが、この一首だろう。そういえば樹木希林さんも生前、『梁塵秘抄』を愛読していたそうな。彼女の生き様もこの歌のように無邪気そのものだったろうと思…
ターシャ・テューダー
自然と手作りを愛した絵本作家、ターシャ・テューダーの言葉である。ガーデナーの先駆けとしても知られている彼女の庭は季節の花々で彩られ、亡くなった今も多くの人が訪れるという。晩年、体の衰えを感じたターシャ…
開高健
1961年のトリスウヰスキーのキャッチコピー「人間らしくやりたいナ」を手がけた、作家、開高健の言葉である。戦後の高度経済成長期のただ中で、いち早くその違和感をウヰスキーのコピーにして社会に提示した開高…
藤原正彦
数学者、藤原正彦のエッセイはじつにおもしろい。この言葉も著書『祖国とは国語』にあったのだが、身の上話も自虐話も、社会への提言でさえ嫌味なくサッパリとして、まったく偉そうでないところがいい。数学者とは思…
西行
桜の歌人、西行の歌である。『新古今和歌集』巻第四秋歌上の299首目がこれだ。桜を詠ませたら右に出るものはいないというほど典雅な歌を詠む西行だが、秋の歌も秀逸である。事情あって世捨て人となったからこそ、…
ラルフ・ウォルドー・エマーソン
ヘンリー・ソローの師であり友人であったラルフ・ウォルドー・エマーソン。彼のエッセイ『自己信頼』は自己啓発本としても人気だが、そもそもエマーソンのいう自己信頼とは「個人の無限性」、すなわち真理は己の内に…
ある文化財修繕者の言葉
この言葉に出会った時、なるほどそうかといたく感心した。故・河合隼雄と小川洋子の対話集『生きるとは、自分の物語を作ること』の中に見つけたのだが、京都の国立博物館の文化財を修繕する人が言ったそうだ。布を修…
大住良之
サッカージャーナリストの大住良之氏の発言である。サッカーマガジンの編集長を務める傍ら、女子サッカーチームの監督や日本サッカー協会審判員などを歴任するサッカー指導者でもある大住氏。ジャーナリストという立…