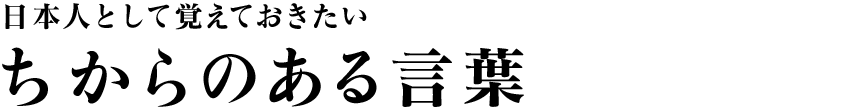いつの時代にも通用する、普遍的な言葉があります。
それぞれの時代を懸命に生き、一事をなした人たちの一言だからこそ、今もなお私たちの心を揺さぶり続ける言葉の数々。“心の栄養”として、活用してください。
Topics
武満徹
作曲家、武満徹の言葉を紹介。「学校にはぼくは縁が薄く、ついに一度も音楽教育というものを受けませんでした」と、中学校もろくに出ていないと告白する武満。独学で音楽を学び、「世界のタケミツ」となったのは学校…
ノヴァーリス
ドイツ・ロマン派の詩人、ノヴァーリスの言葉だ。貴族の家系に生まれた彼は、ゲオルク・フィリップ・フリードリヒ・フォン・ハルデンベルクという立派な本名をもつ。天才の多くがそうであるように、彼もまた28歳と…
『沈黙』(村上春樹著)より
村上春樹氏の短編集『レキシントンの幽霊』の中の『沈黙』という短編で、この言葉を見つけた。主人公の「僕」が、取引先の「大沢」という誠実で物静かな男に「これまで喧嘩をして人を殴ったことがあるか」という質問…
熊谷守一
〝画壇の仙人〟と呼ばれた画家、「モリ」こと熊谷守一の言葉である。「これ以上人が来てくれてはこまる」と言って文化勲章の内示を辞退するほど、モリカズの元にはよくよく人が集まってきたという。人だけでなく、鳥…
ノースロップ・フライ
カナダの文芸評論家、ノースロップ・フライの言葉だ。これまでノーマークだった彼はウィキペディアによると、「20世紀でもっとも影響力をもった文学理論家のひとり」だという。ウィリアム・ブレイクの詩を論じて一…
ウィリアム・アーネスト・ヘンリー
ネルソン・マンデラ大統領が27年間の投獄中に心の支えとしていたという詩『インビクタス』。不屈を意味するこの詩を書いた詩人、ウィリアム・アーネスト・ヘンリーの言葉だ。 ウィリアムは言う。 ――すべての神…
ベンジャミン・フランクリン
アメリカ合衆国建国の父のひとり、ベンジャミン・フランクリンの言葉だ。政治家、外交官、著述家、物理学者、気象学者と、さまざまな顔を持つのも、勤勉で探究心が旺盛だった証だろう。 ベンジャミン・フランクリン…
松尾芭蕉
弟子たちにもたびたび言っていたものと思われる。芭蕉の口癖だったらしい「夏炉冬扇の如し」。芭蕉が本当の芭蕉となったのは、晩年の10年ほどのことだという。『おくのほそ道』の旅に出て、名句が生まれたのもこの…
茂木健一郎
近代になって脳科学の研究は革新的な発展を遂げた。脳を知れば人間の言動原理は、ほぼわかるらしい。日本において脳科学という分野をポピュラーにしたのは、おそらくこの人ではないだろうか。脳のトリセツを真っ先に…
李白
唐の詩仙、李白の詩句である。漢詩『将進酒』の中のこの一句はとくに有名で、座右の銘にする人も多いらしい。儒教的な教示として引き合いに出されることもよくある。李白自身が「デキた人」でなかっただけに、共感を…