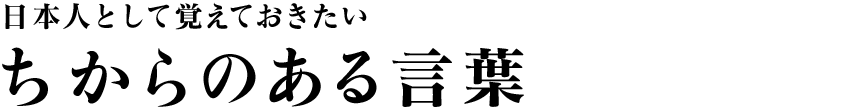いつの時代にも通用する、普遍的な言葉があります。
それぞれの時代を懸命に生き、一事をなした人たちの一言だからこそ、今もなお私たちの心を揺さぶり続ける言葉の数々。“心の栄養”として、活用してください。
Topics
吉川英治
『宮本武蔵』で知られる作家の吉川英治が、その著書の中で記した言葉である。武蔵の言との説もあるそうだが、実際は、吉川氏が好んで使っていたという。この言葉を座右の銘とする人も多いと聞く。人は一人では生きて…
葛飾北斎
これが格言?とお思いの方、あなどるなかれ。知っている人は知っているはず、かの北斎が好んで使ったこの「師造化」という落款と、その名に秘めた熱き誓いを。葛飾北斎、30代後半から50代前半にかけて名乗って…
エピクテートス
エピクテトスとも呼ぶらしい。紀元前一、二世紀ごろのローマの哲人である。かのソクラテスにも影響を与えたという。某新聞でこの言葉に出会い、あたためる時間の必要性も感じなかったので取り上げてみた。編集委員の…
ビアス
紀元前六世紀プリエーヌに生まれたギリシャ七賢人の一人、ビアスの言葉だ。プリエーヌが敵に包囲されたとき、市民がそれぞれ財宝をもって逃げようとする中、ビアスひとり、何ももたずにこう言い放ったという。ビアス…
『ぼのぼの』より
ふたたび登場、ラッコのぼのぼのちゃん。漫画家いがらしみきおが描く4コマ漫画『ぼのぼの』で、疲れた頭をときどきリフレッシュする。動物たちの日常の、ほのぼのとした会話は哲学的で、癒やされるのに考えさせられ…
アラン
以前にも紹介したことがある。「世界三大幸福論」を提唱した一人、フランスの哲学者、アランの言葉をもうひとつ紹介しよう。どの言葉も紹介したいくらいだが、そこは著書『幸福論』から幸福の真髄を読み取ってほしい…
ハンス・セリエ
ストレス学説を唱えたカナダの生物学者、ハンス・セリエの言葉である。彼は、ストレスとは「外部からもたらされる歪み、あるいは歪みの原因」だと定義し、そのことによるさまざまな反応は有害物質から身を守るための…
高梨沙羅
スキージャンプ女子の高梨沙羅選手の言葉である。某新聞のテレビCM紹介欄で、所属するクラレが高梨選手を応援するCMの次回作として取り上げていた。「高梨沙羅ちがい、を磨こう。」編である。最近のCMだから、…
『養生訓』より
江戸時代の儒学者兼医者・薬学者であった貝原益軒の『養生訓』より抜粋。益軒は現代のような飽食時代が到来することを予期していたのであろうか。「珍美の食に対するとも、八、九分にてやむべし。十分に飽き満るは後…
『失敗の本質』より
1984年に刊行された『失敗の本質』より抜粋した。日本軍の組織的敗因を分析した本書は発刊以来、版を重ね大ベストセラー本となっている。長所は短所の裏返しだということを、これでもかと知らしめているが、あま…