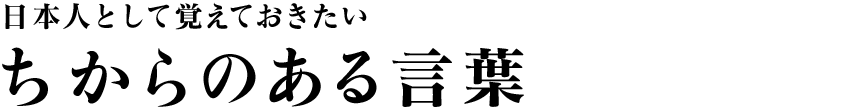いつの時代にも通用する、普遍的な言葉があります。
それぞれの時代を懸命に生き、一事をなした人たちの一言だからこそ、今もなお私たちの心を揺さぶり続ける言葉の数々。“心の栄養”として、活用してください。
Topics
『納棺夫日記』より
映画「おくりびと」の原点となった著書「納棺夫日記」の一節である。著者の青木新門氏自らの体験記でもあるがゆえか、主人公の納棺夫が出会う数々の死はリアリティをともない、まだ生きていた頃の温もりを伝えてくる…
スティーブ・ジョブズ
今やその存在は神格化され、記録に残る言動ひとつひとつが神の教えのごとく尊ばれるようになったスティーブ・ジョブズ。彼が残した数多くの功績の原点は、すべてこの言葉に集約されているといっていい。禅に深く親し…
『神曲』より
以前も紹介したダンテの『神曲』から抜粋した。後半「天国編」で、主人公ダンテがかつての恋人ベアトリーチェと再会し、光(天使)となった彼女から聞いた言葉である。禅の言葉「而今」。「いま、ここ」がそうである…
田居克人
「エル・ジャポン」などで編集長を歴任した、男性ファッション誌「マリ・クレール・スタイル・ムッシュ」の編集長、田居克人氏の言葉である。某新聞の「顔」のコーナーと言えば、察しも付くだろうか。先日、その欄で…
フランソワ・ド・ラ・ロシュフコー
以前にも紹介した、人間性悪説から生まれたロシュフコーの至言集の一文。どれもこれも、人間の愚かな部分に焦点をあてられているからか、隠れた腫瘍を発見されたかのようにドキリとする言葉が多い。すべてが当てはま…
『風姿花伝』より
「秘すれば花」でおなじみ、『風姿花伝』の中の一節である。『風姿花伝』は亡き父観阿弥の教えをもとに、世阿弥が記し残した能の理論書として広く知れているが、能のような芸事に限らず、生き方の指南書としても十分…
渡辺和子
ノートルダム清心学園理事長の渡辺和子さんの言葉である。著書『面倒だから、しよう』から抜粋した。昭和天皇の「雑草という名の草はない」という言葉にも通じる。渡辺さんがよく使う言葉に、「時間の使い方は、いの…
ベニー・グッドマン
〝スウィングの王様〟と呼ばれたスウィングジャズの立役者、ベニー・グッドマン。音楽史上、初めて黒人と白人を同じバンドで演奏させたことで知られるグッドマンらしい言葉だ。過去に縛られそうになったら、この言葉…
この一語は、浮山法遠という禅師の逸話として伝えられているものだ。法遠は、厳令枯淡な人物として知られていた葉県禅師の弟子なのだが、弟子になるまでの修行は、それはそれは人情のかけらもないほど容赦ない仕打ち…
アルベルト・アインシュタイン
ベロだし顔の写真で有名なアルベルト・アインシュタイン。相対性理論などを提唱した世紀の大天才は、誰もが天才であると豪語する。前回取り上げたポール・スミザー氏の言葉と同じような意味合いだが、アインシュタイ…