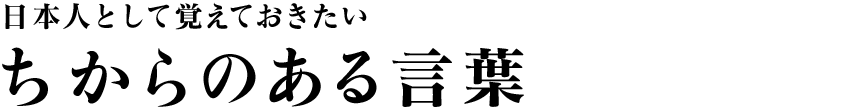いつの時代にも通用する、普遍的な言葉があります。
それぞれの時代を懸命に生き、一事をなした人たちの一言だからこそ、今もなお私たちの心を揺さぶり続ける言葉の数々。“心の栄養”として、活用してください。
Topics
『聖フランシスコの平和の祈り』より
世界一美しい祈りの言葉だと言われる、アッシジのフランチェスコ(聖フランシスコ)の平和の祈り。そのなかの一節である。マザー・テレサは毎朝この祈祷文を唱えていたという。鉄の女として知られるイギリス初の女性…
『願いに生きる』より
仏教詩人、坂村真民の講話をまとめた『願いに生きる』(致知出版)でこの言葉をみつけた。言い方は少しちがうが、最後の章の末尾にあった。運を呼び込む極意として、幸田露伴の「幸福三説」を解説した渡部昇一の著書…
『語りかける花』より
染色家の志村ふくみさんの著書『語りかける花』で、この言葉をみつけた。むかし、「平凡を非凡に」という題で京都新聞に掲載されたエッセイで、同じく染色家の宗広力三氏の昔語りにでてきた言葉だった。 宗広氏が新…
ボブ・ディラン
2016年にノーベル文学賞を受賞して話題になったボブ・ディラン。彼の代表作のひとつ『Blowin’inthewind(風に吹かれて)』を、今現在、思い出す人も多いだろう。リリースされた1963年といえ…
リンテック株式会社の格言より
目にしたことがある人も多いだろう、横顔のシルエットの中に名言がポツリ。粘着素材や特殊紙・フィルムなどを製造販売するリンテック株式会社の広告である。シンプルなだけに、小さい広告でもすぐ目に止まる。さらに…
ジェームズ・アレン
今でこそ当たり前に語られる「思いは形になる」という概念、おそらくこれは自己啓発書の原点とされる『原因と結果の法則』の著者、ジェームズ・アレンが自身の体験から導き出した法則にちがいない。デール・カーネギ…
『過秦論』より
前漢時代に活躍した政治家であり学者の賈誼(かぎ)が記した『過秦論』に、この言葉はある。中国春秋・戦国時代、6国を統治した始皇帝が築いた大国「秦」は、わずか15年で滅亡した。それに対する批判と教訓を賈誼…
志村ふくみ
染色家の志村ふくみさんの言葉である。随筆集『語りかける花』の中の「光の根」というエッセイにあった。染織に一生をささげ、植物の声をひとことも漏らすまいと耳をすませる志村さんだからこその言葉だろう。 直感…
上杉鷹山
広く知られたことわざである。出どころは江戸中期の米沢藩主、上杉鷹山。窮地に追いやられた米沢藩を立て直し、民衆や部下からの信頼も厚かった鷹山は、困難に立たされるたびに、こんな風にして自分も周りも奮い立た…
渋沢栄一
2年後の2024年、紙幣のデザインが一新される。その最高額1万円紙幣の顔は渋沢栄一。生涯にわたり500以上もの企業に携わった「日本資本主義の父」である。渋沢が『論語』を片手にソロバンを弾いていたのは周…