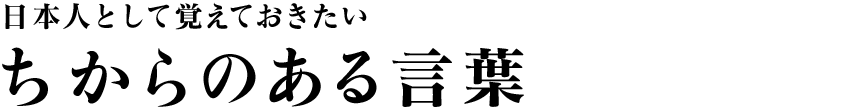いつの時代にも通用する、普遍的な言葉があります。
それぞれの時代を懸命に生き、一事をなした人たちの一言だからこそ、今もなお私たちの心を揺さぶり続ける言葉の数々。“心の栄養”として、活用してください。
Topics
ゲーテ
ドイツの偉大なる詩人といえばこの人、ゲーテ。正式な名をヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテという。詩人であり作家、科学者や政治家といったさまざまな顔をもつゲーテの、その類い希なる才能が遺した数々の作…
世阿弥
『風姿花伝』から、世阿弥の教えのひとつを紹介しよう。以前も別の教えを紹介したことがある。これは第七章、別紙口伝の中のひとつで、鬼人を演じるときの心得を説いている。つまり、怒れるときこそ、やわらかな心を…
古歌
だれが歌ったか、古の歌だそうだ。禅や仏教に精通する人は、一度は耳にしたことがあるはず。禅語にある「即今」とも通じる。生きるとはなにか。生命とはなんなのか。謎解きのように、今も昔も語られる「生きることの…
ウィリアム・ブレイク
イギリスのロマンティシズムを代表する詩人といえば、ウィリアム・ブレイク。有名な詩『無垢の予兆』の冒頭がこれだ。画家でもあった彼の挿絵つきの詩は、よりいっそうブレイクの世界観を表す。その世界観は禅的であ…
松浦静山
肥前国第9代平戸藩主、松浦清の言葉。正確に言えば、47歳で家督を息子に譲った後、松浦静山の名で執筆した随筆集『甲子夜話』の中の一節である。東北楽天ゴールデンイーグルスの名誉監督、野村克也氏の座右の銘と…
W・H・オーデン
アメリカに帰化したイギリスの詩人、W・H・オーデンの詩の一節である。村上春樹が翻訳した『恋しくて』の中の短篇「愛し合う二人に代わって」に出てくる。社会問題を扱い、「30年代詩人」としてブームを巻き起こ…
佐野洋子
ヨーコさんの登場である。辛口なトークが小気味よく、絵本はもとより、彼女のエッセイファンは多い。辛辣な言葉の中にも愛を感じさせるのは、彼女自身が愛の塊だからか…。そんなことを言ったら、あの世から石を投げ…
中田宏
以前にも紹介した、前横浜市長の中田宏氏の言葉をまたもうひとつ。著書『中田主義』には中田氏のフィロソフィーがぎっしり詰まっている。当たり前のことを当たり前として終わらせるのではなく、じっくりと考察し、自…
マザー・テレサ
ノーベル平和賞を受賞したマザー・テレサの言葉だ。生涯を救済活動にささげ、万人に尊厳ある死を与えたいと路上生活者たちの看取りの場として開設された「死を待つ人の家」には、マザーの精神に少しでも触れたいと、…
リディア・シモン
ルーマニアのマラソン選手でオリンピック銀メダリストのリディア・シモンの言葉である。村上春樹の著書『走ることについて語るときに僕の語ること』に書いてあった。彼女がマラソン中に繰り返して唱えている言葉だそ…