平らかなプラットホーム的書の「場」をつくりたい。
書家佐藤達也さん、内野直弥さん
2021.10.20

2014年に『Japanist』で取材をした10、20代の若者たちによる書のコレクティブ「僕らの書展」。リーダーの佐藤達也さん(写真左)が当時からの仲間とともに三人展「書・乳の友」を青山のギャラリーで開催しました。
取材から7年、佐藤さんの書への情熱は今も変わらず続いていますが、向き合う姿勢はちょっと変わったようです。出展作品には書以外に版画もあり、作者の内野直弥さん(写真右)は「ものづくり」が趣味だそうで、筆や小物、靴まで手作りするのだとか。
佐藤さんと内野さんのお二人に、書への思いや向き合う姿勢、今後の活動などをお聞きしました。
「僕らの書展」を終えて
 佐藤さんとは7年ぶりですね。今回の展覧会の「乳の友」というネーミングは、どういう意味があるのですか。
佐藤さんとは7年ぶりですね。今回の展覧会の「乳の友」というネーミングは、どういう意味があるのですか。
佐藤 これは僕たち3人のLINEのグループ名で、特に意味はないんです。ふだん連絡を取り合ったり、書のことや他愛もないことを語り合っている場として使っているLINEで、そういう肩の力の抜けた展覧会にしようと思ってこのネーミングにしました。
「僕らの書展」は昨年(2020年)解散されたそうですが、他のメンバーはどうされているのですか。
佐藤 みんな結婚したり、就職したり、それぞれですね。まったく書から離れている人もいれば、なんとなく続けている人もいる。その中でも僕たち3人は当時から気が合って、プライベートでも書に関しても今もずっと続いています。
もともと「僕らの書展」は10年という期限つきで始めたことなんですよ。2010年から20年を活動期間にするって最初に決めて、その10年の節目が去年。2020年12月の展覧会を最後にグループは解散しました。
なぜ10年と決めていたのですか。
佐藤 こういうのってきっと、だらだらやっていてもしょうがないんですよね。たとえば、スポーツ選手が若いうちに記録を残すというのも、だいたい30歳前くらいに勝負をかけてやるじゃないですか。それと同じで、僕らも「10年でどこまでできるか」ということを課題にしました。20歳から30歳にかけての貴重な10年間を徹底的に書にぶつけることで、絶対何かが変わる。作品に対する考え方も自分なりに構築されるはずだし、それは若い時期にしかできないですから。
その10年間が終わったから、それまでアルバイトで生活していた人が正社員になったり、結婚したりと、それを機転に仲間たちも変わっていったわけです。
 いつ終わるかわからないものに取り組むよりも、期限つきのほうが前向きに取り組みやすということもありますね。
いつ終わるかわからないものに取り組むよりも、期限つきのほうが前向きに取り組みやすということもありますね。
佐藤 団体というものは長く続くと、必ず旧態依然としたものになってしまうんです。僕たちはそれが嫌で「僕らの書展」を始めて、さらに10年間という期限を決めたんです。
昔と今の違い
その10年間、どれくらいのスパンで展覧会を開催していたのですか。
佐藤 基本的には2年おきにやっていましたが、トータルで9回の展覧会を企画しました。前回取材していただいた2014年は東京芸術劇場でしたよね。その後が2016年の秋頃かな。
内野 オーストリアのウィーンでやったんですよ。
 海外ですか。企画からすべてご自分たちで?
海外ですか。企画からすべてご自分たちで?
佐藤 はい。現地のギャラリーに直接交渉に行って。その帰国展を日本でもやろうということで、2017年の3月に銀座のギャラリーで開催しました。
内野 そこから1年おきです。展示をするペースが上がって、18年の11月に月島の倉庫でやって、20年の3月に上野根津のギャラリー。20年の12月に横浜で最後でした。
2014年の取材のとき、展覧会前はメンバー全員で合宿するとおっしゃっていましたが、それもずっと続けていたのですか。
佐藤 やっていました。同じ釜の飯を食うじゃないですけど、そうやって練り上げていくものだから、あれはやっぱり外せなかったです。合宿は絶対やるっていうのも、最初から決めていました。
活動スタイルはずっと変わらずですが、書に対する考え方は変わりましたか。
佐藤 たとえば2014年との比較だと、あの頃は「若さ」とか「新しさ」とか「突破力」みたいなことが重要だと思っていたんですけど、オーストリアに行って、「そういうことも、もうどうでもいいんじゃないか」って感じましたね。要するに、日本でやっているからそういう閉塞感を感じるわけで、外に出たらそんなことは関係なく、むしろ「自分たちがどういう出自で、こういう書ができて」っていうバックグラウンドとか歴史に興味がいくようになりました。
それまではそういう意識はなかったのですか。
佐藤 ありました。ありましたけど、メインはやっぱり新しいものとか突破力ということでしたね。でも「新しいものなんかそう簡単にはできないな」って、うすうす気づき始めたのがその頃です。
 オーストリアに行って、外の世界を見たからということもありますか。
オーストリアに行って、外の世界を見たからということもありますか。
佐藤 そうですね。作品の表現の幅としては、2014年の取材の「僕らの書展」のときより明らかに狭まっているんですよ、自分の中で。あの頃は、中原中也の詩を抽象的に書いたり、体当たり的なでっかい一文字を書いたりということをしたんですけど、だんだん自分の中で表現の幅を狭める、絞り込んで狙っていく、ということが出来るようになりました。あの頃は、全部できることが偉いと思っていましたから。最近は「かたちの意味をあつかう」ことに主題を置いて、意味を書こうと試みています。
ということは、「僕らの書展」の10年間は、佐藤さんにとって自分を見つめるための期間でもあったということですね。
佐藤 そうです。やりたいことは全部やる、その中から絞り込んでいくという10年でした。
「僕らの書展」の頃というのは、やっぱり頑張るんですよ。「やるぞ!」って感じで。喧嘩売られたら、絶対勝たなきゃいけないみたいな。だから勉強もしたし、作品も一生懸命書いた。10年間必死だったから、終わった後は燃え尽き症候群のような状態にもなりました。でも僕は書が好きだから、毎日書き続けていたし、発表の場は欲しいと思っていました。だから今回の「乳の友」の展示はもっと肩の力を抜いて、日頃やっている仕事とか、興味のあるものを集めようと思って、それで内野は版画も出したんです。
内野さんは書以外にも「ものづくり」がお好きだそうですが、版画はいつからやっていらっしゃるのですか。
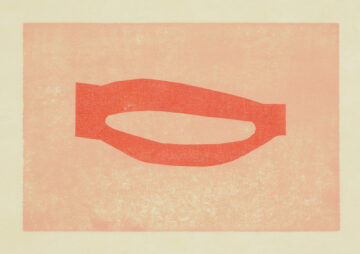 内野 書と同じくらいだから、10年以上前からですね。今回の「乳の友」の趣旨がラフなスタイルというので、じゃあこれまで展示する機会がなかった版画も出してみようかなと思って出品しました。
内野 書と同じくらいだから、10年以上前からですね。今回の「乳の友」の趣旨がラフなスタイルというので、じゃあこれまで展示する機会がなかった版画も出してみようかなと思って出品しました。
今まで「僕らの書展」を10年やってきて、そのときは自由な感性や若い感性によって新たな局面を模索するという標榜があったし、その中で活動しているときはすごく自由にやらせてもらっているから「気合入れてしっかりやっていこうぜ」っていうようなところがあったんですけど、終わってみてわかったのは、その標榜に結構縛られているところがあったなと。自由だと思っていたことが、逆にその自由に縛られていた、自由じゃなきゃいけないみたいなところがあって、そんな風にみんなで目標を掲げて同じところに進まなきゃいけないってことに結果的にはちょっと息苦しさも感じていたんですよね。だから今回3人展をやるにあたっては、そういうものが全部取っ払われました。表現者として表現したものを出すには何を出してもいいんじゃないかと。
自分たちで作ったルールに縛られていたんですね。
内野 だと思います。僕らの書展にいた自分が自分を縛りつけていた感覚が全部なくなると、「わあ、めちゃくちゃラク」って、今までにないほど伸びやかに展示ができました。
書がつないだもの
版画の他にもいろいろ作っているそうで、靴も手作りしているとか。
内野 はい、今は2足目を作っています。靴を作るための道具から作りました。達也さんに作っているものもありますよ。墨を入れるケースですけど。
 佐藤 革のポシェットね(笑)。僕は古い墨などの文房四宝を集めるのが好きで、墨もふだん使いのものと、いわゆる「古墨」といわれるものがたくさんあるんですけど、その一つのかなり古い丸い形の「百子圖」の墨には箱がなくてどうしようと思っていたら、内野が作るよって言ってくれたんです。
佐藤 革のポシェットね(笑)。僕は古い墨などの文房四宝を集めるのが好きで、墨もふだん使いのものと、いわゆる「古墨」といわれるものがたくさんあるんですけど、その一つのかなり古い丸い形の「百子圖」の墨には箱がなくてどうしようと思っていたら、内野が作るよって言ってくれたんです。
なんでも作れるんですね。しかも作るための道具から作るとは驚きです。手で作り上げるということがお好きなんですね。書もその延長線にあるのですか。
内野 というか、ものづくりが好きになったのは書がきっかけなんですよ。「書」の良し悪しというのがあんまり面白くなくて、それよりも、物事の構造がわかるのが楽しい。どうやったらこれができるんだろうって研究するのが好きなんです。靴もそうですけど、ものを作るときに、その作る方法だけじゃなくて、それ以外の道具を作ることにも興味がある。今、手元にあるものだと、革包丁の柄の部分は柿の木を使って手作りしています。
作る過程が好きで、その成果物として、たとえば書であったり版画であったり、靴だったり……と形になっていくんだと思います。だから、それを発表する機会がなくても全然いいんです。
ちなみに筆も作るのですか。
内野 作りますけど、筆はやっぱり職人さんには敵わないですね。ただ、こういうのって構造さえわかれば誰でもできると思いますよ。
そういえば僕が靴を作るきっかけになったのは、オーストリアでの展示会のときなんです。達也さんにつき合ってもらって、一緒に靴屋さんに行ってもらったんですよね。
佐藤 そうそう。そこで内野はいい靴を買ったんです。結構いい値段の革靴を。それを履いちゃうと結局潰れちゃうし、こういうのも日本で欲しいなって思って、でもやっぱり買えないから、だったら作ろうっていう彼独特の発想だったみたいです。
 内野 書をやってるとお金もかかるし、高価なものって買えないですからね。
内野 書をやってるとお金もかかるし、高価なものって買えないですからね。
でも、材料も高いですよね。
佐藤 結局、そっちのが高くつくみたいです(笑)。
内野 はい。道具が高いなら、じゃあ道具も作ろうって。で、道具も作るようになったわけです。
お二人の関係はとても自然体でいいですね。出会ったのはいつですか。
佐藤 これがまた微妙で、同じ宇都宮高校なんですけど、僕が卒業した後に内野が入ったんですよ。
内野 僕は佐藤さんの3つ年下です。高校1年のときに未経験だったんですけど書道部に入ったんです。で、大学1年の佐藤達也っていう先輩が来るっていう話があって、それが出会いですね。
2014年の取材でも、佐藤さんは栃木県内の書道部の中でもかなり有名人だったという話がありましたね。その界隈ではかなり有名だと。取材時ご一緒だった伊藤聡美さんも佐藤さんに魅了されて書の道に入ったとおっしゃっていました。
佐藤 彼女はそうだったみたいでしたけど、内野は僕の方が気に入って、ずっと引きずり回しているんです。内野が「僕らの書展」に入った次の月にはもう静岡に一緒に連れて行きましたし。2人の師匠の柿下木冠先生とも、僕は大学生になってからお会いしたんですけど、内野は高校の頃から可愛いがっていただいていました。
「乳の友」のもう一人のメンバーの小久保充基さんは、佐藤さんの教え子だそうですね。
佐藤 そうです。僕が高校の教師になった初任のときだから、2013年頃ですか。取材のあった2014年当時、小久保君は高校2年生で、お父さんと2人で展覧会を見にきてくれたんです。そのときにちょっと楽しそうだと思ってくれて、2017頃に「僕らの書展」に入ったんですよ。もともと彼の進路は理系だったんですけどね。急に文系に変更して、二松学舎大学の中国文学科に進みました。
高校では書道部に入ってはいたんですが、最初は本格的にやるつもりはなかったみたいです。「僕らの書展」を見てから書が楽しそうに感じたみたいです。今は宇都宮の多氣不動尊というお寺に浄書として勤めていますよ。
 すごい方向転換ですね。どういう経緯でお寺で働くことになったのですか。
すごい方向転換ですね。どういう経緯でお寺で働くことになったのですか。
佐藤 本当は、彼は東京で書や美術の研究をしたかったんです。大学時代に美学のすばらしい先生に出会って、4年生のときに東京芸大の大学院を受けたんですけど落ちちゃって。それで、バーテンダーなどをしながら勉強を続けてもう一回受けようと思っていたみたいです。でも、コロナ禍でバーテンダーの仕事もなくなり、栃木に戻っても実家に帰るのは嫌だからと言うことで、鹿沼の僕の知人がご好意で古民家を貸してくれて、彼はそこでぬか漬けを作ったり、作品を書いたりして過ごしていました。そうこうしているうちに、ありがたいことにお寺での仕事も決まり、アパートも借りられるようになった。自粛中、古民家には僕と内野もたまに遊びに行って、3人でワイワイやってました(笑)。
そういえば佐藤さんはニューヨークに行かれたそうですが、それも3人で?
佐藤 いいえ、小久保君と2人です。コロナが蔓延する前の夏に、約2ヶ月くらい。僕はビビリなんで、一人で行けなかったから小久保君についてきてもらったんです(笑)。
内野 充基って、結構、怖いもの知らずで、知らない人にでも「イェーイ」って話しかけちゃうような人なんですよ。知らない人のところに行ってどんどん話しかけるよね。
佐藤 そうそう。すごかったのは、向こうで彼は持ち金がなくなって、「ちょっと作品売ってくる」ってセントラルパークに売りに行ったんです。で、「売れたの?」って聞いたら、「タバコを一本もらった」とか、そんなこと言ってましたね(笑)。そういうタイプです。
たくましいですね(笑)。ニューヨークにはどういう理由で行かれたのですか。
佐藤 実は2020年に「僕らの書展」をニューヨークでやりたかったんですよ。3月に上野の根津でやって、夏にニューヨーク、12月に横浜。それが最高の終わり方かなって考えていたんです。そのギャラリーを探しに。つてはなかったんですけど、行ってみりゃどうにかなるだろうって感じで行きました。ウィーンのときもそうでした。
 ギャラリーは見つかったのですか。
ギャラリーは見つかったのですか。
佐藤 はい。国連の迎賓館みたいなところで、国連に来た人が自由に見られるギャラリー、そこに決まっていました。それともう一つ、難民支援の施設があるビルのギャラリーで僕の個展をやる予定でした。その2本を同じ時期にやる予定だったんですけど、それもコロナで全部中止です。
残念でしたね。今後、その展覧会の予定はあるのですか。
佐藤 「僕らの書展」はどうかはわからないですけど、僕自身の個展はニューヨークでやりたいなと思っています。
展覧会は中止になりましたが、ニューヨークで知り合った書の若手研究者や日本美術のキュレーターたちとの交流が始まったのは大きな収穫でしたね。それもあって、ニューヨークで個展をやってみたいという気持ちがますます強くなっています。
今年の夏に1点だけ作品を送ったんですよ。「PEACE展」という終戦記念日前後にやる芸術家たちの草の根運動的な展覧会に出品するために。でも、コロナだから入場制限付きだったみたいで。もっと状況がよくなったら向こうで書をやってみたいです。
それぞれの書の道
ところで、お二人は1日のうち、書にかける時間はどれくらいなんですか。
佐藤 僕はわりと真面目なんで、例えば休みの日は午前中は墨を磨って、午後はずっと臨書(書の古典を手本に習うこと)をしています。
内野 僕はそんなにやらないですね。ここ2年くらい、手習いはしますけど、他のことばっかりやっています。柿下先生のお稽古に持って行く書を書くのに半日。それを2日間ぐらいで書いて、その他は靴を作ったり、趣味というか遊びに時間を使っています。楽しいから。
佐藤 僕は時間があればずーっと書いてますね。寝室も作業場も、書のもので埋まっています。僕は臨書が好きなんですよ。だから、ずっと書いていても全然平気。
飽きることはないですか。
佐藤 ないです。臨書はずっとできる。「僕らの書展」のときもそうでしたけど、僕は作品を完成させるのは早いんですよ。合宿の2〜4日間で書き上げると決めて、計画して絶対仕上げる。それも普段からトレーニングのように臨書をやっているからできる。書も瞬発力が必要ですからね。
それと、僕は練習のときも本番と同じか、あるいは本番より良い道具で絶対言い訳できないようにして臨書をしています。本番だと思って練習するのは、ずっと昔から変わっていません。常に真剣勝負です。
師匠の柿下木冠先生ですが、その教え方は「何も言わずに待つ」。佐藤さんはじめお弟子さんたちはかなりリスペクトされているそうですね。お二人は教員ということで、教える立場として、柿下先生の影響はありますか。
佐藤 僕は柿下先生の姿勢を守っていきたいと思っています。今も月に2回、先生のご指導を受けていますが、柿下先生がいなければ「僕らの書展」のような自由な活動はできなかったですからね。普通は口を出されたり、やるなって言われたりするんですよ。仲間内でもいろんな先生に付いている人がいて、それが理由で辞めていった人が大半です。最初は人数も結構多かったけれど、最後は6人にまで減りました。
僕たちは柿下先生が何も言わないでいてくださるので、そこに思いっきり甘えちゃったという感じです(笑)。
 その自由度が幅を広げてくれたりしますよね。
その自由度が幅を広げてくれたりしますよね。
佐藤 そうなんです。でも自由にやらせてくれるけれど、本当に道を外れそうになったとき、例えば作品でも大きくズレそうになったときだけ、チョンと戻してくれる。それって一番むずかしい導き方ですよね。
柿下先生の魅力は、何も言わないで待っていてくださる、必要なときはアドバイスをくださる、それと、もう一つ。相手の立場に立って作品を選ぶ、ということです。例えば僕の作品なら、「佐藤達也は何をやりたいのかを見極めてから作品のアドバイスをしたい」っていう方法です。おそらく書の世界では「これはいい」「これは悪い」という基準があって、それで区分する方が楽なんですが、そうじゃなくて「やりたいことはなんだろう」と相手の立場に立って作品を選ぼうとする。それが柿下先生の選び方です。相手の立場に立って考える、という姿勢は守っていきたいですね。
未来設計図
今お二人は高校の非常勤講師として書道を教えていらっしゃいますよね。作家一本に絞り込むことは考えていますか。
佐藤 僕は考えています。最終的に、書のプラットホームみたいな場所を作りたいんですよ。書が学べたり、書に関係する本がすべて揃っていたり、作品も見られるし、書のことを語り合ったりと、そういうことができる場を作りたい。というのが、今、そしてこれからの目標です。
今回の「乳の友」は、コロナのこともあって来場者数は2014年のときに比べると10分の1くらいだったんですが、来てくれた人がみんな長居してくれたんですよね。あまり人が歩いていないこともあって、ふらっと入るというより、SNSなどで知った人がわざわざ来てくれて、書について話したり、じっくり観賞してくれた。そういうのが嬉しいですよね。
昔は作家になりたいと思っていたし、今もなりたいと思っているけれど、それ以上に、そういうサロン的な場を作りたい。そこで自分も楽しんで書をしたいなと思います。
 内野 僕は書はもちろん好きですけど、書をきっかけにして知識や技術を知りたいと思うようになりました。達也さんみたいに前進するとか、新しいものをというよりは、下に掘って行く。ゼロ地点から上へ進んでいくような動きではなく、どういう構造なのかとか、どういう仕組みなのか、どういう技術なのかと、ゼロ地点から下側へ深く堀り下げていきたいです。だから正直にいうと、一度、一般職に就きたいと思っています。なんでも知りたい、聞きたいタイプなので、今までいた環境がどういうものだったのかということを確認するためにも、一般企業に入って世の中の動きを見てみたいです。
内野 僕は書はもちろん好きですけど、書をきっかけにして知識や技術を知りたいと思うようになりました。達也さんみたいに前進するとか、新しいものをというよりは、下に掘って行く。ゼロ地点から上へ進んでいくような動きではなく、どういう構造なのかとか、どういう仕組みなのか、どういう技術なのかと、ゼロ地点から下側へ深く堀り下げていきたいです。だから正直にいうと、一度、一般職に就きたいと思っています。なんでも知りたい、聞きたいタイプなので、今までいた環境がどういうものだったのかということを確認するためにも、一般企業に入って世の中の動きを見てみたいです。
では、今後の活動の予定を教えてください。
佐藤 「書の入門書」を作ろうとして動いています。さらっと軽く読めて、書を知れる本。美術でも入門書とかあるじゃないですか。バロック、ゴシックとかを簡単にまとめたもの。ああいう感じの本です。今ある書の本って、例えば、書のテクニックを教えるハウツー本や、高校書道の教科書くらいのやや専門的な書道の本しかないんです。とっつきにくいし、予備知識がないと理解しにくい。僕らの場合は、膨大な専門書を読んで、断片的な知識を組み合わせて、戦後の書道史を自分の中で組み立てて編んでいくしかなかった。だから、それが一発でわかる入門書を作ろうと思って、友人の書の学芸員と東洋美術史の研究員と僕の3人で進めています。具体的には、明治以降の書の歴史や変化、運動などを客観的かつ視覚的にまとめたもの。ぱっと見て「なるほど、書ってこういう風になってるんだ」とわかる本です。
というのも、海外で現地の人に「これも書なんですか。書ってこういうものじゃないんですか」って見せられたのが、なんだかよくわからないアート的な「書」で、ショックだったんですよ。だから、自分が自分の出自をちゃんとを知って、書をやっている以上、「書」というものを自分なりに正しく知っておかないと、変なものが世の中に広がっちゃうと思ったんです。
内野 着物の着付けとか、舞踊なんかもそうですよね。「え? これ着物?」っていうようなインチキ臭いものがいっぱい出回ってるし、舞踊を見せてもらっても、まったく変な踊りで「え? 何この踊り」ってびっくりします。変な書でも、「わー! ジャパニーズカルチャー」って喜ばれるのは、ちょっとね。それを日本って言ってる時点で、間違った伝わり方をしてるなって思います。
佐藤 それが国内でも起きてる今だから。そういう意味でも「入門書」は、「わたしがやっている書というのはこういうものなんだ」と知れるだけで、その人自身がちょっと深まりますし、自分がやっていることにも説明がつく。だから入門書を作ることは、そういうきっかけ作りでもあるわけです。
サロン的な書の「場」。そのための第一歩になる「書の入門書」。面白そうですね、ぜひ実現してほしいです。
佐藤 ありがとうございます。最後にお知らせですが、延期になってしまった鹿沼での「書・乳の友」栃木展を12月8日(水)から12日(日)まで鹿沼市文化活動交流館にて開催します。それと、去年からYouTube「僕らの書展」チャンネルを始めたので、よかったら見てください。
(写真上から:「書・乳の友」東京展 会場風景 左から内野・小久保・佐藤、「僕らの書展」公開制作風景(2020年)、オーストリア・ウィーン展ポスター、佐藤作品「花」、内野版画作品「(無題)」、内野作の革の墨箱と佐藤の蒐集する墨、内野作の靴・道具など、「僕らの書展2020FIN」会場風景①、佐藤作品「ふたつのしあわせ」、柿下木冠師と「僕らの書展」メンバー、内野作品「衆」、最下「僕らの書展2020FIN」会場風景②)
(取材・文/神谷真理子)
Information
【僕らの書展】
HP:https://www.bokuranoshoten.com/upcoming
YouTubeチャンネル:
https://www.youtube.com/channel/UCm045EutmW-8yrHEsBhuHcQ















