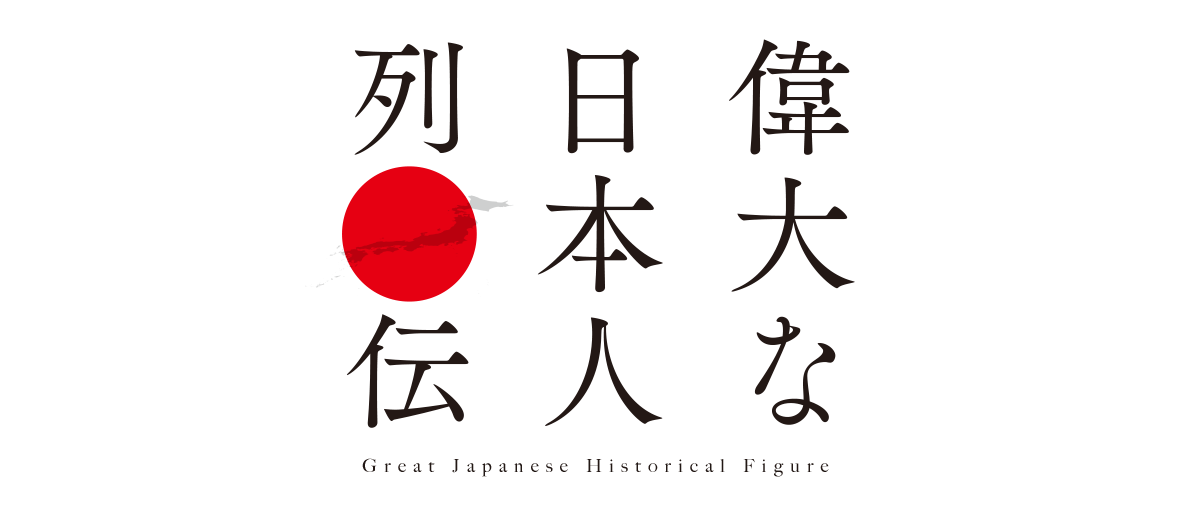日本型経営の根本をつくる
会社は私物にあらず

2024年度、日本の最高額紙幣の肖像が渋沢栄一になる。聖徳太子や福澤諭吉と比べると、なんとなくありがたみが減る感があるが、「日本資本主義の父」が最高額紙幣の肖像画として使われるのは、なにかと理にかなっている気がする。茫洋とした顔が親しみやすくもあり……。
明治維新の後、未曾有の内憂外患にさらされていたおり、日本は多くの傑物に恵まれた。政治家に限らず、軍人にも官僚にも経済人にも大人物が現れた。
渋沢栄一は、時代と人物との関係を次のように述べている。
「明治維新のように社会の動揺が激しい時期は、風雲に乗ずる機会が多くなるので、だれもがそれぞれの道を自由に進むことができる。しかし、社会の秩序が確立され天下泰平となれば、社会に同化する人物だけが世間になじみ、いわゆる変人は社会秩序を乱すため世間から排除される」と。
なるほど、当時個性的な人物がたくさん現れたのは、波乱激動の時代だったからなのか。
なかでも渋沢栄一の圧倒的な功績はどうだ。第一国立銀行をはじめ、東京瓦斯、東京海上火災保険、王子製紙(現王子製紙・日本製紙)、田園都市(現東急電鉄)、秩父セメント(現太平洋セメント)、帝国ホテル、秩父鉄道、京阪電気鉄道、東京証券取引所、キリンビール、サッポロビール、東洋紡績など500を超える会社の設立や経営に参画したと聞けば、驚かずにはいられない。
ただ、たくさんの会社を興したというだけであれば、渋沢のほかにもいるかもしれない。渋沢の真骨頂は、まったく独自の経営観をもっていたことだ。つまり、徹頭徹尾、会社を社会の公器とみなしていたということ。だから、自分が興した会社であっても自分のものとは考えなかった。経営が順調に進むのを見定めると、自分の持ち株を売却し、その資金を次の起業に充当させた。まるで自分の人生の持ち時間と競い合っているかのように、猛烈な勢いで会社を設立し続けたのである。
かのドラッカーは、渋沢を次のように評している。
「私は、経営の『社会的責任』について論じた歴史的人物のなかで、かの偉大な人物の一人である渋沢栄一の右に出るものを知らない。彼は世界のだれよりも早く、経営の本質は〝責任〟にほかならないということを見抜いていた」
現在でもドラッカーを信奉する日本人経営者は多いが、むしろ渋沢の経営観を学ぶべきではないか。
血気盛んな青年時代
渋沢は1840(天保11)年、現埼玉県深谷市に生まれた。5歳の頃から父に『三字経』や『大学』『中庸』『論語』などの手ほどきをうけ、7歳のときには従兄の尾高惇忠のもとに通い、四書五経や『日本外史』を学んだ。さらに剣術は、大川平兵衛より神道無念流を学んだ。
その後、北辰一刀流の千葉道場に入門し、剣術修業のかたわら、勤皇の志士たちと交友を結ぶ。その影響からか、1863(文久3)年、郷里で決起した後、横浜を焼き討ちにし、長州と結んで幕府を倒すという計画を企てる。
しかし、その計画は惇忠の弟・長七郎に諫められ、断念する。
渋沢の倒幕計画は幕府に知られることになり、父より勘当を受けたという体裁をとって京都へ移り、一橋家に仕えることになる。
その後、出世した渋沢は、慶喜が第15代将軍に就任したのに伴い幕臣となり、1860(慶応3)年、パリで行われる万国博覧会に将軍の名代として出席する徳川昭武の随員としてフランスへと渡航する。
このときのフランス体験は、渋沢に多くのものをもたらした。彼はその留学で学んだこととして、以下の3つをあげている。
●国家の発展はその国の経済力にあり、経済力を高めるには実業を伸ばす以外にない。
●事業の発展には資本と人材を結びつける株式会社がもっとも適している(※渋沢は当時、株式会社を合本組織と名づけていた)。
●ヨーロッパには官尊民卑の弊風がなく、日本も国家の繁栄を図るには、この弊風を打破せねばならない。
つまり、フランスでの体験をもとに、渋沢はさまざまな分野で事業を興すことが経済力を富ませることになり、ひいては国家の隆盛につながるということに気づくのである。そして、そのためにこそ自分の存在価値があるのだと。
以後、渋沢の軸はブレることはなかった。明治2年、民部省(2年後に大蔵省に統合)租税正に就任すると、租税の金納化を主張する。それまで税は年貢米によって納められていたが、現金による納税は大久保利通も主張していたことであった。この政策には、農民をはじめ、それまでの士族階級など多くの国民が反対したが、近代国家建設に欠かせないことであった。
渋沢の卓越しているところは、ひとつの政策が実行されるにともなって発生する社会の需要に、事業をもって応えようとしていた点だ。たとえば、現金による納税が義務化されれば、農産物などの生産物を市場に運んで現金化する必要がある。その際、交通インフラや保険制度の整備が必要となる。渋沢はそういった課題に対し誠実に対応し、資本と人材を投入しながら事業基盤を築いたのである。
明治6年、大蔵省を辞す決意を固める。今でこそ役人を辞して実業家になったことはそれほど奇異なこととは映らないが、徳川家光以来、朱子学が浸透した江戸の社会は、士農工商の身分制度を象徴するように、商人は賤しい身分だと思われていた。官僚を辞めて自ら商業の世界に足を踏み入れた渋沢の選択は、周囲を驚かせるにじゅうぶんだった。
類まれな人物鑑識
渋沢は『経営論語』という本を著している。論語のなかの言葉を抜き出し、渋沢流の解説を加えている書物だ。
それを読むと、「論語読みの論語知らず」にならないよう戒めていたことがわかる。「論語は明治前、支配層にのみ読まれ、本質から離れて取るに足りないような章句を研究する弊害に陥っていた」とも断じている。実践をともなわない机上の学問で終わってはいけない、あるいは為政者に都合のいい解釈ばかりしてはいけないと肝に銘じ、知行合一を旨としていたからこそ、あれだけの偉業を成し遂げたのであろう。
この書物のもうひとつの楽しみは、渋沢の優れた人物鑑識である。渋沢と同時代の偉人たちがものの見事に喝破されている。ふだん、歴史書でしか知り得ない偉人たちの体温や吐息までが伝わってくるようで、あまりに面白い。少々長くなるが、いくつか抜粋して紹介したい。
まずは、維新三傑に関するくだりだ。論語の「君子は器ならず」をひき、リーダーたる者、一技、一芸があるだけではいけないと諌めている。
「私は大久保公の日常を見るたびに、『器ならず』とは大久保公のごとき人を言うのであろうと思っていた。たいていの人は、いかに識見が卓抜であるという評判があっても、その心中のおおよそは、はたからうかがい知ることができるものだ。しかし、大久保公に至っては、どこが公の真相であるか、何を胸底に蔵しているのか、まったく測ることのできない人であった」
大久保には嫌われたが自分も厭な人だと思っていたと心中を明かしている点は、じつにあけすけだ。しかも、好き嫌いとは別に、人物の大きさを素直に認めているところがおもしろい。
「西郷隆盛公は、これもなかなか達識の偉い方で、器ならざる人に相違ないが、ひとことで言えば、とても親切で同情心が深く、どうすれば他人の利益になるかとそのことばかりに気を使っていたように思う。はたから見たところでは、公が賢い達識の人であるか鈍い愚かな人であるか、はっきりわからなかったものである。ここが西郷公と大久保公と違ったところで、西郷公は他人に馬鹿にされても馬鹿にされたと気づかず、そのかわり他人にほめられても嬉しいとも思わず、喜ぶこともなく、それに気づかないように見えた。とても同情心の深い、親切な御仁で、器ならざると同時に、また将に将たる君子の趣があった」とその厚い人間性を見抜いているが、同時に、「西南戦争の発端も、結局、西郷公が部下に対してあまりに仁愛に過ぎたからである」と書いている。論語で重要とされる「仁」や「愛」であっても、〝過ぎたるはなお及ばざるがごとし〟と結んでいるところがいかにも冷静だ。
後に、相馬藩の興国安民法の廃止に伴う争議の際も、相馬藩から相談を受けた西郷はその法を維持するよう唱えるが、渋沢にこう諭されている。
「いやしくも一国を双肩に担い、国政の大任にあたる参議の御身をもって、国家の小局部である相馬一藩の興国安民法のためには奔走されるが、一国の興国安民法をいかにすべきかについてのご賢慮がないのは、近頃もってその意を得ぬ次第、本末転倒もはなはだしきものである」
西郷は黙ってすごすごと引き下がったというが、誰に対しても率直に物言う渋沢の性格がよく表れている。
木戸孝允についてはこう述べている。
「木戸公は大久保公や西郷公よりも文学の趣味が深く、かつすべて考えたり行動したりするところが組織的であった。しかし器ならざる点においては、大久保・西郷の二傑と異なるところがなく、凡庸の器に非ざることを示すに足る大きな趣があった」
三傑に比べると、あの勝海舟も色あせて映ったようだ。
「勝海舟伯も達識の方で、凡庸の器でなかったことは確かであるが、大久保・西郷・木戸の三傑に比べれば、よほど器に近いところがあって、器ならずとまではいかなかったように思われる」
伊藤博文は議論に長け、なにごとも自分が一番ではないと気が済まない人だと断定しているが、明治憲法制定の功績については、最大限の称賛を与えている。
大隈重信については、他人の言を聞くよりも、他人に自分の言を聞かせるタイプで、いつも楽観的。どんなに相手に批判されようが、「議論は国家を富ます」と考え、鷹揚であったと書いている。反対に山県有朋や西郷従道は他人の意見を聞くのみで寡黙であったと書いている。
なにごとも知行合一を旨とする渋沢は、同時代の偉人たちの言動から、自身の行動規範をつくることも怠らなかった。曰く、「事に対しては井上候、人に対しては大隈候というのが私の本領」。
ものの見方が悲観的で人の欠点を厳しく指摘する癖のある井上馨となにごとも豪放磊落な大隈重信の良いところをミックスし、活かそうという姿勢は、まさに学びの人である。
金の本質をとらえる
渋沢は、「日本資本主義の父」と呼ばれているが、「資本家」あるいは「財閥の長」とはならなかった。その気になれば、三井高福、岩崎弥太郎、安田善次郎、住友友純、古河市兵衛、大倉喜八郎などのように財閥の創始者となれたはずだ。しかし、そういうことには一向に興味が湧かなかったようである。
また、事業にとどまらず、教育にも力を入れ、東京女学館、日本女子大を援助して校長になった他、東京帝国大学、早稲田大学など40に近い男女大学に援助を行っている。
また、当時は商人に高等教育はいらないという考え方が支配的だったが、商業教育にも力を入れ商法講習所(現一橋大学)、大倉商業学校(現東京経済大学)の設立に協力したほか、二松學舍(現二松學舍大学)の舎長に就任した。
金は、いつの時代も人に大きな作用を及ぼす。およそ、この世に生きている人で金の呪縛から完全に解放されている人は皆無に近いと思うが、渋沢は金の本質をかなりの正確さで捉えていたと思えてならない。渋沢の名言を羅列するだけでもその片鱗がうかがえるはずだ。
「真性の利殖は仁義道徳に基づかなければ決して永続するものではない」「人は自ら富まなければ、広く民に施してよく衆を救うわけにはいかない」
「楯に両面があるように、弊と利は表裏一体だ」
「悪銭身につかず」「盛って入るものは盛って出ず」……。
なぜ、渋沢は金の本質を見抜くことができたのだろう。そのヒントのひとつは、論語のこの言葉だ。
「奢なれば則ち不遜なり、倹なれば則ち固なり」(述而篇)
金を得て傲岸不遜になることは論外。かといって倹約すればいいというものでもない。金は使い方によって世の中に貢献することができ、自分も愉しい人生をおくることができる。
1931(昭和6)年、91歳で没するまで、渋沢はその信念を通した。明治神宮を現在の代々木に造営する事業に多大な貢献をしたことは案外知られていないようだ。また、渋沢は1926年と1927年のノーベル平和賞の候補になっている。
本サイトの髙久の連載記事
髙久の電子書籍