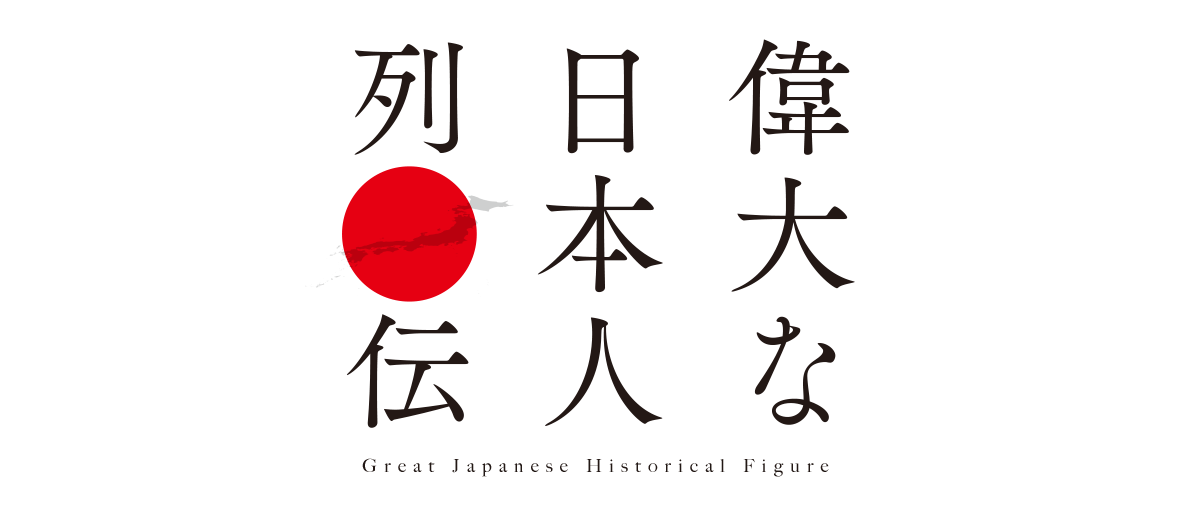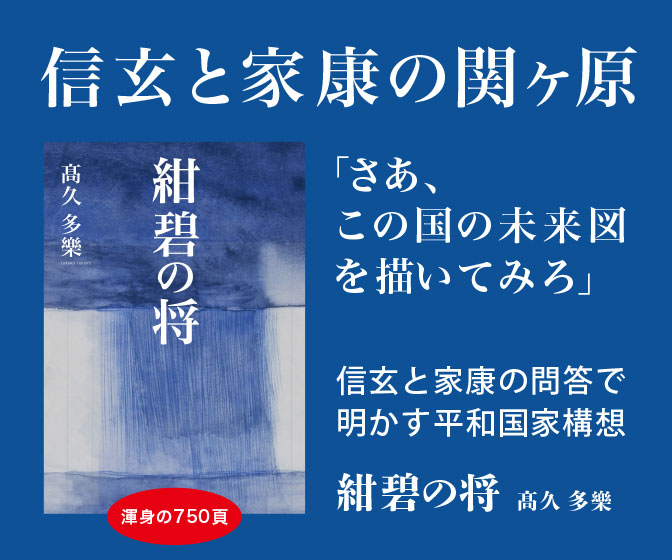神と鬼の視点をもつ異才
日本史々上、信長ほど日本人離れした人物はいない。なにごとにおいても周りとの調和を重視する日本人独特の情緒は、ほとんど見られない。非情に徹し、合理的な判断と一片のためらいもない実行力は、神業か悪魔の申し子かと思わせるほど。それでいて、異様なほどプライドが高いのに自分の考えに固執しない。いいと思えば、積極的に取り入れる柔軟さをもつ。必要とあらば、卑屈なまでにへりくだることだってできる。ある意味で、武士にあるまじきタイプといえる。
織田信長は、知れば知るほど類型化することができない。織田信長的という人物がほかに存在しないのだ。織田信長のような人物は織田信長だけ。孤高の人である。
信長の変革力
信長によって変革を遂げたことがいくつもある。たとえば、
●いつでも戦えるプロの兵団を組織する
●規制を撤廃し、商業振興を図る
●宗教兵力を無力化する
●ヨーロッパの科学技術や文化を積極的に導入する
●形式的慣習やしがらみを打破する
などがあげられる。詳しくは後に述べるとして、まずは信長の生い立ちを追ってみよう。
信長は1534(天文3)年、織田信秀の三男として生まれた。生後すぐ両親と離れ、傳役(教育係)平手政秀らとともに那古野城に居住する。
生まれた時代は陰惨を極めていた。天文年間(1532〜54)は、日本史上、最も人心が荒れた時代だ。骨肉相食む争いが各地で繰り広げられた。
しかしそんな時代だからこそ、信長の長所が失われなかったともいえるだろう。江戸時代のような安定した社会であれば、信長の個性はすべからく短所ととられ、潰された可能性が高い。〝なんでもあり〟の世の中が、信長のなにものにもとらわれない自由な気風を助け、その才能を開花させたといっていい。
後に天下を平定した徳川家康は、治世の根本を儒学におき、窮屈ではあっても安定した社会をつくろうとしたが、信長は儒学の教えの対極にあるような人物だった。それが彼の魅力でもあったわけだが……。
形式主義を打破
幼少時の信長は大うつけ者だったといわれるが、実態はどうだったのだろう。
当時は群雄割拠の時代で、織田家も周りを敵に囲まれている状態だった。そのため、信長は敵を油断させるために演技をしていたといわれるが、彼は自分を偽っていつまでも演技を続けられるような人間ではない。信長の性格そのものが発露しただけではないか。もの心ついた頃から自分以外を愚者と断じ、古い社会の慣習をとことん愚弄していた信長が、世間のしきたりに対し、徹底的に反抗するのは当然のこと。彼は、人は徒党を組めば既得権益化するという本質を本能的に嗅ぎ取っていたにちがいない。幕府も公家も宗教も既得権益の塊であり、一度その秩序を破壊しなければならないと頑な思い込んでいたのではないか。
信長は21歳のとき、叔父信光と謀り、尾張守護代織田彦五郎を殺害して清洲城を奪い、そこを自らの居城とする。ついで家臣から人望の厚かった弟信行との対立を制し、25歳のとき、ついに尾張を平定する。
翌年、わずか3千の兵で5万の今川義元軍の本隊を急襲し、義元を討ち取ることに成功する。よく知られている桶狭間の合戦だ。諜報を重視して敵の行動パターンを解析し、地形を考慮しながら敵の急所を突くというやり方は、太平洋戦争時の米軍のようでもあった。
今川が弱体化することで、人質となっていた松平元康(後の徳川家康)が駿河を脱出して三河に居を決めるや、ただちに元康と相互不可侵を主とする清洲同盟を締結。さらに、当時最強と怖れられていた武田信玄の脅威をかわすため、卑屈なまでにへりくだって養女を勝頼に嫁がせる。尊大でわずかな無礼も許さなかった信長が信玄にとった態度は、とうてい同じ人物のふるまいとは思えないほど、おべっかの塊のようであった。必要とあれば、だれにでもへりくだることができるというのは、武士としての妙なプライドに邪魔されていなかったということ。天下布武という大目標の前では、卑屈になろうが残虐の限りを尽くそうがなにほどのこともなかったのだ。
着々と勢力を拡大した信長は、足利将軍家の跡目争いに乗じる。足利義昭を奉じて上洛し、朝廷工作をして義昭を第15代将軍に就かせた。
しかし、彼は義昭の配下で満足するような人間ではない。義昭の将軍としての地位を利用するだけ利用し、天下布武を遂行しようという腹づもりだった。
自分の意のままにならないと気づいた義昭は、各地の大名に教書を発し、朝倉・浅井・武田・毛利・六角・比叡山延暦寺・石山本願寺・伊勢長島の一向宗などによって信長包囲網を形成する。他方、信長が味方と頼むは家康だけ。信長は、比叡山延暦寺を焼き討ちするなどしゃにむに戦うが、甲斐の武田信玄が大軍を率いて上洛の途についたという知らせが入った。いよいよ信長の命運も尽きようかと思われた。
精鋭を率いる信玄は徳川方の城を落としながら進軍し、三方ヶ原では家康・信長の連合軍を大敗させた。
しかし、天は信長に味方する。信玄が急死し、武田軍は甲斐へ引き返すことになる(信長はかなり強運の持ち主とみえ、後に義昭の要望を受けて上杉謙信が上洛しようとした際も、謙信の死という運に恵まれている)。
その後、破竹の勢いで版図を広げる。浅井・朝倉を滅ぼし、伊勢長島の一向一揆では僧徒2万人を焼き殺して平定。天正3年には長篠の合戦で武田騎馬軍団の主力を壊滅させる。さらに石山本願寺を屈服させ、本格的に毛利・上杉攻めを開始するが、その矢先、明智光秀の謀反によって本能寺で自刃する。享年49歳だった。
プロの軍団を組織
ポルトガル人宣教師に随行したイタリア人から鉄砲を使った戦術を伝授してもらい、いち早く銃撃隊を組織したこともさることながら、なんといっても真骨頂はそれまでの戦のやり方を根本的に変えたことだろう。
それまではどの軍団も、兵力の大半を領地の農民に頼っていた。当時の米の重要性はあらためて語るまでもない。よほど差し迫った状況でもない限り、農繁期に農民が戦に駆り出されることはなかった。そのため、戦は主に農閑期に行われた。
ところが、信長は金で兵士を雇い、一年中いつでも戦える軍団を組織した。今から考えれば、特別なことではないかもしれないが、当時、そう考える戦国武将はいなかった。身分、出自を問わず、どんな人間も雇った。当初は「忠誠心がない兵士が何人いても戦力にはならない。金だけもらって戦では逃げ出すにちがいない」と冷ややかに見ていた人が多かったが、信長は戦に負けても信念を変えることはなかった。ひたすら人を集め、戦専門の軍団を拡張させていく。やがてそれが功を奏した。四面楚歌の状況においても、同時に多方面作戦を遂行することができたのだ。
見逃してならないのは、それを可能にした豊かな経済力があったこと。多くの武士は、銭金に対する潔癖感があってか商業振興に対する意識が薄かったが、信長は商業の重要性を早くから認識し、軍団組織に多大な金を費やした。
かつてある新興の実業家が「金で買えないものはない」とうそぶいたが、信長は「金で買えないものもあるが、ある程度まで買うことができる」という現実的な認識をもっていた。そのちがいは、天と地ほども大きい。
人を〝流通〟させる
楽市楽座の発想はそれまでにあったが、それを徹底的に活用したのは信長だ。
天正5年、信長は築城なったばかりの安土城下を楽市とし、商人が自由に出入りできるようにした。同時に座も廃止して規制緩和を断行。安心して人が集まって来られるよう、中山道の通行の安全を保障する宣言も発した。
これらによって多くの人が集まって商いが活性化し、それに引き寄せられて多くの人が集まってきた。通行手形の金にたよらなくても、人が大勢集まればおのずと金は落ちる。信長は世の中の根本原理を理解していたのだ。
当時、経済の基礎は米であったが、米は年に一度しか収穫がなく、消費が滞りやすい。しかし、貨幣での売買は物理的にも決済が容易で、商いの相手さえいれば一年中いつでも取り引きできる。公正な取り引きができるよう、枡の大きさを統一したことも画期的だった。
初めて城下の並木道を整備したのも信長といわれる。人は清潔で美しく、賑わいがあるところに集まってくるということを知っていたのだ(残念なことに、現在の日本のまちづくりはそれと正反対のことをしているように思える)。
延暦寺焼き討ちの功罪
『太平洋の奇跡―フォックスと呼ばれた男』という映画がある(2011年公開)。戦争中、サイパン島において、わずか47人で4万5千人の米軍を巧みに翻弄した大場栄陸軍大尉が主人公である。
そのなかで、米軍のある人物が上官に対し、日本人の特質を説明する際、将棋とチェスのちがいを述べる。
「何が言いたいのだ?」と訝る上官に対し、その人物は、「日本人は敵の親玉を討っても部下は殺さない。味方にして自分の軍の兵員として使う」と説明していた。
しかし例外がある。信長だ。敵に対し、情け容赦はしなかった。必要と思えば、ためらいもなく皆殺しにした。謀反した荒木村重の一族郎党に対する残忍な処刑は、背筋が凍る思いだ。
忠義を尽くした佐久間信盛親子を突如、追放した際も、家臣団を震え上がらせた。彼にとって、長年奉公してくれたという実績など、なにほどの重みもないのだ。つねに〝いま現在の価値〟で人を計った。
神仏をも怖れぬ不届き者――、信長をそう断じ、毛嫌いする史学者も少なくない。事実、戦後の信長の仕置きは徹底していた。時に応じて、降った敵を許すこともあったが、原則として私情をはさむことをしなかった。その日本人離れした非情さと残忍さは比類がない。
信長の悪逆非道の行いといえば、延暦寺の焼き討ちをあげる人も多いが、歴史家の井沢元彦氏は別の角度から評価する。『井沢式「日本史入門」講座2 万世一系/日本建国の巻』で次のように述べている。
――信長以前、延暦寺はじめ宗教集団が武装化し、自分たちと意見が対立する集団を殺戮することが日常茶飯に行われていた。特に延暦寺が日蓮宗の寺を片っ端から焼き討ちし、女子どもも皆殺しにした天文法華の乱で焼けた京都の面積は、応仁の乱のときよりも広大だったといわれる。ところが、信長の延暦寺焼き討ち以来、日本の宗教集団は、おとなしくなった。現代までたどってみても、オウム真理教によるテロなど、ごくわずかしかない。このことの功績は大きい――。
信長は、宗教集団が商人から座銭を取ることも禁止した。本分は神仏に祈ることにあるにもかかわらず、武器をもって勢力を拡大させ、民から金を徴収するなど言語道断だと認識していたのだ。
たしかに信長は残虐非道なふるまいもしたが、それによって社会の悪弊の一部が改善されたことはまちがいない。
「極端」「先鋭」の限界
武田信玄は「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」と言い、武田二十四将という、有力で固い結束の家臣団を得た。恨みが大きな禍根を残すということを知っていたのだ。その点、信長は怨恨の恐ろしさを軽視しすぎた。明智光秀ならずとも、だれかに謀反を起こされただろう。
とはいえ、やはり信長があの時代に登場したことの意義は大きい。なにより戦国の世に終止符を打つ道筋をつけたこと、鉄砲や軍艦など新しい兵器を導入したこと、商工業を興すことが社会善になるということを広く伝えたこと、茶の湯や能など芸術を奨励したことなど、一人の人間が行ったことにしてはあまりにたくさんある。
安土城址を訪ねたときのことだった。信長という男がとほうもなく自信をもっていたをまざまざと思い知らされた。あるいは虚栄心だったかもしれないが、大手門から続く大手道は幅広く、まっすぐ上へ伸びていた。本来、防御を考えれば、曲がりくねった道にするはずだが、防御を考えていない大手道は当時の信長のたしかな自信を表していた。さらに、山の頂上に建てた天守閣は5層7階と頭抜けて高く、地下1階から地上3階までは火に弱い吹き抜け構造だった。
当時、日本に来ていたポルトガルの宣教師ルイス・フロイスは、信長について次のように述べている。
「彼は対談する際、遷延することや、だらだらした前置きを嫌い、ごく卑賤の者とも親しく話をした」
「彼はわずかしか、またはほとんどまったく家臣の忠言に従わず、(略)自らの見解に尊大だった。彼は日本のすべての王侯(大名)を軽蔑し、下僚に対するように肩の上から彼らに話した。そして人々は彼に絶対君主に対するように服従した」
目の前に信長がいるかのような、鮮やかな描写である。
西郷隆盛は革命家、大久保利通は政治家だが、信長は革命家でもあり政治家でもあった。そういう人物は、日本史上、やはり信長以外に見いだせない。
●知的好奇心の高い人のためのサイト「Chinoma」10コンテンツ配信中
本サイトの髙久の連載記事
髙久の著作