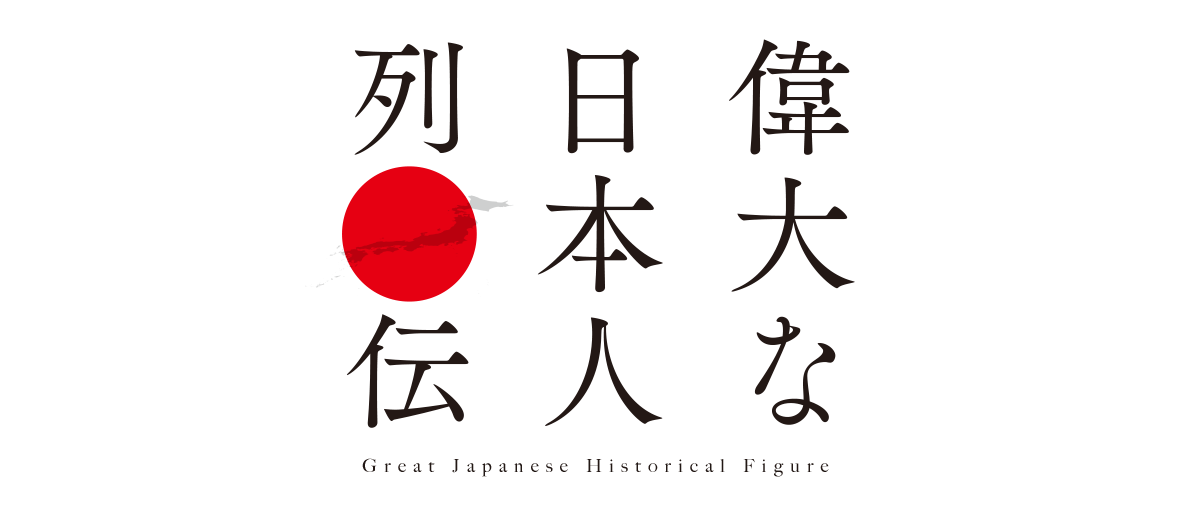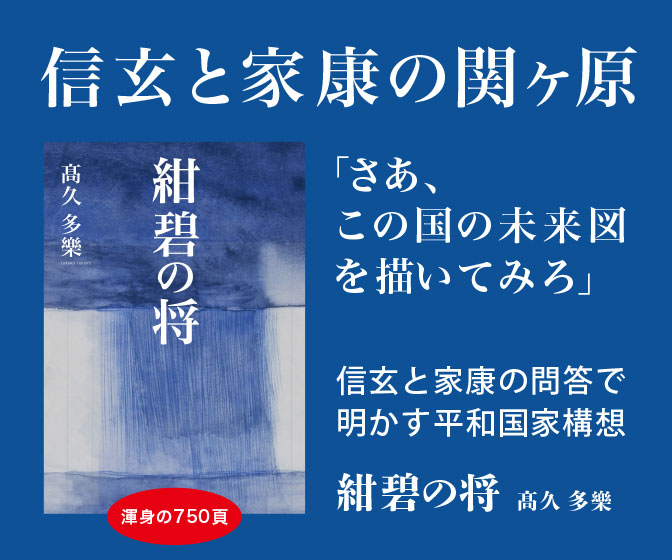リアリズムと大風呂敷の折衷
 もし、後藤なかりせば
もし、後藤なかりせば
昭和通り、靖国通り、晴海通りなど、都心の動脈と言うべき幹線道路がなかったとしたら、今の東京はどのような様相を呈していただろう。あるいは、あったとしても幅員40メートルもの広い道路ではなく、片側一車線ほどの狭い道路だったらどうであったか。
現代人の感覚でいえば、都市計画や区画整理は当たり前のことだが、公共の概念に乏しく、個人財産の私有権が力をもっていた頃に、あのような幹線道路をつくることは想像を絶する困難を強いられた。それをやってのけた後藤新平という男の辣腕に驚く。
また、関東大震災の後、後藤新平が復興院総裁でなかったら、首都圏の復興はどうなっていただろう。後藤は震災の5日後の大正12年9月6日、「帝都復興の議」を閣議に提案している。もし、後藤のような都市計画の知識と信念を抱く政治家がいなかったら、おそらく遅々として進まなかったか、あるいは無計画なままに建築物やインフラが再建され、火災に弱い都市になっていたはずだ。
さらに、後藤が衛生官僚でなかったら、日本の衛生状態はどのようになっていただろう。伝染病で命を落とした人が膨大な数になった可能性が高い。そのようにさまざまな「もし」を考えると、後藤新平という人物の輪郭が浮き上がってくる。
人材煩悩・人間道楽
後藤は安政4(1857)年、岩手県水沢に生まれた。同藩出身には後に総理大臣になった斎藤実がいる。
後藤は、賊軍として人生のスタートをきった。物心ついた頃、世の正義は薩長にあり、佐幕藩出身者は犬猫同様の扱いをされていた。そのような逆境の下、後藤は〝学問を積めば貧しさから脱出できる〟と勉学に励む。
後藤にとって幸運だったのは、江戸城引き渡しに立ち会い、胆沢県大参事として水沢に赴任していた安場保和(横井小楠門下生)に見出され、「公共」と「交易」の思想を教わったことだ。そのときに得た思想は、その後の後藤の骨格になっていく。
どんな成功者にも、〝その出会いがなかったら…〟という人物との邂逅があるものだが、後藤にとっては安場ということになるだろう。後に後藤は、長州閥の元勲や軍人らと交わり、その後ろ盾によって強引ともいえる施策を遂行することになるが、「賊軍出身の若者」がそこに至る道筋をつけることができたのは、明らかに安場との出会いがきっかけになっている。
明治8年、19歳で福島県病院6等生となり、その後、愛知県医学校(現・名古屋大学医学部)に職を得、24歳で病院長に就任。いくら人材不足の時代とはいえ、その若さで医学校の病院長とは驚きである。ちなみに、月給は初任給の20倍にあたる60円に上がっている。
さらに驚くべきことは、病院長という立場ながら、政府に対し次々と建白書を上奏していることだ。そのなかのひとつが内務省衛生局長・長与専斎の目に止まり、内務省衛生局に採用される。時に26歳。賊軍出身者で、権力者に媚びへつらうことなどまったくできない若者を抜擢する空気が、当時の日本にはまだあったのだ。後に後藤は、「人材煩悩」「人間道楽」などと揶揄されるほど、優れた人材を渇望し、これぞと思った人材は強引に引き抜くのだが、その源泉は自らの体験のなかに宿っていたのだ。
明治23年、ドイツへ自費留学し、コッホに師事していた北里柴三郎に会い、さらにミュンヘン大学で衛生学の学位を取得する。帰国後は内務省の衛生局長に就任するのだが、官僚として地歩を築いた後藤に、「衛生のスペシャリスト」として活躍の場が設けられることになる。だが、その前に、大きな艱難が後藤を待ち受けている。
相馬事件に連座し、入獄
後藤は明治26年、お家騒動のひとつ、相馬事件に連座し、鍛冶橋監獄に収監されてしまう。そのきっかけは事件当事者に哀願され、3000万円(今では数億円)の借金をしたことに端を発する。後藤は冷徹な面もあるが、情にもろい面もあり、それが裏目となってしまった。当時、すでに後藤の名声は世間に響いており、よもや自分が収監されることになると思っていなかったらしいが、いったん収監されるや、徹底して闘う姿勢を崩さなかった。立ち上がることさえできない狭さの懲罰房に閉じ込められるが、頑として自分の非を認めなかった。監獄送りを指示したのは、陸奥宗光だと言われている。
最初の大仕事、集団検疫
日清戦争当時、大本営は広島にあった。出獄後、広島へ行った後藤は、中央衛生会委員に就任する。
そして、衛生のスペシャリストとして大きな舞台が回ってくることになる。明治27年、日清戦争に従軍して大陸に渡っていた兵士たちが日本に帰還する際の集団検疫である。あまり知られていないが、遠征軍が帰還する際にその土地の風土病を持ち帰り、伝染病が流行するというケースが多々あった。西南戦争のような国内戦でさえ、その後に伝染病が大流行している。ちなみに、明治10年前後の国内のコレラによる死者は年間約10万人を越えている。
日清戦争の後、大陸から帰還する兵士の数はおよそ24万人。彼ら全員に対し、赤痢・腸チフス・コレラなどの検疫をしなければいけないが、兵士たちは一刻も早く日本に帰りたい。しかし、短期間に集団検疫を行う方法は確立されておらず、兵士たちは過酷な環境の艦船の中で長期間の待機を余儀なくされる。大規模な軍隊が他国で戦った最初のケースでもあり、当時、まだ検疫に対する認識は薄く、現場の軍首脳は「ここで待たされる方がよほど危険だ」ともの凄い剣幕で後藤に詰め寄る。実際、艦内で伝染病が蔓延し、相当数の死者が出たという。
だが、後藤は一歩も譲らない。軍人の威圧をものともせず、自分の思い通りに現場を指揮し続けた。そして、知恵を絞り、世界にも類例がないほどのスピードで集団検疫を実施するのである。圧倒的な権限をもつ現場の軍人に対し、毅然と物言いができた背景には、児玉源太郎の存在がある。児玉は検疫に理解があり、後藤のよき後ろ盾となった。ちなみに、この年のコレラでの死者は約4万人。もし、その集団検疫がなされなければ、数十万から数百万の死者が出ただろうと推測されている。
台湾での活躍
次の活躍の舞台は台湾に用意されていた。日清戦争後、日本は台湾を領有することになるが、当時の台湾は文明の及ばぬ不毛の地であった。激しい反日ゲリラ、蔓延するアヘン、極めて悪い衛生状態など、緊急の課題は目白押しだった。
そのような状況下、またしても後藤を引き立てたのは長州の軍閥だった。2代目台湾総督となった桂太郎が後藤を台湾総督府民政長官に抜擢するのである。
赴任した後藤は、まっさきに水利などのインフラ整備や衛生環境の向上に手をつける。オスマンのパリ大改造など、欧州では衛生対策をきっかけに都市が改造されるケースが多いが、後藤もそれを台湾で実施した。さらに真骨頂といえるのが、大リストラを断行したことだ。台湾総督府はまだ歴史の浅い組織だったがすでに肥大化しており、後藤は1080人もの役人を解雇する一方、仕事のできる官吏には特別手当を支給するなど、強弱をつけた人事を実施した。能力を見込んだ者には借金をしてでも支援するという徹底ぶりだった。
日本人の民族的欠陥ともいえるもののひとつに、組織において公正な懲罰ができないということがある。太平洋戦争時において、更迭された軍首脳がいなかったというのは、それを象徴している。
しかし、後藤はしがらみをいっさい考慮せず、無能な人間をクビにした。おそらく、ただ単にいい仕事がしたかったのだろう。そのためには無能な人間集団では実現できない。「人材煩悩・人間道楽」はそういう面の裏返しとも言えるのである。ちなみに、その頃、農学者・新渡戸稲造を殖産部門に招き入れ、明治35年、新渡戸を通訳として欧米視察に出かけている。
新天地における後藤の施策の基本は、「生物学の原則」に従っていたことも特筆すべきだ。つまり、〝社会の習慣や制度は生物と同じで相応の理由と必然性からできたものであり、それを無視すれば大きな反発を招く〟という考え方である。その土地に合わせた政策が重要であり、支配される側の民心の安定なくして統治することはできない。そのために、現地の文化や風習を調べることに多くの労力を費やした。そこが、「遅れた地に文明をもたらす」という西欧列強帝国主義の方法論と大きく異なる点である。
満鉄総裁に
次なる活躍の場は満州であった。
当初、児玉源太郎から南満州鉄道の初代総裁を打診された後藤は頑なに断っていた。ある日、児玉と激論をした翌日、児玉は急死する。そのことで後藤は意を決し、満鉄総裁という難しい立場に身を置くことになる。
当時、満州は極めてデリケートな地域であった。ロシアのみならず、アメリカも権益を欲しており、日本は難しい満州経営を強いられていた。そのことの失敗が大東亜戦争につながっていく。
満鉄総裁として後藤が据えたコンセプトは、満鉄を「文装的武備」と位置づけることであった。満鉄はただの一企業ではなく、炭坑採掘、水運業、電気業、倉庫業、鉄道付設地における不動産経営、住民への課税を含む行政権をもっていた。それを生かし、軍人の武断政治に対する民政の要と位置づけたのである。つまり、産業を興し、大勢の移民が日本から満州に渡って定着すれば、多大な費用をかけて軍隊を駐留させるよりも外交的な効果が大きい。さらに、大量輸送手段を有しておくことは緊急時に大きな力を発揮する。そのために経済を発展させ、人心をとらえる文化力を養うことが肝要としたのである。
また、鉄道による東西文明の融和が後藤の満鉄経営の肝でもあった。
後藤は、ロシアの脅威が増す時期にあっても、中国・ロシアとの協調こそ日本が生き残る道であると説いていた。そのために、世界をつなぐ鉄道として、満鉄をとらえてもいた。
それまで日本の鉄道の軌道は狭軌(106.7cm)だったが、後藤は世界標準の広軌(143cm)を採用するなど、ここでも旧来の発想にとらわれることなく自分の信念を貫いている。
後藤は長春の都市計画にも携わるなど、多方面でその才能を発揮するが、満州を去った後、満鉄は軍や政党の干渉を許すことになるのである。
関東大震災後の大風呂敷
大正9年、原敬から依頼を受けた渋沢栄一の斡旋をうけ、後藤は東京市長に就任する。「都市研究会」を発足させ、会長に就任していた後藤にとって、うってつけの役職だった。就任後、すかさず東京市民に対し6万5000通のアンケートハガキを送り、市政に関する意見を求め、それらを参考にしながら8億円の都市計画を発表する。
そして、あの日がくるのである。大正12年9月1日、マグニチュード7.9の関東大震災が発生。木と藁と紙でできたような東京は一瞬のうちに燃え広がり、おびただしい焼死者を出すことになった。
その翌日、後藤は組閣中の山本権兵衛邸へ行き、内務大臣を引き受け、5日後に復興案を閣議提案するのである。と同時に、自邸を開放して被災民1000人余りを受け入れる。
復興案のコンセプトと概要は、東京を再び火災に弱い帝都に復旧するのではなく、抜本的な都市改造を図る「復興」を目指すというものであり、以下の四つに集約されていた。
一 遷都をしない。
二 復興費用は30億円(当時の国家予算13億円)。
三 欧米最新の都市計画を用い、日本にふさわしき新都を造営する。
四 都市計画を実行するため、地主に対して断固たる姿勢をとる。
であった。都市とは効率的に人やモノ、資本、情報を流通させるという概念に基づいていた。
しかし、後藤の広げた大風呂敷は、政敵・政友会に批判され、計画は縮小を余儀なくされる。当時の大臣で、都市を社会的公器ととらえている人は皆無といってよかった。そのことについて、昭和天皇が遺憾の意を表明された。
後藤は大風呂敷と揶揄されることが多かったが、その背景には「大金で世の中をよくする」という思想があった。ただし、大風呂敷を広げるばかりではなく、畳み方も知っていた。個人として金に執着はなかったが、公器としての金にはこだわったのである。
後藤新平といえば、「自治三訣」と連想する人も多いだろう。「人のお世話にならぬよう。人のお世話をするよう。そして報いを求めぬよう」という言葉にこそ、後藤新平の人生哲学が凝縮されている。
天下国家を見据えるマクロなまなざしとプラグマティックな行動力。情にもろいロマンチストでありながら、平気で大勢のクビをきるリアリスト。自らの人生を肯定する野心家・自信家・楽天家でいながら反骨と反権力の気風に富んだ激情家。後藤新平はさまざまな顔をもつ傑物であった。
後藤の肉声は後藤新平記念館の公式サイトで聞くことができる。朴訥な東北弁は風貌に似合わず、とても人間味を感じさせる。
●知的好奇心の高い人のためのサイト「Chinoma」10コンテンツ配信中
本サイトの髙久の連載記事
髙久の著作