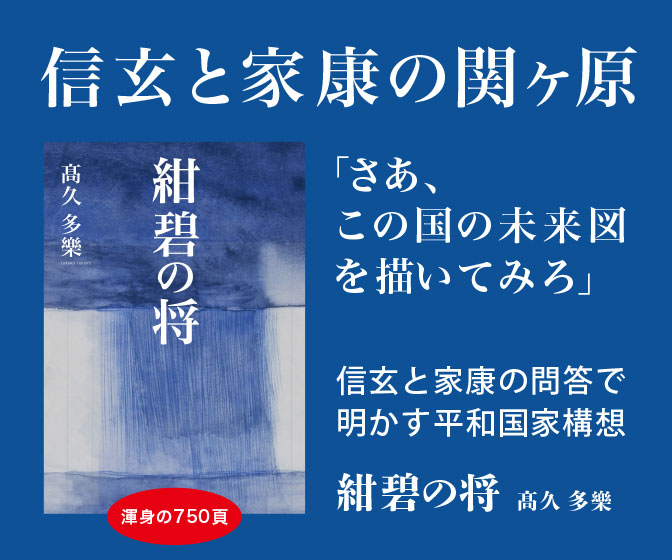現代の日本人が忘れてしまった日本の心を演劇という枠を越えて伝えていきたい。
演劇人、「国際劇団 アユリテアトル」団員近藤春菜さん
2018.07.11
 パリのジャック・ルコック国際演劇学校を卒業した6人のメンバーで結成した「国際劇団 アユリテアトル」。メンバーは日本、カナダ、スウェーデン、フランスと国際色豊か。その中の一人、近藤春菜さんは『Japanist』でもお馴染み、近藤隆雄氏のご息女であり、本欄でも紹介したゲルタイス菜々さんは妹です。演劇を深く学ぶため、日本を飛び出し海外で見つけた日本の心。現代の日本人が忘れてしまったその心を、演劇という枠を超えて広く伝えていきたいと、世界各地で創作公演やワークショップなどのさまざまな活動を積極的に行っています。
パリのジャック・ルコック国際演劇学校を卒業した6人のメンバーで結成した「国際劇団 アユリテアトル」。メンバーは日本、カナダ、スウェーデン、フランスと国際色豊か。その中の一人、近藤春菜さんは『Japanist』でもお馴染み、近藤隆雄氏のご息女であり、本欄でも紹介したゲルタイス菜々さんは妹です。演劇を深く学ぶため、日本を飛び出し海外で見つけた日本の心。現代の日本人が忘れてしまったその心を、演劇という枠を超えて広く伝えていきたいと、世界各地で創作公演やワークショップなどのさまざまな活動を積極的に行っています。
自分らしさに気づいた演劇との出会い
先日は横浜ボートシアターの舞台「さらばアメリカ!」に招待していただき、ありがとうございました。以前、拝見した「恋に狂いて」とはかなりタイプの異なる舞台でしたね。個人的には前回の方が情緒があって好きですが、評判はいかがでしたか。
評判は良かったですよ。人それぞれ好みはありますよね。今回は89歳の演出家、遠藤啄郎さんの体験を元に戦後の日本を描いた舞台でしたから、世代によって感想に差があるのが印象的でした。特に、戦争を体験していない私達の世代には現実にあったこととは信じられないエピソードも多く、理解に苦しんでいる姿も見られました。ただ、その時代を生きた方々からは、さまざまな体験談とともに「良かった」「あの頃を思い出した」というような感動の言葉をたくさんいただきました。私自身も、最初に台本を読んだ時には「え? これ本当にあった話なの?」と混乱しましたが、読めば読むほど毎回新たな発見があり、現代との深いつながりに気づかされ、最後には深く心を揺さぶられた作品です。ぜひ若い世代の人たちにこそ観ていただきたいです。
そうですか。ところで、春菜さんは、いつから演劇を始めたのですか。
中学生の頃からです。父が若い頃、英語劇をやっていたこともあって勧められ、英語劇部に入りました。
英語劇といってもお客さんは大多数が日本人です(笑)。物語を伝える際、セリフには頼れません。その分、言葉以外の部分、例えばリズム、抑揚、間、呼吸、身体表現などを駆使するなど、工夫が必要でした。その頃から、私の中では自然と「コミュニケーションは言葉だけではない」という意識が培われていったのだと思います。中高時代は、ちょっとした言葉の行き違いで誤解が生まれたり、なかなか素直に振る舞えなかったり、と人間関係で悩むことが多々ありました。しかし、舞台の上では素直になれる自分がいる。思い切り全身全霊で表現しても受け止められる、ということがわかってから、舞台は自分にとってかけがえのない、大切な場所に変化していきました。
 大学でも演劇を?
大学でも演劇を?
はい。戦前から続く伝統ある英語劇大会に毎年出演し、演劇づけの毎日を送っていました。特に1年の時に参加した大会では、「LOST IN YONKERS」という作品のBELLA役でベスト・パフォーマー賞をいただきました。BELLAは、体は40歳、心は子供のままという複雑な女性で、その人物の気持ちを少しでも理解するために、彼女になりきって毎日過ごしていました。実際、電車の中で突然泣き出したり、笑い出したりということもやってみました。当然、周りは驚きますよね。隣りに座っていたおじさんが「大丈夫? おじさんに話してごらん」と言いながら抱きついてきたときは、身の危険を感じました。それでも、「台本に書かれているセリフを少しでも自分のものに近づけるためには日常生活の中でいかに行間を埋めるかが大切だ」と思い、そうやって、どのような役になっても全力で役作りをする日々でした。その甲斐あってか、クライマックスで母親に「子供が欲しい、愛が欲しい」と訴え、拒絶され、泣き崩れるシーンでは、800人くらいいたお客さんの空気が一体になり、会場全体が凍りつき、そして私が崩れるのと同時に空間自体も崩れていったのを全身で感じました。背筋が凍りついた感覚を今でも鮮明に覚えています。その「LOST IN YONKERS」の舞台で、私の所属していた立教大学ESSドラマプロダクションは、ベストパフォーマー賞、イングリッシュプライズ、ステージエフェクト、グランドプライズ、すべての賞を受賞し、総合優勝を果たしました。
それほど演劇にのめり込むと、実生活に支障はでますよね。
はい。役が決まったら朝から晩までずっと舞台のことばかり。そのため、大学時代は単位が取れず卒業が危うかったです(笑)。舞台は打ち上げ花火のようなもので、本番が終わると今までの生活が跡形もなく消え去ってしまいます。そのため、のめり込みすぎていた私は、本番が終わった後に虚無感に襲われ、リカバーするのに半年くらいかかりました。しかし、それでは現実に適応できません。役と自分自身をコントロールできるのがプロです。役者を職業とするつもりはありませんでしたが、演劇を続けていくためには、もっと自分を見つめなおす必要があると思い、海外へ演劇を学びにいきました。
役者になろうと思っていたわけではないのですか。
実は私、幼い頃から虫や生き物が大好きで、ずっと動物や自然環境に関わる仕事がしたいと思っていました。動物の心を理解し、コミュニケーションが取れるようになりたい、と大学では心理学を専攻しました。また、アメリカのシーワールドでイルカ飼育のキャンプに参加したり、屠殺場を巡ったり、NGOに参加して中国の砂漠地帯に植林に行ったり、いろいろと試したのですが、どうしても役に立たなくて(笑)。樹を植えるどころか、凍った砂漠の土を掘ることすらできず、植林に行っても結局村の子供たちと一緒に人形劇創りをしていました。紆余曲折を繰り返しましたが、そんな中で自分の軸は演劇だと気づくことができたのは良かったです。生かすも殺すも人の心なら、人の心や感性を開いていく仕事がしたい。そのために今まで演劇で培ってきた経験は、手段として活かせるのではないか。そう思い、大学の卒業時には「臨床心理現場における演劇と仮面の役割」というテーマで論文を書きました。
能面(内向)とニュートラルマスク(外向)の効用
演劇と心理学を結びつけるのですか。
はい。イギリスでは、「応用演劇」といって、教育や心理などさまざまな現場で演劇を活かしていく分野があります。当時、日本ではまだ新しい概念であまり理解されなかったため、まずは実践と理論両方が必要だと、イギリスの大学院で修士をとりました。その後、どうしても行きたかったパリのルコック国際演劇学校にて、仮面を使ったさらに実践的なトレーニングを積みました。
 それは、どういうものですか。
それは、どういうものですか。
「身体言語こそが人間の共通語である」という考えのもと、身体が何を語っているかを読み解き、また、表現する身体を鍛えていくトレーニングです。人は、言葉で嘘をつけても、身体では嘘をつけません。身体と心は密接に関係し、すでにさまざまなことを語っています。そこには国の壁はない。ルコック校には毎年約30カ国からアーティストが集まり、国や言葉、文化、教育などの違いを越え、人間としての本質的な表現は何かを実践的に探っています。特に私が魅かれていたのが、ニュートラルマスク(中性面)、という仮面を使ったトレーニングです。表情や個性のない面をつけることで、普段、無意識にやっている動きや癖が削ぎ落とされて、偏りのない、バランスのとれた自然な動きができるようになるというものです。このニュートラルマスクは、日本の能面から影響を受けてつくられたそうです。たとえば、人には個性というものがありますよね。その「個性」だと思われているものは、環境や人との関わりの中でつくられたものがほとんどで、本来の自分の姿とはかけ離れていることが多い。つまり、仮面をかぶっている、偏りがある状態です。それを、心理学ではペルソナと言うのですが、その仮面を取り外し、生まれたままの姿を再発見することが、本来の自分を取り戻すことにつながると考えられています。本来の自分を再発見することで、心を取り戻し、もともと持っている本当の意味での個性が発揮されるようになると。ニュートラルマスクは、その力を引き出すことができるのです。
それは面白いですね。海外にも能のような面があったとは驚きです。
お能には客観的な目を持って自己を見つめるという「離見の見」というものがあります。これは禅にも通じていて、自分のことを客観的に見つめることができてはじめて、バランスのとれた自然な状態になれると考えます。ルコック校のトレーニングでも、ニュートラルマスクを使い、この客観的な目を育むことをとても重視しています。ただ、能面はほとんど前が見えないように作られているのに対し、ニュートラルマスクは目の部分がはっきりと見開かれています。これは、お能が内に向かって意識を高め、イメージの世界を広げていくのに対し、ニュートラルマスクは外に意識を広げ、子供のように無邪気に世界を発見し、外にイメージの世界を描いていくという違いがあります。内向と外向、集中の方向性は違っても共通しているのは、無駄な自意識を捨て「今、この場所に、ただいる」ことが表現する上で何においても一番重要ということです。
海外には、日本の文化に魅了された人たちがたくさんいて、ニュートラルマスクのように日本文化や芸術から影響を受けたものが数多くあります。日本を外から見ると、あらためて日本の良さに気づかされることが多いです。
「国際劇団 アユリテアトル」の挑戦
ジャック・ルコック国際演劇学校を卒業後、6人の多国籍メンバーで「国際劇団 アユリテアトル」を結成しましたね。
ルコック校での体験やそこから生まれてくる舞台があまりにもユニークで面白く、素晴らしかったので、これが日本でも実現できたらいいな、と思い結成しました。まったく違う背景や価値観を持つ人たちが、国や文化、老若男女すべての壁を越えて一体となって笑い、感動できるような舞台。役者たちは皆、一人ひとりが出る杭となり、違いを活かしながら、根底の部分では協調しつながっているような関係性で、創作期間は、毎日大笑い、時には本気でぶつかり合い、本当に充実して楽しいです。アユリテアトルの作品では、舞台上で基本的に役者は皆自分の母国語を話しますが、身体表現や言葉の音楽性などで、何ヶ国語が混じっていても理解できるようにさまざまな工夫をしています。
 芥川龍之介の作品を上演していますね。
芥川龍之介の作品を上演していますね。
はい。芥川関連では2作品舞台化しました。一つは、「藪の中」で、2005年にアユリテアトルのメンバーが初来日した際にたまたま読んだことがきっかけです。日本で約2ヶ月共同生活する中で、ぶつかり合い、皆それぞれ文化の壁に悩んでいました。特に多国籍の人が集まると、皆、正しいと思っていることが違います。同じ経験をしたはずなのに、主観によって真実が違ってしまう。その時にたまたま読んだ「藪の中」が、その当時の私達が直面していた問題を見事に描いていて、外国人メンバーが感動し、舞台化が始まりました。この芥川龍之介の小説をベースにした『藪の中-Distruthted-』は、2007年の夏、カナダで毎年行われる演劇祭『トロント・フリンジ・フェスティバル』でベスト・アンサンブル賞に選ばれました。また、その後もカナダのメンバーが芥川作品に自伝を含めすべて読むほどのめり込み、芥川の人生を、「鼻」「馬の脚」「地獄変」という彼の作品を通して舞台化しました。その作品、「A FOOL’S LIFE-或阿呆の一生-」は、2011年に、カナダで最も名誉ある演劇大賞DORA AWARDSで全6部門ノミネート、音楽賞を受賞しました。海外では夏目漱石や芥川龍之介などの作品も、わかりやすく訳されていて、若い人たちにも人気です。日本だと「芥川は難しい、古い」など固定概念がありますが、海外ではそのような色眼鏡がない分、皆、素直に作品の面白さ、コミカルさ、現代とのつながりを感じて作品を楽しんでいます。「A FOOL’S LIFE-ある阿呆の一生-」の舞台では多くの人たちがお腹を抱えて笑い、共感し、感動する姿を目の当たりにし、日本人である私にとってとても新鮮でした。
現在は「妖怪」をテーマに作品作りをされているようですが。
2011年から「-妖怪- MONSTER PROJECT」に取り組んでいます。2017年2月にカナダで第1回公演をしました。これは、私が日本の妖怪が大好きで、カナダにいた際の気分転換に「YOKAI OF THE DAY」と、毎日1匹(?笑)ずつ、妖怪をカナダ人に紹介していたのがきっかけです。日本の妖怪は、必ずしも攻撃してくるわけではなく「ただそこで小豆を研いでいるだけ」とか、べとべとさんのように、「べとべとさん、お先にどうぞ」と言えば去っていく、とか、タヌキのように袋をさまざまな形に変化させて飛んだり踊ったりするコミカルキャラクターという豊かな世界観がカナダ人にとっては驚きで新鮮だったようです。「妖怪」を英語にしようとすると「MONSTER」と訳されてしまいます。しかし、「MONSTER」と訳した時点で、妖怪の持つ豊かさが失われて別物になってしまう。妖怪は、自然現象がベースになっているものが多く、ただそこにいて、こちらが悪さをしなければ大抵は危害を加えてこないが、「MONSTER」は人間が変身した姿で必ず人間に危害を加えてくる。この「妖怪-MONSTER-」というテーマに取り組んだ時点で、日本人と西洋人の自然とのつき合い方、宗教観、価値観の違いなどがどんどん浮き彫りになってきました。その違いを稽古場でとことん突き詰め、遠慮せずにぶつけ合い、時には本気でケンカし、振り返りながら物語を創っていき、最終的には、その経験がすべて凝縮されたとても面白い舞台作品に仕上がりました。「A FOOL’S LIFE-或阿呆の一生-」も「妖怪-MONSTER-PROJECT」もカナダでとても評判が良かったので、ぜひ日本の方々にこそ観ていただきたいです。いずれは日本で公演するのが夢です!
演劇の要素を活かした新しい取り組み
現在は、舞台の他に、ワークショップもされているようですね。どういう活動をされているのですか。
一般の人はもちろん、企業研修などでニュートラルマスクを使ったワークショップを行っています。父が行っているサムライ塾でも取り入れていますが、受講した方たちは明らかに体験する前とした後の目の輝きや表情、存在感が変化します。
また、演劇ということであれば、発達障害を持つ子供たちにもワークショップを行っています。これは主に身体表現を活かした演劇創りをするものです。何か感じていることがあるけど、言葉でうまく表現できない。そのような時は、実は身体で動いてみるほうがしっくりくる表現を見つけられるものです。まずは動いてみる、するとそこから言葉が生まれてくる。また、演劇創りに夢中になることによって、自分でも気づかぬ間に表現し、主張し、受け入れられ、コミュニケーションを取っていた、という体験を積み重ねることができます。このワークによって、まったく話さなかった子が話せるようになったり、と親や先生たちが驚くような変化がみられることもありましたよ。
私のワークはとてもシンプルで、体験し、見ればすぐにわかることです。しかしその分、言葉で説明するのには苦労していて、いろいろなところから「読み物が欲しい」「教科書を作ってくれ」と言われ続けています。そのため、いずれ体系化して、テキストにまとめるというのが今後の目標です。
それは楽しみですね。それが実現すれば、いろいろな場面で使えそうですね。二人目のお子さんも生まれて大変な中、演劇に仕事にとお忙しいことと思いますが、頑張ってください。期待しています。
 ありがとうございます。
ありがとうございます。
(写真上から:LOST IN YONKERS BELLA、ニュートラルマスク、「鼻」或阿呆の一生より、 子連れでWS)
国際劇団アユリテアトル
https://www.ahuritheatre.com/jp/