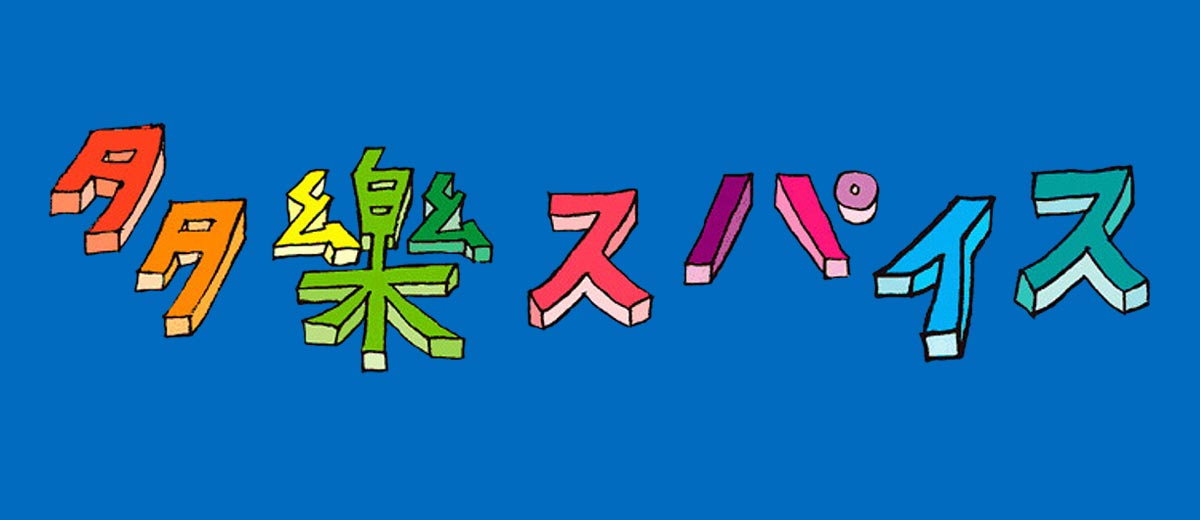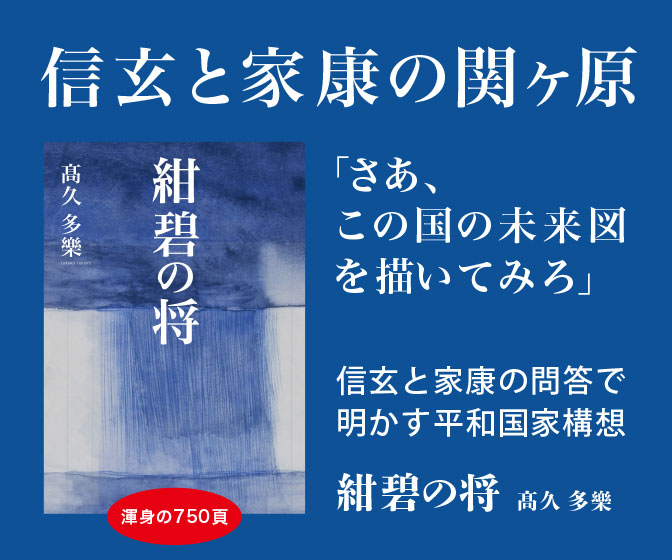いたるところ小説の舞台
 バルザック、デュマとくれば、自動的にヴィクトル・ユゴーという名が導き出される。19世紀に活躍した3人のフランス人作家について書かれた鹿島茂氏の『パリの王様たち』を読むと、彼らが作品だけではなく、人物としてもいかに傑出していたかわかる。
バルザック、デュマとくれば、自動的にヴィクトル・ユゴーという名が導き出される。19世紀に活躍した3人のフランス人作家について書かれた鹿島茂氏の『パリの王様たち』を読むと、彼らが作品だけではなく、人物としてもいかに傑出していたかわかる。
とにかく放蕩の限りを尽くしたといっていい。膨大な借金を重ね、道楽につぎこんだ。性欲、食欲、名誉欲ともに人並み外れ、今の世に生きていれば、そのまま「生ける伝説」になれただろう。
ユゴーは代表作『レ・ミゼラブル』だけで判断すれば、いかにも聖人君子風だが、その実、女性と見れば目がランランし、80歳を過ぎてなお息子の嫁だか恋人にまでちょっかいを出したというツワモノ。実際、「千人斬り』に近いことをしていたらしい。
それでもフランス人はおおらかで、ユゴーを特別な国民的英雄と見ている。日本人が富士山を愛するがごとく、フランス人はユゴーを愛し、誇りにしている。つまり、フランス人の懐の深さといおうか、「偉大な人なんだから、そういう面もあっていいんじゃない?」という考え方があるのだと思う。以前、ミッテランかシラクに何人もの愛人がいることが発覚したが、ほとんどのフランス人は、「だから、なーに?」とまったく意に介していなかった。
ところで、前回に続き、小説の事実化である。セーヌ川にかかるアルマ橋のたもとに地下下水道入り口がある。実はこれ、名前の通りパリの地下を流れる下水道への入り口なのだ。パリの地下にはすでに19世紀、広大な地下下水道が敷かれていた。そこを舞台にしたのが、あの世界的傑作『レ・ミゼラブル』である。ラストの場面、ジャン・バルジャンが愛娘コゼットの許婚マリユスを助け、背負いながら地下下水道を歩く場面である。子どもの頃は『ああ無情』の名で親しみ、長じてから完全版を読み、深い感銘を受けた。
私はどうしてもその現場が見たくて、地下下水道に入りこんだ。もちろん、薄暗いし、異臭もある。「いったい何が悔しくて、こんなところに来ているのか?」と素朴な疑問を抱きつつ歩を進めると、ありましたありました。なんと、ジャン・バルジャンがマリユスを背負っているシーンを描いた図が壁に掲げられている。まるで、ここがそのシーンの現場ですよ、と言わんばかりに。
結局、前回書いたシャトー・ディフと同様、あくまでもフィクションなのに、あまりにも人々の脳裏に強烈に焼き付いてしまったために「事実化」してしまったのである。
いいな、そういうのって。
「フランスはいいところだ。フランス人さえいなければ」というイギリスのジョークはたしかに言い得て妙だが、一方、フランス人ほどわかりにくく面白い人間はいない(西洋人は、日本人の方がわかりにくいと言うだろうが)。
(110426 第246回 真はパリの地下水道にある、『レ・ミゼラブル』のワンシーンを描いた図)