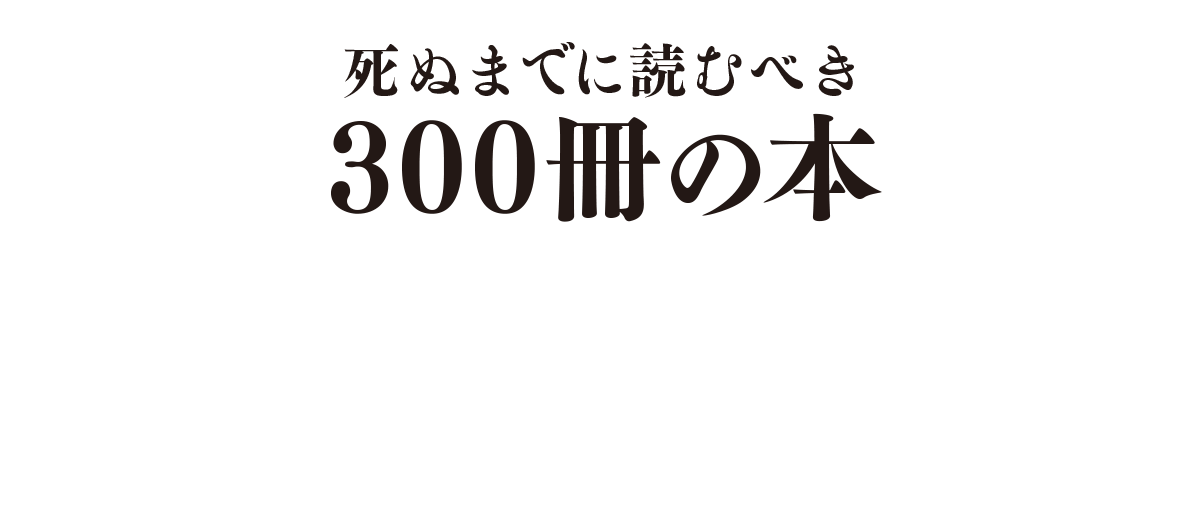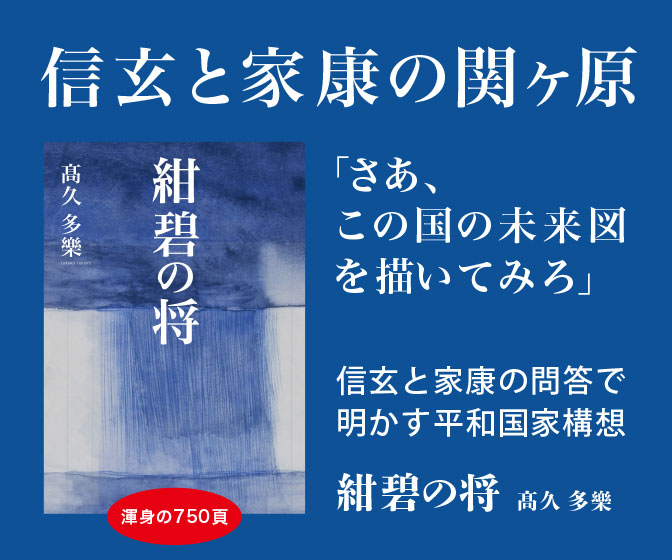「この小説には人生のすべてが詰まっている」

読み終えて、魂を鷲づかみされるような、心が打ち震えるような深い感動に包まれた。
長い長い小説だ。数々の名作を世に出した宮本輝が、足かけ37年を要して書き上げた。
著者の父をモデルにした物語は大河のごとく、ゆっくり流れる。市井の人間の流れとはそういうものだろう。激しく転変する人生は、つくりものだと教えてくれる。
本作は1982年から2018年にかけて発表された。「流転の海」「地の星」「血脈の火」「天の夜曲」「花の回廊」「慈雨の音」「満月の道」「長流の畔」「野の春」という全9巻構成だ。
すべてを書き終えた宮本輝は、ある新聞のインタビューでこう答えている。
「この小説には人生のすべてが詰まっている」
それが少しも大げさに感じない。松坂熊吾という人物を主人公に、多くの人間が複雑な綾を織りなすようにからんでくる。登場人物は1200人以上。彼ら彼女らは、すべて市井の人たちだ。広く世間に名の知られた人は一人もいない。
人生は、なんらかの縁があって出会う人たちとの「作用・反作用」の集大成ともいえる。性格も来歴も立場も異なる無数の人間が交わり、無限ともいえる「作用・反作用」の連なりの線上に生きている。「○○したから○○になる」という紋切型の結果になるとは限らない。こういうスケールの大きな完成された小説を読むと、「論語」は平板で紋切型と思えてしまう。あくまでもビッグデータ的な人間観だからしかたがないが、「論語」や老荘思想、そしてあらゆる宗教の唱えている通りにならないというところが人生の妙味である。いいことを施したからいい結果につながるとは限らないのだ(反対に、悪いことをした人がいい結果になることはほとんどないが)。
物語は、大阪を舞台に、終戦直後から始まる。戦争に負け、だれもがその日生きるのに必死。現代から見れば、あまりにも過酷だが、当時を生きる人たちに悲壮感はない。艱難辛苦の日々が当たり前なのだ。そういう時代を力強く生き、自らの人生の計を切り拓いていった〝ふつうの人たち〟の熱気が行間から立ち上ってくる。
最終巻「野の春」のあとがきで、著者はこう書いている。
――37年もかけて、7000枚近い原稿用紙を使って、なにを書きたかったのかと問われたら、「ひとりひとりの無名の人間のなかの壮大な生老病死の劇」と答えるしかない。
そう、この物語では多くの生と死が描かれている。人間ばかりではなく、さまざまな生き物が生まれ、死んでいく。どんな理由か知らないが、この世に生まれ、そして死んでいく。与えられた生の時間のなかで、それぞれの命を消化する。完全燃焼する人もいれば、生涯くすぶっている人もいる。
主人公の松坂熊吾は過剰なくらいにスケールが大きく、熱血漢で情け深く、世の中を見通す目を持っている。しかし、それらの資質がすべて吉と出るとは限らないところが人生の難しさだ。事業を起し、成功するものの、死ぬときはすべてを失ってしまうのだ。50歳で息子をさずかり、「この子が成人式を迎えるまでわしは絶対に死なない」と心に決め、それは成就するものの、その間に失うものもはかりしれない。
とりわけ使用人に恵まれない。お節介を焼くが、ことごとく裏切られる。ひとことでいえば、人を見る目がないのだが、そうさせているのは虚栄心だろう。自分を等身大以上に見せたくて、つい背伸びしてしまう。それが他人への施しとなって現れるが、つけ入るスキを与えることにもなる。施した人が平身低頭し感謝してくれれば一時的に満足する。しかし、それが凶と出ることもある。事業も背伸びする。妻の房江はそのあたりの加減を知っているが、それを言えば暴力を受けるから言わない。やがて、少しずつ傾いていく。
ラストは静かで荘厳だ。体の自由や言葉まで失った熊吾は、鉄格子のついた精神病院に収容される。最期の面会に訪れた妻と息子を見て、熊吾の顔は歪み、そしてたちまち泣き顔になった。両の目から涙を流し、泣いた。幼児と同じ泣き顔で妻と息子をしばらく見たのち、目を閉じ、それきり反応しなくなった。
あらん限りのエネルギーを使い果たして死んでいく松坂熊吾の最期は、著者の父に対する壮大なオマージュにちがいない。